「就労移行支援って、なんだかおかしいって聞くけど本当?」
「利用してみたいけど、ネットの悪い評判が気になって一歩踏み出せない…」
障害のある方の就職をサポートしてくれる「就労移行支援」。しかし、インターネットで検索すると「おかしい」「やばい」「意味ない」といった不安を煽る言葉も目に入り、利用をためらってしまう方も少なくないでしょう。
結論から言うと、就労移行支援に関するネガティブな評判には、残念ながら事実も含まれています。 しかし、その多くは「一部の質の低い事業所」の問題や、「利用者と事業所のミスマッチ」が原因です。
大切なのは、悪い評判に惑わされて可能性を閉ざしてしまうことではなく、「おかしい」と言われる理由の正体を知り、自分に合った信頼できる事業所を見極める力を身につけることです。
この記事では、元利用者の声や客観的なデータも交えながら、以下の点を徹底的に解説します。
- 就労移行支援が「おかしい」と言われる7つの理由とその背景
- 絶対に避けるべき「やばい」事業所の具体的な特徴
- 後悔しないための事業所の選び方と、利用中の対処法
この記事を最後まで読めば、あなたは就労移行支援に対する漠然とした不安を解消し、自信を持って就職への一歩を踏み出せるようになるはずです。
記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。
読み間違いがありますが、ご容赦ください。
▼就労移行支援は「おかしい」?後悔しない選び方と活用術~ネガティブな評判の真相に迫る

なぜ?就労移行支援が「おかしい」と言われる7つの理由
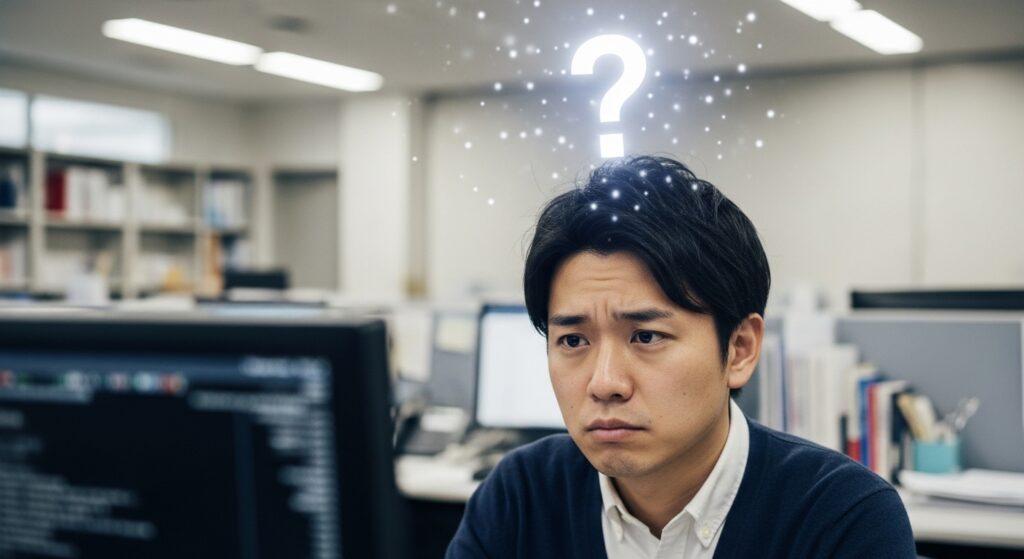
多くの人が「おかしい」と感じるポイントは、ある程度共通しています。まずは、その代表的な7つの理由と、なぜそうした状況が生まれてしまうのかを具体的に見ていきましょう。
理由1:プログラム内容が「おかしい」
「毎日Excelの同じ作業ばかりで、スキルが身についている気がしない」
「正直、小学生レベルの課題をやらされて、時間を無駄にしているように感じる」
これは、最もよく聞かれる不満の一つです。本来、就労移行支援は一人ひとりの特性や目標に合わせた「個別支援計画」に基づいてプログラムが組まれるはずです。しかし、事業所側のノウハウ不足や人員不足により、全員に画一的なプログラムを提供しているケースがあります。これでは、自分の目指す職種に必要なスキルは身につきません。
理由2:スタッフの対応が「おかしい」
「相談しても『あなたの頑張りが足りない』と精神論で返される」
「スタッフの専門知識が乏しく、キャリア相談にならない」
利用者にとって、スタッフは就職活動の伴走者となる重要な存在です。しかし、残念ながらすべてのスタッフが高い専門性と熱意を持っているわけではありません。高圧的な態度を取ったり、親身に相談に乗ってくれなかったりするスタッフがいる事業所では、安心して通所を続けることは困難です。
理由3:就職実績が「おかしい」
「就職率90%と聞いて期待したのに、すぐに辞めてしまう人ばかりだった」
高い就職率をアピールしている事業所は多くありますが、その数字には注意が必要です。実は、「就職率」の計算方法は事業所によって異なり、アルバイトでの就職を実績に含んでいたり、短期間で退職したケースを除外していたりする場合があります。
本当に注目すべきは、就職後の定着率です。厚生労働省の社会福祉施設等調査などによると、就労移行支援を利用して就職した方の職場定着率は平均82.3%となっています。ただし、障害種別によって定着率に差があり、精神障害では49.3%、発達障害では71.5%といったように異なります。
数字の表面だけでなく、「どのような企業に」「どのような職種で」「どれくらいの期間働き続けているか」という実績の「質」を確認することが不可欠です。
理由4:利用者層の雰囲気が「おかしい」
「周りの利用者のやる気が感じられず、自分のモチベーションも下がってしまう」
就労移行支援は、さまざまな障害特性や年齢、目標を持つ人が集まる場所です。そのため、時には事業所の雰囲気が自分に合わないと感じることもあります。特に、自分の障害特性(例:発達障害)に特化していない事業所の場合、他の利用者とのコミュニケーションやプログラムのペースに馴染めず、孤立感を深めてしまうケースも見られます。
理由5:ルールの厳しさ・自由度が「おかしい」
「スマホの持ち込み禁止、私語厳禁など、ルールが厳しすぎて息が詰まる」
「逆に自由すぎて、何をすればいいか分からず1日が終わってしまう」
事業所の方針によって、ルールの厳しさは大きく異なります。一般企業に近い緊張感を求める人もいれば、自分のペースで安心して過ごせる環境を求める人もいます。どちらが良い悪いではなく、事業所が提供する環境と、自分が求める環境との間にミスマッチがあると、「おかしい」という不満に繋がります。
理由6:費用・お金の面で「おかしい」
「利用料は無料でも、交通費や昼食代が毎日かかり、生活が苦しい」
「後からテキスト代として追加料金を請求された」
就労移行支援の利用料は、前年度の所得に応じて決まり、約9割の方が自己負担0円で利用しています。しかし、事業所に通うための交通費や昼食代は原則自己負担です。この点を事前に理解していないと、想定外の出費に繋がります。また、悪質なケースでは、本来不要な費用を請求されることもあるため注意が必要です。
理由7:そもそも制度自体が「おかしい」と感じる
「利用できる期間が原則2年間と決まっていて、焦ってしまう」
「通ったからといって、必ず就職が保証されるわけではない」
就労移行支援は、あくまで就職に向けた訓練とサポートを提供するサービスであり、「就職そのもの」を保証する制度ではありません。また、利用期間が原則2年(最長で1年の延長が可能)という上限もあります。こうした制度の仕組みを正しく理解せず、「通いさえすれば何とかなる」と過度な期待を抱いていると、現実とのギャップに「おかしい」と感じてしまうことがあります。

要注意!避けるべき「やばい」就労移行支援事業所の特徴5選
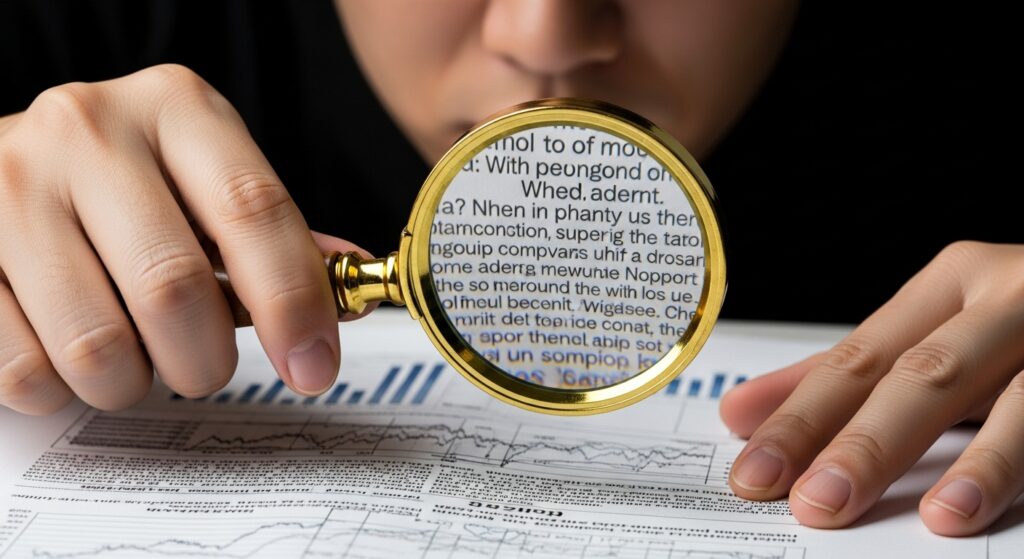
では、具体的にどのような事業所を避けるべきなのでしょうか。ここでは、入所してから後悔しないために、事前に見極めるべき「やばい」事業所の特徴を5つご紹介します。
| チェック項目 | 具体的な危険サイン |
|---|---|
| 1. 見学・体験時の対応 | ・質問に対して曖昧な答えしか返ってこない。 ・施設の良い点ばかりを強調し、デメリットを説明しない。 ・見学当日に契約を迫るなど、決断を急がせる。 |
| 2. 就職実績の根拠 | ・「就職率」の高さばかりをアピールし、「定着率」を公開していない。 ・就職先の企業名や職種について、具体的な事例をほとんど示せない。 |
| 3. プログラム内容 | ・個別支援計画についての丁寧な説明がなく、全員が同じプログラムを受ける前提で話が進む。 ・見学時に行われているプログラムが、自習や簡単な軽作業ばかり。 |
| 4. スタッフの様子 | ・スタッフに笑顔がなく、疲弊しているように見える。 ・スタッフ同士のコミュニケーションが不足している、雰囲気が悪い。 ・短期間でのスタッフの入れ替わりが激しい。 |
| 5. 第三者からの評判 | ・Googleマップの口コミやSNSで、具体的な内容を伴う悪い評判が複数見られる。 ・行政からの指導や監査が入った過去がある(自治体のサイトで公表されている場合も)。 |
これらのポイントは、公式サイトの情報だけでは分かりません。必ず複数の事業所を見学・体験し、自分の目で確かめることが重要です。

失敗しない!自分に合った就労移行支援事業所の選び方【5ステップ】

「やばい」事業所を避けるだけでは不十分です。最も大切なのは、数ある事業所の中から「自分に合った」場所を見つけること。そのための具体的な5つのステップをご紹介します。
ステップ1:自己分析で「自分の軸」を明確にする
まず、就労移行支援を利用して「どうなりたいのか」を具体的にしましょう。
- スキル: PCスキル、コミュニケーション能力、専門技術など、何を身につけたいか?
- 環境: 静かな環境で集中したいか、人との交流が多い環境が良いか?
- サポート: どんな配慮が必要か、何を相談したいか?
- 目標: どんな職種・業界で、どんな働き方をしたいか?
この「自分の軸」が、事業所選びの羅針盤になります。
ステップ2:複数の事業所をリストアップする
自分の軸が定まったら、候補となる事業所を探します。
- LITALICO仕事ナビなどのポータルサイト: 全国の事業所を条件で絞り込んで検索できます。
- 市区町村の障害福祉課: 地域の事業所リストをもらえたり、相談に乗ってもらえたりします。
- ハローワークの専門援助部門: 就職相談と合わせて、事業所の情報を得られます。
まずは3~5ヶ所ほど候補を挙げてみましょう。
ステップ3:説明会・見学でプログラムと雰囲気を知る
リストアップした事業所に問い合わせ、必ず見学に行きましょう。その際は、以下のチェックリストを参考に、積極的に質問してください。
| 確認カテゴリ | 質問リストの例 |
|---|---|
| プログラム | ・1日の具体的なスケジュールを教えてください。 ・個別支援計画は、どのくらいの頻度で見直しますか? ・希望する〇〇のスキルを学べる講座はありますか? |
| 就職支援 | ・主な就職先にはどのような企業がありますか? ・過去3年間の就職率と「6ヶ月後の定着率」を教えてください。 ・企業実習には参加できますか? |
| スタッフ | ・スタッフの専門資格(社会福祉士、精神保健福祉士など)について教えてください。 ・スタッフ1人あたり、何人の利用者を担当していますか? |
| 環境・利用者 | ・利用者の年齢層や障害特性の傾向を教えてください。 ・困ったときに相談しやすい雰囲気ですか? |
ステップ4:必ず「体験利用」をする
見学で良いと感じたら、契約前に必ず「体験利用」をしましょう。多くの事業所では、1日~数日間の体験が可能です。実際にプログラムに参加してみることで、見学だけでは分からなかった雰囲気や、他の利用者との相性などを肌で感じることができます。
ステップ5:第三者の意見も参考にする
事業所のスタッフは、当然ながら自分の事業所の良い点をアピールします。判断に迷ったら、客観的な意見を聞くために第三者機関にも相談してみましょう。
- 相談支援専門員:
障害福祉サービス全体の利用計画を立てる専門家。中立的な立場で事業所選びをサポートしてくれます。 - 障害者就業・生活支援センター:
就業と生活の両面から支援を行う機関(全国339箇所、通称「なかぽつ」)。地域の事業所の評判に詳しい場合があります。基本的に利用は無料です。
複数の視点から情報を集めることで、より納得のいく決断ができます。

もし利用中に「おかしい」と感じたら?3つの対処法

すでに入所している事業所に対して「何かおかしい」と感じ始めた場合、一人で抱え込まずに行動することが大切です。我慢し続ける必要は全くありません。
対処法1:事業所のスタッフに相談する
まずは、信頼できるスタッフや事業所の責任者に、何に困っているのか、どう感じているのかを具体的に伝えてみましょう。「プログラム内容を変更してほしい」「担当スタッフとの相性が合わない」など、正直に話すことで、状況が改善される可能性があります。
対処法2:市区町村の障害福祉担当課に相談する
「事業所には直接言いにくい」「相談したけど改善されない」という場合は、お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課に相談してください。ここは、事業所を監督する立場にある公的な窓口です。事業所への指導や、他のサービスの情報提供などを行ってくれます。
対処法3:事業所の変更・退所を検討する
環境がどうしても合わない場合は、事業所を変更する(移る)という選択肢もあります。就労移行支援の利用は一度きりではなく、標準利用期間内であれば複数回の利用が可能です。心身の健康を損なってまで、合わない場所に通い続ける必要はないのです。まずは市区町村の窓口や相談支援専門員に相談し、次のステップを一緒に考えてもらいましょう。

Q&A|就労移行支援の「おかしい」に関するよくある質問
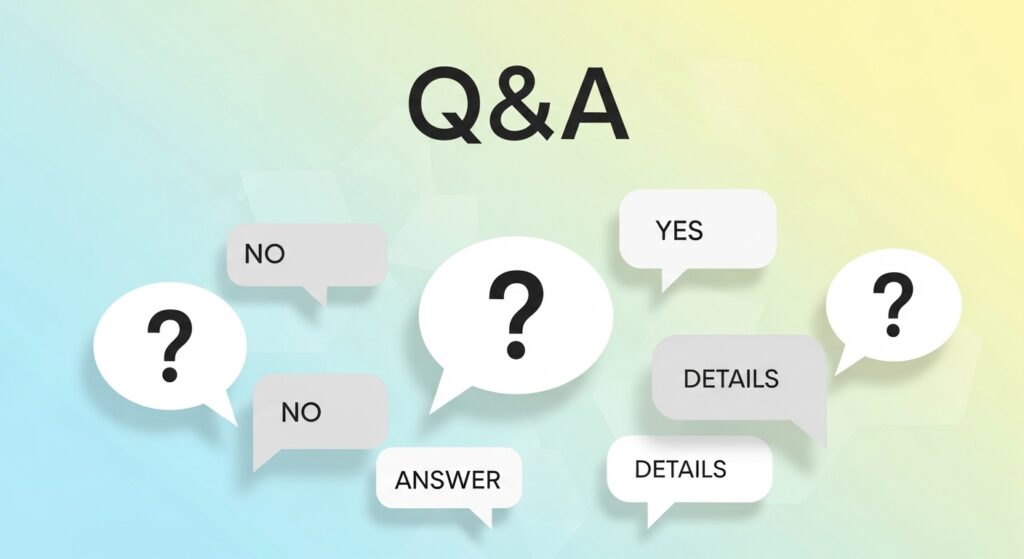
- Q就労移行支援は意味ないって本当ですか?
- A
「意味があるかどうか」は、本人と事業所の相性次第です。質の高い事業所と出会い、主体的にプログラムに取り組むことで、希望の就職を実現し、人生の大きな転機となった方はたくさんいます。一方で、ミスマッチな事業所を選んでしまい、「意味がなかった」と感じる方がいるのも事実です。だからこそ、事前の事業所選びが何よりも重要になります。
- Qプログラムについていけない場合はどうすれば良いですか?
- A
まずは「ついていけない」と感じていることを、正直にスタッフに相談してください。個別支援が基本ですので、あなたのペースや理解度に合わせてプログラムの難易度を調整してくれるはずです。それができない事業所であれば、あなたに合っていない可能性が高いと言えます。
- QQ3. お金がないと利用は難しいですか?
- A
利用料については、約9割の方が自己負担0円で利用していますのでご安心ください。ただし、交通費や昼食代は原則自己負担となります。自治体によっては、交通費の助成制度を設けている場合もあります。制度の有無や内容は地域によって異なるため、お住まいの地域で助成制度があるか、一度市区町村の障害福祉課にご確認ください。

まとめ
この記事では、就労移行支援が「おかしい」と言われる理由から、後悔しないための事業所の選び方、困ったときの対処法までを詳しく解説してきました。
重要なポイント
- 「おかしい」という評判の多くは、事業所とのミスマッチが原因。
- 公式サイトの情報だけでなく、自分の目で見て、体験して判断することが不可欠。
- 就職率だけでなく「定着率」や「支援の質」に注目する。
- 困ったときは一人で抱え込まず、事業所や公的機関に相談する。
- 合わないと感じたら事業所を変更するという選択肢もある。
就労移行支援は、正しく活用すれば、あなたのキャリアにとって非常に強力な味方となり得ます。ネガティブな情報に臆することなく、この記事で紹介した視点を持って、あなたに最適な一歩を踏み出してください。あなたの未来を心から応援しています。










