「就労移行支援って、本当に自分に合っているのかな…」
「利用して後悔しないか不安…」
障害や心身の不調を抱えながら、就職を目指して就労移行支援の利用を考えているとき、このような不安を感じるのは当然のことです。
高額な費用がかかるわけではなくても、あなたの貴重な時間と「働きたい」という前向きな気持ちを投資するのですから、絶対に失敗したくないですよね。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、「就労移行支援が向いてない人の特徴」と「利用してよかった人のリアルな声」の両方を徹底的に解説します。
最後まで読めば、あなたが就労移行支援を利用すべきか客観的に判断できるようになり、もし利用すると決めた場合でも、後悔しないための具体的なアクションプランがわかります。
記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。
読み間違いがありますが、ご容赦ください。
▼就労移行支援は本当にあなたに必要?後悔しないための見極めと活用法

結論:就労移行支援は「目的」と「事業所選び」が9割
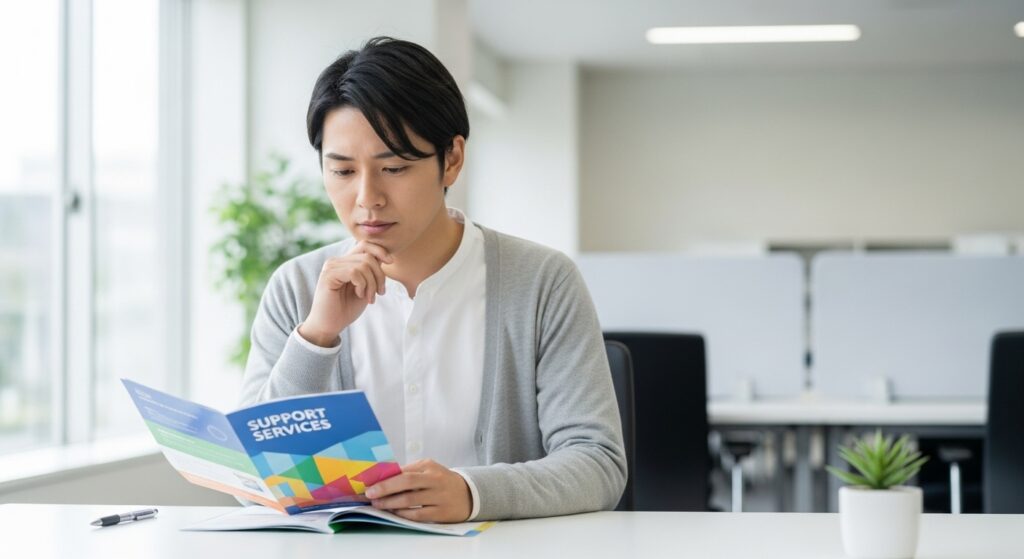
本題に入る前に、最も重要な結論からお伝えします。
就労移行支援というサービスがあなたに合うかどうかは、「何のために利用するのか(目的)」と「自分に合った事業所を選べるか」という2点で、その9割が決まります。
「利用したけど意味がなかった」「向いてなかった」と感じるケースのほとんどは、サービスそのものが悪いのではなく、この目的と事業所のミスマッチが原因です。
この記事では、そのミスマッチを防ぐための具体的な知識を一つずつ見ていきましょう。

要注意!就労移行支援が向いてない可能性が高い5つの特徴
まず、どのような人が就労移行支援とのミスマッチを起こしやすいのか、具体的な特徴を5つご紹介します。
ただし、これらに当てはまるからといって「絶対に利用してはいけない」わけではありません。「こういう傾向があると、目的を見失ったり、訓練が苦痛になったりしやすい」というサインとして捉え、対策を考えるきっかけにしてください。
1. 働くことへの意欲が低い・目的が曖昧
「親や支援者に勧められたから、なんとなく…」
「今は働けないけど、とりあえず日中に通う場所が欲しい」
このように、「就職したい」という明確な意欲がご自身の中にない場合、就労移行支援の訓練は目的のない作業になりがちです。週5日、決まった時間に通い、カリキュラムに取り組むことは、想像以上にエネルギーを要します。目的が曖昧なままだと、「何のためにこれをやっているんだろう」と苦しくなってしまうかもしれません。
【対策】
もし働く意欲が湧かないのであれば、焦る必要はありません。まずはカウンセリングを受けたり、地域の相談支援事業所などで「自分が将来どうなりたいのか」「何に興味があるのか」を専門家と一緒に整理する時間を持つことをお勧めします。
2. 基本的な生活リズムが整っていない
就労移行支援は、企業への就職を目指すための「リハビリ」の場です。そのため、多くの事業所では週3?5日、朝から夕方までといった、実際の勤務に近い形での通所が求められます。
昼夜逆転している、週に1?2日外出するのがやっと、という状態の場合、安定して通所すること自体が非常に高いハードルになります。無理に通おうとすると、かえって体調を崩してしまう危険性もあります。
【対策】
まずは生活リズムを整えることを最優先しましょう。週1~2日の短時間通所から始められる事業所や、生活リズムの改善自体をサポートしてくれるプログラムがある事業所を探すのが有効です。また、「自立訓練(生活訓練)」という別の福祉サービスを利用して、生活の土台を固めてから移行支援に進む、というステップも考えられます。
3. 指示待ちで、主体的に動くのが苦手
「手厚くサポートしてくれる」というイメージから、「黙っていても、スタッフが全部お膳立てしてくれるはず」と考えていると、期待とのギャップが生まれる可能性があります。
もちろん、スタッフは手厚くサポートしてくれますが、それはあくまであなたの「主体性」があってこそ活きるものです。「何に困っているのか」「どうなりたいのか」をあなた自身が発信し、スタッフと一緒に課題解決に取り組む姿勢が大切になります。
【対策】】
大規模な事業所が不安な場合は、利用者一人ひとりへの目が行き届きやすい小規模な事業所を選ぶと良いでしょう。また、見学や体験利用の際に「自分のペースで相談しやすい雰囲気か」をしっかり確認することが重要です。
4. 専門スキルだけを短期間で習得したい
「プログラミングスキルを3ヶ月で身につけて、ITエンジニアになりたい」
「とにかく早くMOS資格だけを取りたい」
このような明確な目的は素晴らしいですが、もし「特定の職業スキル習得だけ」がゴールであれば、就労移行支援は少し遠回りになるかもしれません。
就労移行支援は、PCスキルなどの職業訓練と同時に、障害特性の理解、コミュニケーション、ストレス対処法といった、長く働き続けるための土台作りを総合的に行う場所だからです。
【対策】
特定のスキル習得が目的なら、職業訓練校(ハロートレーニング)や民間のプログラミングスクールなども視野に入れ、それぞれのメリット・デメリットを比較検討してみましょう。その上で、やはり働き続けるための総合的なサポートが必要だと感じれば、就労移行支援が最適な選択肢となります。
日本初の先端IT特化型の就労移行支援事業所「Neuro Dive」は、AIやデータサイエンスが学べると評判なので、このような事業所の無料説明会に参加するのもよいでしょう。
5. 他責思考が強く、環境や人のせいにしがち
「うまくいかないのは、事業所のプログラムが悪いからだ」
「スタッフの教え方が下手だから、スキルが身につかない」
就職活動や訓練が思うように進まないとき、その原因を自分以外のものに求めてしまう傾向が強いと、成長の機会を逃してしまうかもしれません。支援はあくまであなたの努力を後押しするものであり、最終的に自分の課題と向き合うのはあなた自身です。
【対策】
自分と向き合う作業は一人では難しいものです。だからこそ、カウンセリングや面談が充実している事業所を選びましょう。信頼できるスタッフと対話を重ねる中で、客観的に自分を見つめ、課題を乗り越える力を育てていくことができます。

「就労移行支援、行ってよかった!」リアルな声と得られる5つのメリット

一方で、多くの方が就労移行支援を利用して「人生が変わった」「行って本当によかった」と感じているのも事実です。ここでは、具体的なメリットを5つ、利用者の声(※)と共に紹介します。
(※プライバシーに配慮した架空の事例です)
1. 自分に合う仕事が明確になった(自己理解)
Aさん(20代・発達障害)の声
「自分では事務職が向いていると思い込んでいましたが、訓練でデータ入力や書類整理をやってみたら、集中力が続かずミスばかり。逆に、スタッフに勧められて挑戦した軽作業では『正確で早い』と褒められ、自分の意外な得意分野に気づけました。今は倉庫でのピッキング作業で、正社員として働いています」
自分一人で「適職」を見つけるのは困難です。就労移行支援では、様々な訓練プログラムを試したり、スタッフから客観的なフィードバックをもらったりする中で、自分の得意・不得意、好き・嫌いを深く理解できます。この自己理解こそが、ミスマッチのない就職への第一歩です。
2. 安定して働ける生活リズムと体力がついた
Bさん(30代・うつ病)の声
「休職期間が長く、昼夜逆転していました。最初は週2日の午前中だけ通うのがやっとでしたが、スタッフさんが親身に相談に乗ってくれ、半年後には週5日、9時から16時まで安定して通えるように。この『毎日通えた』という事実が、就職活動への大きな自信になりました」
規則正しく通所する生活は、そのまま働くためのリハーサルになります。毎日決まった時間に起き、準備をして、同じ場所へ通う。この繰り返しが、就労に必要な生活リズムと体力を自然に養ってくれます。
3. 苦手だったコミュニケーションに自信がついた
Cさん(20代・不安障害)の声
「人と話すのが苦手で、特に『報告・連絡・相談』ができませんでした。でも、事業所のグループワークで発表の練習をしたり、SST(ソーシャルスキルトレーニング)で断り方や頼み方をロールプレイングしたりするうちに、少しずつ自信がつきました。同じ悩みを持つ仲間がいたのも心強かったです」
職場での悩みの多くは人間関係やコミュニケーションに関するものです。就労移行支援では、ビジネスマナーの基本から、障害特性に合わせたコミュニケーションの工夫まで、実践的に学ぶことができます。
表:就労移行支援で受けられる主な訓練内容
| カテゴリ | 具体的な訓練内容 |
|---|---|
| 自己理解 | 障害特性の理解、ストレスコーピング、キャリアプランニング、感情コントロール |
| PCスキル | Word, Excel, PowerPointの基礎・応用、MOS資格対策、データ入力 |
| コミュニケーション | SST(ソーシャルスキルトレーニング)、ビジネスマナー、アサーション、グループワーク |
| 実践訓練 | 事務補助、軽作業、プログラミング、デザイン、企業インターン(企業実習) |
| 就職活動 | 求人検索、履歴書・職務経歴書の作成支援、模擬面接、面接同行 |
4. 応募書類の添削や面接練習が心強かった(就職活動サポート)
Dさん(40代・統合失調症)の声
「長いブランクがあり、職務経歴書に何を書けばいいか全く分かりませんでした。スタッフの方が私の話をじっくり聞いて、強みや経験を一緒に言語化してくれたおかげで、自信を持って提出できる書類が完成しました。模擬面接も10回以上付き合ってくれて、本番では練習の成果を発揮できました」
障害者雇用には、一般の転職活動とは異なるノウハウが必要です。障害についてどう説明するか、必要な配慮をどう伝えるかなど、専門的な知識を持つスタッフが二人三脚で就職活動をサポートしてくれるのは、何より心強い点です。
5. 就職後も相談できる場所がある安心感(定着支援)
Eさん(30代・双極性障害)の声
「就職して3ヶ月経った頃、新しい環境のストレスで体調を崩しかけました。すぐに定着支援の担当者に相談したら、私の状況を会社の人事担当者へうまく伝えてくれて、業務量を調整してもらえることに。一人で抱え込んでいたら、きっと退職していたと思います」
就労移行支援のサポートは、就職したら終わりではありません。就職後も、スタッフが定期的に職場を訪問したり、面談を行ったりして、あなたが長く安定して働き続けられるようにサポート(職場定着支援)してくれます。この「いつでも帰れる場所がある」という安心感が、大きな支えになります。(※)
※就職後6ヶ月の定着支援に加え、別途申請することで「就労定着支援」サービスを最大3年間利用可能です。これにより、合計で最長3年半のサポートが受けられます。

後悔しない!自分に合う就労移行支援事業所の選び方【5つのチェックリスト】
ここまで読んで、「自分は就労移行支援を使ってみる価値がありそうだ」と感じた方も多いでしょう。
ここからは、後悔しないための最も重要なステップ、「事業所選び」の具体的なチェックリストを5つ紹介します。必ず複数の事業所を見学・体験して、このリストを元に比較検討してください。
1. 事業所の「雰囲気」は自分に合うか
プログラムの内容も大事ですが、それ以上に「自分が安心して通える場所か」という感覚は重要です。スタッフの話し方、他の利用者の表情、事業所全体の清潔感や明るさなどを肌で感じてみましょう。
- [ ] チェックポイント: 見学や体験利用の際に、自分がリラックスできるか、威圧感や居心地の悪さを感じないか。
2. 「訓練プログラム」は自分の目的に合っているか
事業所によって、PCスキルに強い、軽作業が中心、精神障害へのケアが手厚いなど、特色は様々です。自分が学びたいこと、身につけたいスキルに合ったプログラムが用意されているかを確認しましょう。
- [ ] チェックポイント: カリキュラムの具体的な内容、個別対応の柔軟性、企業実習の機会があるかなどを質問する。
3. 「就職実績」は信頼できるか
ただ「就職率〇%」という数字だけでなく、その中身を見ることが大切です。どのような業種・職種への就職が多いのか、自分の希望する働き方に近い実績があるかを確認しましょう。可能であれば、就職後の定着率(長く働き続けている人の割合)も重要な指標です。
- [ ] チェックポイント: 就職先の企業名(一部でも)、職種、雇用形態、定着率について具体的に質問する。
4. 「スタッフの専門性」は高いか
あなたの障害特性を深く理解し、的確なアドバイスをくれるスタッフがいるかは、利用の満足度を大きく左右します。精神保健福祉士やキャリアコンサルタントなどの有資格者がいるか、スタッフの定着率は高いかなども参考になります。
- [ ] チェックポイント: 相談時のスタッフの対応は丁寧か、質問に対して明確に答えてくれるか、専門的な知識を感じられるか。
5. 「場所」は無理なく通えるか
意外と見落としがちですが、通いやすさは継続の鍵です。自宅からの所要時間、交通費、駅からの距離などを考慮し、2年間通い続けることを想定して現実的な負担かどうかを判断しましょう。
- [ ] チェックポイント: 実際に自宅から事業所まで行ってみて、ルートや混雑具合、体力的な負担を確認する。

もし「向いてないかも」と思ったら?就労移行支援以外の選択肢
様々な情報を検討した結果、「今の自分には就労移行支援は合わないかもしれない」と感じることもあるでしょう。それは決してネガティブなことではなく、あなたにとって最適な道を見つけるための重要な一歩です。
ここでは、就労移行支援以外の主な選択肢を比較表にまとめました。
表:就労移行支援と他のサービスの比較
| サービス名 | 対象者 | 主な目的 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 就労移行支援 | 一般就労を目指す障害者(65歳未満) | 就職準備と職場定着 | 障害特性の理解から定着まで総合的にサポート | 利用期間が原則2年。賃金は発生しない。 |
| 就労継続支援A型/B型 | 現状で一般就労が困難な方 | 福祉的な配慮がある環境で働く | 雇用契約を結び(A型)、賃金を得ながら働ける | 一般企業への就職が直接の目的ではない。 |
| 障害者向け転職エージェント | ある程度、就労準備性が高い方 | 障害者雇用求人とのマッチング・転職支援 | 非公開求人や好条件の求人が多い。専門的サポート。 | スキル訓練や生活リズム改善のサポートはない。 |
| ハローワーク | 全ての求職者 | 求人紹介、職業相談 | 求人数が圧倒的に多い。専門援助部門がある。 | 担当者によって障害への理解度に差が出やすい。 |
| 地域障害者職業センター | 障害のある方全般 | 職業評価、職業準備支援、相談 | 公的機関として中立的な立場から専門的支援を受けられる。 | 直接的な訓練プログラムは限定的。 |

就労移行支援に関するQ&A
最後に、就労移行支援に関してよくある質問にお答えします。
- Q利用料金はかかりますか?
- A
前年度の世帯所得に応じて自己負担額の上限が定められていますが、多くの方が自己負担なく無料で利用しています。例えば、住民税非課税世帯の方は自己負担がありません。ご自身の負担額については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で確認できます。
- Q利用期間はどのくらいですか?
- A
原則として24ヶ月(2年間)です。ただし、自治体の審査により、必要性が認められれば最大1年間の延長が可能な場合があります。
- Q途中で辞めることはできますか?
- A
はい、いつでも辞めることができます。 もし事業所が合わないと感じた場合、無理に通い続ける必要はありません。まずは事業所のスタッフや、お住まいの地域の相談支援事業所に相談してみましょう。他の事業所に移ることも可能です。

まとめ:不安な今こそ、最初の一歩を踏み出そう
就労移行支援が自分に合っているか、不安に思うのは当然です。しかし、その不安は、あなたが真剣に自分の将来と向き合っている証拠でもあります。
この記事で見てきたように、就労移行支援の成否は「明確な目的意識」と「自分にぴったりの事業所選び」にかかっています。「向いてない人の特徴」として挙げた項目も、裏を返せば「事業所選びで特に注意すべきポイント」として捉えることができます。
もし少しでも「利用してみる価値があるかもしれない」と感じたら、まずは気になる事業所の公式サイトを覗いて、無料相談や見学を申し込んでみましょう。
話を聞くだけでも、あなたの悩みや疑問が整理され、次の一歩が見えてくるはずです。この記事が、あなたの後悔のない選択と、希望ある未来への第一歩となることを心から願っています。










