「仕事のミスが多すぎる」
「話が噛み合わない」
「なぜかいつも人間関係でトラブルになる…」
身近なパートナーや家族、同僚に対して、このような悩みを抱えていませんか?もしかしたら、その言動の背景には「大人の発達障害」があるのかもしれません。
しかし、本人に自覚がない場合、どう伝えればいいのか、非常に悩みますよね。伝え方を間違えれば、相手を深く傷つけ、関係性が悪化してしまう可能性もあります。
この記事では、大人の発達障害の可能性のある方に、相手を傷つけることなく「気づき」を促し、より良い関係を築くための具体的な5つのステップを解説します。
「自覚させる」という一方的なアプローチではなく、共に問題に向き合い、解決していくためのヒントがここにあります。一人で抱え込まず、この記事を参考に、まず一歩を踏み出してみましょう。
▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。
もしかして大人の発達障害?「自覚がない」本人にどう向き合うべきか

大人の発達障害は、生まれつきの脳機能の発達の偏りによるもので、本人の「わがまま」や「努力不足」が原因ではありません。主なものに、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)などがあります。
しかし、大人になるまで診断されなかった人の多くは、本人はもちろん、周りもその特性に気づかず、「個性の範囲」あるいは「本人の努力不足」として見過ごされてきました。
なぜ本人は「自覚がない」のか?3つの心理的背景
本人に自覚がないのには、いくつかの理由が考えられます。
- 昔から「これが当たり前」だった:
生まれつきの特性であるため、本人にとってはそれが普通の状態です。他の人と自分を比べ、「なぜかうまくいかない」と感じていても、それが発達障害の特性によるものだとは思い至らないのです。 - 「自分の努力不足」だと信じている:
周囲から「不注意だ」「やる気がない」と叱責され続けた経験から、うまくいかない原因をすべて自分の性格や努力不足のせいだと内面化してしまっているケースも少なくありません。 - 指摘されることへの防衛:
発達障害の可能性を指摘されることは、自分自身を否定されるように感じられ、無意識に受け入れることを拒否してしまうことがあります。
これらの背景を理解せず、一方的に「あなたは発達障害だ」と決めつけることは、相手を追い詰め、心を閉ざさせてしまうだけです。大切なのは、まず相手の状況を理解しようと努めることです。
「自覚させる」の前に。まず、あなたが知っておくべき大人の発達障害の基礎知識
伝える前に、まずはあなたが大人の発達障害について正しく理解することが不可欠です。思い込みや誤解に基づいた言動は、相手を傷つける原因になります。
| 発達障害の種類 | 主な特性(例) | 周囲からの見え方(誤解) |
|---|---|---|
| ASD(自閉スペクトラム症) | ・相手の気持ちを察するのが苦手 ・場の空気が読めない ・強いこだわり、ルーティンを好む | 「空気が読めない人」「自分勝手」「融通が利かない」 |
| ADHD(注意欠如・多動症) | ・忘れ物やケアレスミスが多い(不注意) ・じっとしていられない(多動性) ・思いつきで行動してしまう(衝動性) | 「だらしない人」「やる気がない」「落ち着きがない」 |
これらの特性は、あくまで一例です。現れ方には個人差が大きく、複数の特性を併せ持っている場合も少なくありません。
【STEP1】伝える前の準備が9割。自分の心と情報を整理する
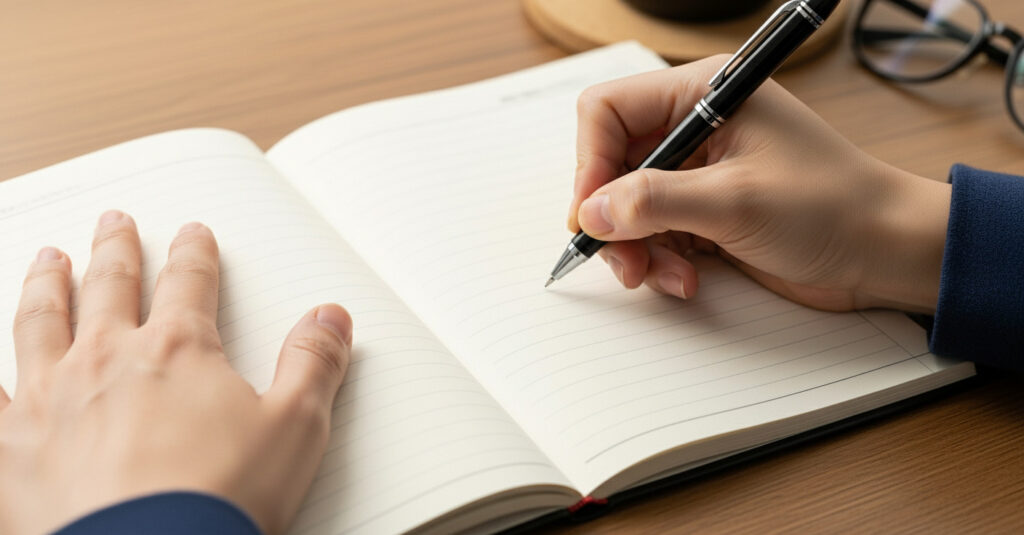
本人に話をする前に、最も重要なのが「準備」です。感情的なまま話を進めても、良い結果にはつながりません。まずは自分自身の心と情報を整理しましょう。
感情的にならない。事実と自分の気持ち(Iメッセージ)を切り分ける
相手の言動に対して、あなたが「困っている」「悲しい」「疲れた」と感じるのは自然なことです。しかし、その感情をそのままぶつけるのは避けましょう。
大切なのは、「あなたは〇〇だ(Youメッセージ)」という主語で相手を責めるのではなく、「私は〇〇で困っている(Iメッセージ)」という主語で、自分の気持ちと客観的な事実を伝えることです。
- NG例(Youメッセージ):
「なんでいつも時間を守れないの?だらしない!」 - OK例(Iメッセージ):
「(待ち合わせに遅れてきたという事実)。私は、約束の時間に連絡がないと、何かあったのかと心配になるし、悲しい気持ちになるな。」
このように伝えることで、相手は人格を否定されたと感じにくく、話し合いに応じやすくなります。
正しい知識を持つ。思い込みや誤解をなくす
前述の通り、まずは公的機関のウェブサイトや専門書などで、大人の発達障害に関する正しい知識をインプットしましょう。知識は、あなたを冷静にし、偏見から守ってくれます。
伝える目的を明確にする。「支配」ではなく「協働」
あなたは何のために、本人に伝えたいのでしょうか?相手を言い負かしたり、自分の思い通りにコントロールしたりするためではありませんよね。
目的は、二人で協力して「困りごと」を解決し、より良い関係を築くことであるはずです。この「協働」という目的を忘れないことが、話し合いの方向性を見失わないための羅針盤となります。
【STEP2~4】相手を傷つけない「伝え方」の具体的な3ステップ

準備が整ったら、いよいよ実際に伝えるステップに進みます。焦らず、一つひとつ丁寧に進めていきましょう。
STEP2: 環境を整える(いつ、どこで話すか)
話をする場所とタイミングは非常に重要です。
- 場所:
自宅のリビングなど、二人がリラックスできる、プライバシーが守られる静かな場所を選びましょう。カフェやレストランなど、第三者がいる場所は避けるべきです。 - タイミング:
お互いに時間に余裕があり、心身ともに疲れていない時を選びます。仕事から帰った直後や、寝る前などは避けましょう。「少し大事な話があるんだけど、週末の午後に30分くらい時間をもらえないかな?」などと、事前にアポを取るのが理想です。
STEP3: 具体的なエピソードを元に「困りごと」を共有する
抽象的な批判や人格否定は絶対にNGです。「いつも〇〇だ」といった主語の大きな話ではなく、具体的なエピソードを一つ取り上げましょう。
会話例:
このように、「事実」+「Iメッセージ」+「協力の依頼」をセットで伝えることで、相手は責められていると感じにくくなります。
STEP4: 「発達障害」の言葉を使わず、解決策を一緒に探す姿勢を見せる
初期段階では、あえて「発達障害」という言葉を出さない方が賢明な場合が多いです。その言葉自体が、相手に強い拒否反応を引き起こさせてしまう可能性があるからです。
まずは、具体的な「困りごと」に焦点を当て、「どうすればミスを減らせるか」「コミュニケーションを円滑にできるか」といった解決策を一緒に探すスタンスを強調しましょう。
その話し合いの中で、
といった具体的な対策を提案し、本人が「自分は他の人とは違う特性があるのかもしれない」と自然に気づけるように導くのが理想です。
【STEP5】一人で抱え込まない。専門家や相談窓口という選択肢

二人だけで解決しようとすると、どうしても行き詰まってしまうことがあります。そのような時は、専門家の力を借りるのが最善の策です。
全国の相談窓口一覧
公的な相談窓口は、無料で相談でき、診断がなくても利用できる場合があります。まずは電話で問い合わせてみましょう。
| 相談窓口 | 対象者 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 発達障害者支援センター | 発達障害のある本人とその家族 | 総合的な相談、支援計画の作成、医療・福祉・労働などの関係機関との連携 |
| 精神保健福祉センター | 心の健康問題全般を抱える人 | 精神保健に関する相談、医療機関の案内など |
| 市町村の障害福祉担当窓口 | その地域に住む障害のある人 | 福祉サービス(障害者手帳、自立支援医療など)の申請受付や相談 |
※上記は代表的な相談窓口です。名称や連絡先、具体的なサービス内容はお住まいの自治体によって異なりますので、詳細は各自治体の公式ウェブサイトで必ずご確認ください。
医療機関(精神科・心療内科)を受診するメリット
診断を受けるかどうかは本人の意思が最も尊重されるべきですが、受診には多くのメリットがあります。
- 原因の特定:
長年の「生きづらさ」の原因が特性にあると分かり、本人が自分を責めなくなる。 - 具体的な対策:
医師やカウンセラーから、特性に合った対処法(環境調整、薬物療法、カウンセリングなど)のアドバイスがもらえる。 - 公的支援の利用:
診断を受けることで、障害者手帳の取得や就労支援サービス、自立支援医療制度など、必要な公的支援を受けられるようになる。
本人に医療機関を提案する際は、「あなたの病気を治すため」ではなく、「あなたの『困りごと』を減らすための専門的なアドバイスがもらえる場所だよ」と伝えると、抵抗感が和らぐかもしれません。
これはNG!関係を悪化させる絶対にやってはいけない伝え方

良かれと思って取った行動が、逆効果になることもあります。以下の行動は絶対に避けましょう。
大勢の前で指摘する、人格を否定する
「だからお前はダメなんだ」といった人格を否定する言葉や、他の家族や職場の同僚がいる前で特性を指摘することは、相手のプライドを深く傷つけ、回復しがたいダメージを与えます。
無理やり病院に連れて行こうとする
本人が納得していないのに、無理やり病院に連れて行くのは逆効果です。本人の意思で「相談に行ってみよう」と思えるまで、焦らず待つ姿勢も大切です。
他人と比較して責める
「〇〇さんはできているのに、なぜあなたはできないの?」という比較は、劣等感を煽るだけで、何も生み出しません。比較するべきは、他人ではなく、「過去の本人」です。少しでも改善が見られたら、その点を具体的に褒めるようにしましょう。
伝える側のあなたの心のケアも忘れずに

ここまで、本人にどう伝えるかを中心に解説してきましたが、最も大切なのは、あなた自身の心の健康です。身近な人を支えることは、想像以上にエネルギーを消耗します。
気持ちを吐き出せる場所を見つける(家族会、カウンセリング)
一人で抱え込まず、あなたの気持ちを安心して話せる場所を見つけましょう。同じような立場の人々が集まる「家族会」に参加したり、専門のカウンセラーに相談したりするのも非常に有効です。
自分を責めない。「できること」と「できないこと」の境界線を引く
相手の特性を変えることはできません。あなたがしてあげられることには限界があります。「自分がなんとかしなければ」と全てを背負い込み、自分を責めるのはやめましょう。あなた自身の人生と幸せも、同じように大切にする権利があるのです。
まとめ:焦らず、根気強く。大切なのはより良い関係を築くこと

大人の発達障害の可能性を本人に伝え、気づきを促すことは、非常にデリケートで根気のいるプロセスです。
この記事で紹介した5つのステップを、もう一度おさらいしましょう。
- 準備: 自分の感情と情報を整理し、目的を明確にする。
- 環境: リラックスできる場所とタイミングを選ぶ。
- 共有: 具体的なエピソードを元に「困りごと」を伝える。
- 協働: 解決策を「一緒に」探す姿勢を見せる。
- 相談: 一人で抱えず、専門家や第三者を頼る。
最も大切なのは、相手を一方的に「変えよう」とするのではなく、特性を理解し、お互いが過ごしやすくなる方法を「一緒に探していく」という姿勢です。
このプロセスは、あなたと大切な人との関係を、より深く、より建設的なものへと変えていくための、一つのきっかけになるはずです。焦らず、あなた自身のことも大切にしながら、一歩ずつ進んでいきましょう。
※注意事項:
この記事は情報提供を目的としたものであり、医学的な診断に代わるものではありません。気になる症状がある場合は、自己判断せず専門の医療機関にご相談ください。
記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医










「この間の〇〇の件なんだけど、あなたが『やっておく』と言っていた書類の提出が、締め切りを過ぎてしまっていたよね(事実)。あの時、私は急いで取引先に謝罪の連絡をしなければならなくて、とても慌てたし、悲しい気持ちになったんだ(Iメッセージ)。同じようなことが何度かあって、どうすれば防げるか、一緒に考えられないかな?(協力の依頼)」