「なぜ自分だけ仕事ができないんだろう…」
「何度確認してもミスをしてしまう」
「周りの人と上手くコミュニケーションが取れない」
職場でこのように感じ、一人で自分を責めていませんか?その尽きない悩み、もしかしたらあなたの能力や努力不足ではなく、生まれ持った「脳の特性」が関係しているのかもしれません。
この記事では、近年理解が進んでいる「発達障害」の特性が、仕事のどのような場面で困難として現れるのかを詳しく解説します。さらに、当事者の方が明日からすぐに実践できる具体的な仕事術から、周囲の上司や同僚ができるサポートの方法、そして頼れる専門機関まで、網羅的にご紹介します。
この記事を読み終える頃には、ご自身の状況を客観的に理解し、自分に合った働き方を見つけるための第一歩を踏み出せるはずです。
▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。
【セルフチェック】仕事でこんな「できない」に心当たりはありませんか?
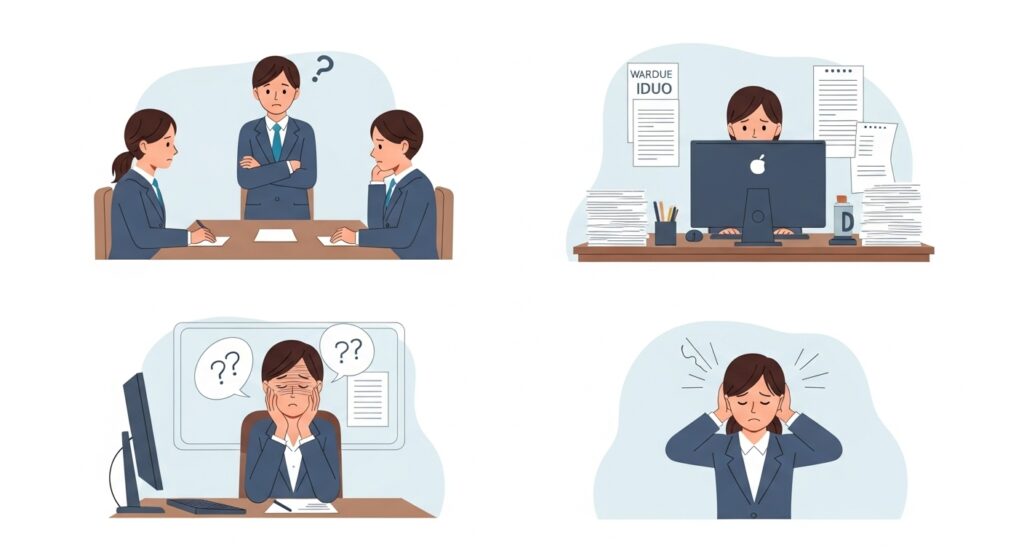
発達障害の特性は、個々人によって現れ方が大きく異なります。しかし、仕事の場面では、いくつかの共通した「困難」として表面化することがあります。まずは、ご自身に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。
Case1: コミュニケーションの困難
- 相手の意図を察するのが苦手で、「空気が読めない」と言われることがある。
- 雑談や世間話にどう参加していいか分からず、孤立しがち。
- 思ったことをストレートに伝えすぎてしまい、相手を傷つけるつもりはなくても誤解を招く。
- 報告・連絡・相談のタイミングや内容が適切でないと指摘される。
Case2: タスク・スケジュール管理の困難
- 複数の仕事を同時に頼まれると、何から手をつけていいかパニックになる(マルチタスクが苦手)。
- 仕事の優先順位付けが苦手で、重要でない作業に時間をかけすぎてしまう。
- 長期的なプロジェクトの見通しを立てるのが難しく、締め切り直前になって慌てることが多い。
- 書類やデータの整理整頓が苦手で、必要なものをすぐに見つけられない。
Case3: 注意・集中力の困難
- 単純な計算ミスや誤字脱字など、不注意によるミス(ケアレスミス)を繰り返してしまう。
- 会議中など、長時間じっとしているのが苦痛で、集中力が続かない。
- 周りの音や人の動きなど、些細なことが気になってしまい、作業に集中できない。
- 一度集中すると過度にのめり込み、休憩を取るのを忘れたり、他のことが目に入らなくなったりする。
Case4: 感覚・感情コントロールの困難
- 蛍光灯の光やオフィスの騒音、特定の匂いなどが、人一倍気になり疲れてしまう(感覚過敏)。
- 予期せぬトラブルや急な予定変更にうまく対応できず、思考が停止してしまう。
- 一度感じた怒りや不安をなかなか切り替えられず、仕事に引きずってしまう。
これらの困難は、誰にでも起こりうることです。しかし、これらのうち複数に、そして頻繁に心当たりがあり、日常生活や仕事に大きな支障をきたしている場合、その背景には発達障害の特性が隠れている可能性があります。
「仕事ができない」の背景にある発達障害の3つのタイプ

発達障害は、生まれつきの脳機能の発達の偏りによるもので、決して本人の「わがまま」や「努力不足」が原因ではありません。DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)では「神経発達症群(神経発達障害群)」として分類され、仕事上の困難に結びつきやすい代表的なタイプとして、主に以下の3つが挙げられます。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性と仕事での傾向
ASDは、「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」と「限定された興味・こだわり」を主な特性とします。スペクトラムという名の通り、特性の現れ方は人によって様々です。DSM-5では、従来の自閉症、アスペルガー症候群などの下位分類が統合され、現在はASD(自閉スペクトラム症)として診断されています。
| 特徴 | 仕事での困りごと例 |
|---|---|
| こだわりの強さ・思考の柔軟性 | ・自分なりの手順やルールに固執し、非効率でもやり方を変えられない ・急な仕様変更や業務内容の変更に対応するのが極めて苦手 |
| 対人関係・コミュニケーション | ・曖昧な指示(「あれ、やっといて」など)の意図を理解できない ・相手の表情や声のトーンから感情を読み取ることが難しい ・会議などで暗黙の了解が分からず、場の空気を乱す発言をしてしまうことがある |
| 感覚の特性(過敏または鈍麻) | ・オフィス内の騒音や光、匂いなどが気になり、極度に疲労する(感覚過敏) ・逆に、空腹や疲労に気づきにくく、体調を崩しやすい(感覚鈍麻) |
ADHD(注意欠如多動症)の特性と仕事での傾向
ADHDは、「不注意(集中力・注意力のコントロールの困難)」、「多動性(落ち着きのなさ)」、「衝動性(思いつきで行動してしまう)」の3つを主な特性とします。DSM-5-TR(2022年)では正式に「注意欠如多動症」という診断名になっています。
| 特徴 | 仕事での困りごと例 |
|---|---|
| 不注意 | ・メールの宛先間違いや添付忘れ、誤字脱字などケアレスミスが多い ・物をどこに置いたか忘れ、探し物ばかりしている ・重要な会議中でも他の考えが浮かんでしまい、話を聞き逃す |
| 多動性 | ・デスクワークで長時間座っていることができず、そわそわしてしまう ・貧乏ゆすりやペン回しなど、無意識な動きが止められない |
| 衝動性 | ・考えがまとまる前に発言してしまい、議論を混乱させることがある ・相手の話を最後まで聞かずに、遮って話し始めてしまう ・思いついたことをすぐ実行しようとし、計画性に欠ける |
SLD(限局性学習症)の特性と仕事での傾向
SLD(限局性学習症)は、DSM-5において正式名称とされており、以前は学習障害(LD)と呼ばれていました。全般的な知的発達に遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」といった特定の能力を習得し、使うことに著しい困難がある状態を指します。
| 特徴 | 仕事での困りごと例 |
|---|---|
| 読字障害(ディスレクシア) | ・マニュアルや長文のメールを読むのに非常に時間がかかる、内容を正確に理解できない ・文字が歪んで見えたり、どこを読んでいるか分からなくなったりする |
| 書字表出障害(ディスグラフィア) | ・文字の形を整えて書くのが苦手で、議事録などの手書きが困難 ・漢字を思い出せない、簡単な単語でもスペルを間違える |
| 算数障害(ディスカリキュリア) | ・桁の多い数字の計算や、簡単な暗算が苦手 ・数量の比較や概算、時間の管理などに困難を感じる |
これらの特性は一つだけ現れるとは限らず、例えばASDとADHDの両方の特性を併せ持つ人も少なくありません。大切なのは、自分の困難がどの特性に起因するのかを理解することです。
【当事者向け】明日からできる!困難を乗り越える具体的な仕事術

自分の特性を理解したら、次は具体的な対策です。能力を変えるのは難しくても、やり方や環境を工夫することで、仕事のパフォーマンスは大きく改善できます。
対処法①:環境を調整する
集中力を削いだり、ミスを誘発したりする要因を、物理的に排除・低減する工夫です。
- 物理的環境の調整
- デスク周り: 視界に入る情報を減らすため、机の上には今使うもの以外置かない。書類はカテゴリ別にクリアファイルやボックスで管理し、必ずラベリングする。
- ノイズ対策: 周囲の音が気になる場合は、ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓の着用を会社に相談してみましょう。
- 座席の配慮: 可能であれば、人の往来が少ない壁際の席や、仕切りのあるブース席への移動を願い出るのも有効です。
- 人的環境(コミュニケーション)の調整
- 指示の受け方: 曖昧な指示は必ず確認し、「〇〇という理解で合っていますか?」と復唱する癖をつける。口頭での指示は忘れてしまう可能性が高いため、メールやチャットなど、文字で残してもらうようにお願いする。
- 報連相のルール化: 報告のタイミング(例:〇時と△時に定時報告)や方法(例:テンプレートを使う)を上司と決めておくと、迷いがなくなります。
対処法②:ツールを徹底活用する
記憶力や注意力を補うために、テクノロジーやアナログなツールを積極的に活用しましょう。
| 困りごと | おすすめのツール・活用法 |
|---|---|
| タスク・スケジュール管理 | ・Googleカレンダー、Todoist、Trello: 全ての予定やタスクを一つのツールに集約。締め切り前に通知が来るようリマインダーを複数設定する。 |
| 時間管理 | ・タイムタイマー、ポモドーロ・テクニック: 視覚的に残り時間が分かるタイマーで時間を意識する。「25分集中+5分休憩」のサイクルで集中力を維持する。 |
| メモ・アイデア整理 | ・Google Keep、Evernote: 思いついたことをすぐに記録。音声入力機能を活用すれば、書くのが苦手でも手軽にメモが取れる。 |
| 読み書きの補助 | ・音声読み上げソフト、OCRアプリ: 資料を読むのが苦手な場合、テキストを音声で聞く。手書きのメモをテキストデータ化する。 |
対処法③:自分の「取扱説明書」を作る
自分自身で特性を理解するだけでなく、周囲にも正しく理解してもらうことは、働きやすさに直結します。
- 得意なこと・苦手なことを言語化する:
「マルチタスクは苦手ですが、一つのことに集中して取り組む作業は得意です」のように、具体的に書き出します。 - こういう時に困る、という状況を伝える:
「急な予定変更があると混乱しやすいです」「口頭での指示は忘れてしまいがちです」など、困る状況を伝えます。 - してほしい配慮を具体的に提案する:
「指示は箇条書きのテキストでいただけると助かります」「作業に集中したい時はイヤホンをさせてください」など、相手が行動しやすいレベルでお願いを伝えます。
これを上司との面談などで共有することで、不要な誤解を防ぎ、必要な配慮を得やすくなります。
【上司・同僚向け】発達障害のある方への効果的なサポート方法

職場のメンバーが少し関わり方を工夫するだけで、当事者は安心して能力を発揮できるようになります。これは2024年4月に施行された改正障害者差別解消法により、事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されており、単なる思いやりではなく法的な責務となっています。特別な対応というよりは、「誰にとっても分かりやすい、働きやすい職場づくり」のヒントとして捉えてください。
指示は「具体的」かつ「明確」に
抽象的な表現は避け、具体的な行動レベルまで落とし込んで伝えることが重要です。
| 悪い例(NG) | 良い例(OK) |
|---|---|
| 「この資料、いい感じにまとめといて」 | 「この資料のAとBのデータを引用して、PowerPointで5枚のスライドにまとめてください。目的はC部長への進捗報告です。締め切りは明日の15時です」 |
| 「なるべく早くお願い」 | 「今日の17時までに、まずはドラフト(下書き)を見せてください」 |
タスクは分解し、優先順位を明確にする
大きなプロジェクトは、当事者にとってどこから手をつけていいか分からなくなりがちです。
- タスクの細分化:
「新商品企画」という大きなタスクではなく、「①市場調査」「②競合分析」「③コンセプト立案」のように、具体的な作業工程に分解して依頼します。 - 優先順位の明示:
「まず最優先で①を、次に②をお願いします。③はまだ着手しなくて大丈夫です」と、番号を振るなどして優先度を明確に伝えます。
定期的な進捗確認とポジティブなフィードバック
任せきりにせず、短いサイクルで進捗を確認する機会を設けましょう。これにより、万が一、方向性がずれていても早期に修正できます。
また、できたことや改善した点を具体的に褒めるポジティブなフィードバックは、本人の自信とモチベーション向上に繋がります。
強みを引き出す役割分担を考える
苦手なことを克服させるよりも、得意なことを活かせる環境を整える方が、本人にとっても組織にとっても有益です。
例えば、細部へのこだわりが強い人にはデータチェックや校正作業を、発想が豊かな人にはアイデア出しのブレインストーミングへの参加を促すなど、特性を強みとして捉えた役割分担を検討しましょう。
困難は「強み」になる!発達障害の特性を活かせる仕事とは

発達障害の特性は、見方を変えれば唯一無二の「強み」になります。ここでは、それぞれの特性が活かされやすい仕事の例をいくつかご紹介します。
ASDの強み:集中力、探求心、正確性
興味のある分野に対する高い集中力や、徹底的に探求する姿勢、ルールや手順を忠実に守る正確性は、専門職で大きな強みとなります。
- 向いている仕事の例:
- IT・技術職: プログラマー、システムエンジニア、Webデザイナー
- 研究・専門職: 研究者、データサイエンティスト、経理、校正者
- その他: 図書館司書、倉庫管理、職人
ADHDの強み:行動力、発想力、好奇心
枠にとらわれないアイデアを生み出す力、興味のあることに対するフットワークの軽さや行動力は、変化の多い仕事で輝きます。
- 向いている仕事の例:
- 企画・クリエイティブ職: 企画、マーケター、デザイナー、ライター
- 営業・接客職: 営業(特に新規開拓)、販売員、イベントプランナー
- その他: 起業家、ジャーナリスト、カメラマン
もちろん、これらはあくまで一例です。大切なのは、自分の「好き」や「得意」を軸に、特性との相性が良い職業分野や職場環境を見つけていくことです。
一人で抱え込まないで。頼れる相談先と支援サービス

もし、仕事の悩みが深刻で、自分一人の工夫や職場の配慮だけでは解決が難しいと感じたら、外部の専門機関に相談することも非常に重要です。
会社内の相談窓口
まずは、社内の相談窓口を活用してみましょう。
- 産業医・保健師:
労働安全衛生法に基づき、従業員の健康管理を専門としており、医学的な観点からアドバイスをもらえます。常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務付けられています。 - 人事部・労務部:
働き方や配属に関する相談が可能です。合理的配慮の提供について相談することもできます。 - 信頼できる上司:
自分の「取扱説明書」を共有し、理解を求める最初のステップとして重要です。
地域の専門機関
お住まいの地域にある公的な専門機関は、無料で相談に乗ってくれます。
| 機関名 | 主な役割 |
|---|---|
| 発達障害者支援センター | 発達障害者支援法第14条に基づき設置された、発達障害に関する総合的な相談窓口。本人だけでなく家族からの相談も可能で、生活から就労まで幅広く支援する。各都道府県・指定都市に設置。 |
| 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ) | 障害者雇用促進法に基づき設置された機関で、障害のある方の「働きたい」と「生活したい」を一体的に支援する。就職活動のサポートから職場定着支援まで行う。全国に337ヶ所設置(2024年4月時点)。 |
| ハローワーク(専門援助部門) | 障害のある方向けの専門窓口があり、求人紹介や就職に関する相談ができる。専門知識を持った相談員が配置されている。 |
就職・転職をサポートするサービス
今の職場環境がどうしても合わない場合、転職も有力な選択肢です。
- 就労移行支援事業所:
障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、障害のある方が就職するために必要なスキルを学ぶ訓練や、就職活動のサポート、就職後の定着支援を受けられる。全国に約3,300ヶ所設置(2024年時点)。 - 障害者専門の転職エージェント:
発達障害の特性に理解のある企業の求人を多数扱っており、専門のキャリアアドバイザーが面接対策や企業との条件交渉などをサポートしてくれます。
まとめ:自分の特性を理解し、あなたに合った働き方を見つけよう

「仕事ができない」と感じる辛い経験は、決してあなたの価値を決めるものではありません。それは、単に今の「環境」や「やり方」が、あなたの「特性」と合っていない(ミスマッチが起きている)というサインなのかもしれません。
重要なのは、以下の3つのステップです。
- 知る: まずは自分の特性を客観的に理解する。
- 工夫する: 自分に合った仕事術やツール、環境調整を試す。
- 相談する: 一人で抱え込まず、上司や同僚、専門機関を頼る。
この記事で紹介した情報が、あなたが自分らしく、持っている強みを最大限に活かせる働き方を見つけるためのきっかけになれば幸いです。あなたの未来は、あなたが思っているよりもずっと明るい可能性に満ちています。
注意事項:
本記事は情報提供を目的としたもので、医学的診断に代わるものではありません。診断は必ず専門の医療機関にご相談ください。記事内容は一般的な情報であり、お悩みの方は支援機関への相談をお勧めします。
記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医










