「就労移行支援に毎日通ったのに、就職できなかった…」
「貴重な2年間を費したのに、結局なにも変わらなかった。無駄だったかもしれない…」
もしあなたが今、そんな風に自分を責め、後悔の念に苛まれているとしたら、まず一番にお伝えしたいことがあります。
その経験は、決して無駄ではありません。
そして、就労移行支援を利用しても就職に至らないケースは、決してあなただけではないという事実です。
確かに、就職という目標が達成できなかったことは、辛く、悔しいことだと思います。しかし、その過程で得た学びや気づきは、間違いなくあなたの血肉となっています。それは、次のステップへ進むための、そして「自分に合った働き方」を見つけるための、何より貴重な羅針盤になるのです。
この記事では、なぜ就職に繋がらなかったのかを冷静に分析し、その悔しい経験を「価値ある経験」へと転換し、未来へ繋げるための具体的な方法を一緒に考えていきます。
記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。
読み間違いがありますが、ご容赦ください。
▼ 就労移行支援、無駄じゃなかった!就職できなかった経験から「自分だけのトリセツ」を見つける方法

なぜ?就労移行支援で就職できない主な7つの理由

まずは、就職に至らなかった原因を客観的に探ってみましょう。これは、誰かを責めるためではなく、次の一歩をより確かなものにするために、状況を冷静に整理するための大切なステップです。
理由1: 事業所とあなたの相性が合わなかった
最も多いのがこのケースです。毎日通う場所だからこそ、事業所との相性は結果を大きく左右します。
- 訓練プログラムのミスマッチ
あなたが目指す職種(例: 事務職)と、事業所が提供するプログラム(例: 軽作業中心)にズレはありませんでしたか? - 雰囲気や人間関係
スタッフの対応は丁寧でしたか?他の利用者と安心して過ごせる環境でしたか?小さなストレスの積み重ねが、就職活動への意欲を削いでしまうことがあります。 - サポート体制の不足
定期的な面談の機会は十分にありましたか?応募書類の添削や面接練習など、具体的なサポートは手厚かったでしょうか。
理由2: 「就職」への焦りが強すぎた
「早く就職しなければ」という焦りが、かえって視野を狭めてしまうことがあります。体調やスキルの準備が整う前に就職活動を始めてしまうと、うまくいかないことが続き、自信を失ってしまう悪循環に陥りがちです。まずは心と体の状態を安定させることが、就職への一番の近道です。
理由3: 企業が求めるスキル・経験とのミスマッチ
事業所で学んだスキルと、実際の障害者雇用の求人で求められるスキルにギャップがあった可能性も考えられます。企業側が「配慮はするが、任せたい業務がある」と考えているのに対し、自分ができることとの間に隔たりがあると、採用にはなかなか結びつきません。
理由4: 利用目的が曖昧だった
「障害者手帳を取得したから、とりあえず行ってみよう」というように、明確な目標がないまま利用を開始すると、訓練のモチベーションを維持するのが難しくなります。「どんなスキルを身につけたいか」「どんな働き方を実現したいか」という目的意識が、2年間の使い方を大きく変えます。
理由5: 体調や生活リズムが不安定だった
就労移行支援の大きな目的の一つは、安定して働き続けるための生活リズムと体力を身につけることです。週5日の通所がギリギリの状態で、そこからさらに就職活動の負荷がかかると、体調を崩してしまうことも少なくありません。まずは安定した通所を続けることが最優先です。
理由6: 事業所の就職実績やサポート体制の問題
残念ながら、すべての事業所が高い就職実績や手厚いサポート体制を持っているわけではありません。
- 企業の開拓力
事業所が独自に開拓した求人が少なく、ハローワークの求人を横流しするだけになっていないか。 - 実践的サポートの質
応募書類の添削が形式的だったり、面接練習が不十分だったりすると、選考通過率は上がりません。
このように、利用者側だけでなく事業所側に課題があるケースも少なくないのです。
理由7: そもそも就労移行支援が最適なサービスではなかった
あなたの状態や目指すゴールによっては、就労移行支援以外の福祉サービスの方が適している場合があります。
| サービス種別 | 主な対象者 | 目的・内容 |
|---|---|---|
| 就労移行支援 | 一般企業への就職を目指す方 | 就職に必要な知識・スキル習得、就活支援、定着支援(原則2年) |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約を結び働きたいが、一般企業は難しい方 | 雇用契約に基づき、支援を受けながら働く。最低賃金が保障される |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約を結ばず、自分のペースで働きたい方 | 軽作業などを通じ、工賃を得る。比較的自由なペースで利用可能 |
| 自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活を送りたい方 | 食事や金銭管理など、生活能力の維持・向上を目指す |
もし、「働くこと以前に、まずは生活リズムを整えたい」という段階であれば、自立訓練の方が合っていたかもしれません。

「無駄だった」は間違い。就労移行支援で得られた5つのこと
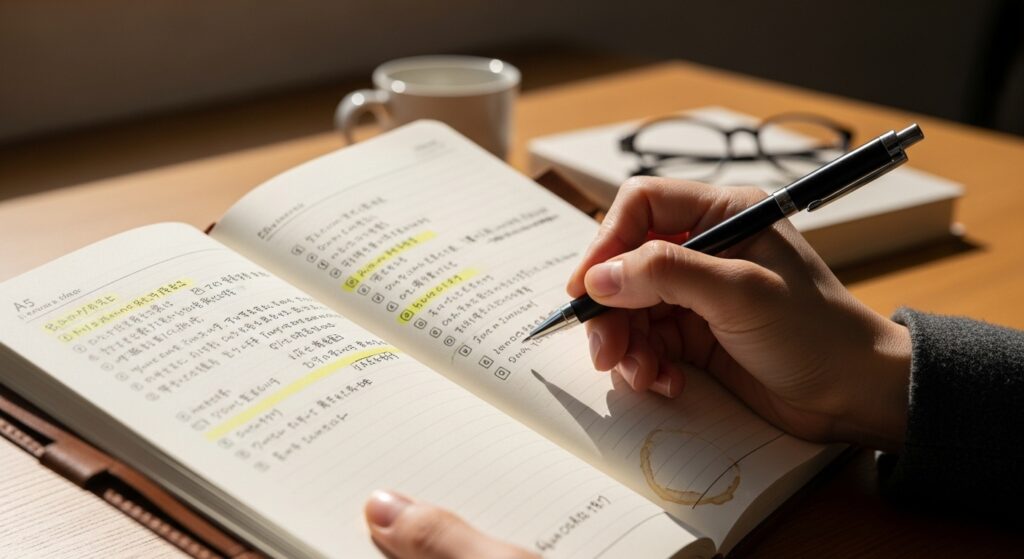
結果として就職に繋がらなかったとしても、あなたが過ごした時間に価値がなかったわけでは決してありません。視点を変えれば、次のステージで必ず役立つ「財産」を手にしているはずです。
- 安定した生活リズムの基礎
決まった時間に起き、準備をして、家を出る。この一連の行動を繰り返した経験は、働く上での最も重要な土台です。たとえ毎日通えなかったとしても、「外に出る」という習慣を続けたこと自体に大きな価値があります。 - コミュニケーションの経験値
事業所のスタッフや他の利用者との関わりは、良くも悪くもコミュニケーションの訓練になります。「報告・連絡・相談」の練習や、意見が違う人との適切な距離の取り方など、集団生活の中でしか学べないスキルを経験しました。 - 深い自己理解(得意・不得意の再発見)
様々な訓練プログラムを試す中で、「この作業は集中できる」「こういう環境は苦手だ」といった、自分の特性を具体的に理解できたのではないでしょうか。これは、今後の職業選択や、働く上での配慮事項を伝える際に、非常に重要な情報となります。 - 基本的な実務スキル
多くの事業所では、WordやExcel、ビジネスマナーなどの基本的な訓練を行います。たとえ完璧に使いこなせなくても、「一度学んだことがある」という事実は、次の学びへのハードルを下げ、自信に繋がります。 - 社会資源との繋がりというセーフティネット
あなたは「困った時に相談できる場所」を知りました。就労移行支援事業所だけでなく、地域の支援センターやハローワークなど、様々な社会資源の存在を知れたことは、今後の人生における大きなセーフティネットになります。

【次の一歩】就職できなかった経験を活かすための具体的なアクションプラン

では、その価値ある経験を手に、次に何をすべきか。具体的な4つのステップをご紹介します。
ステップ1: 経験の棚卸しと「就活の軸」の再設定
まずは、今回の経験を客観的に振り返り、言語化することから始めましょう。
- 失敗要因の分析
なぜ就職に至らなかったのか、前のセクションで挙げた7つの理由などを参考に書き出してみる。 - 得られたもののリストアップ
「無駄じゃなかったこと」で挙げた5つの視点で、自分が得たもの、できるようになったことを具体的にリスト化する。 - 就活の軸の再設定
上記を踏まえ、「どんな環境なら無理なく働けそうか」「仕事に求める最低条件は何か」「どんなサポートがあれば頑張れそうか」を改めて考え、自分の「軸」を再設定します。
ステップ2: 別の就労移行支援事業所を探す(セカンドオピニオン)
「一度失敗したからもうこりごり」と思うかもしれません。しかし、事業所との相性が原因だった場合、場所を変えるだけで、驚くほどうまくいく可能性があります。次は失敗しないために、以下のチェックリストを活用してください。
【失敗しないための事業所選びチェックリスト】
| チェック項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| プログラム内容 | □自分が目指す職種に合った専門的なプログラムがあるか? □実践的な内容か(座学だけでなく、実務に近い訓練があるか) |
| 就職実績 | □就職者数だけでなく、「就職先の職種」「定着率」も公開しているか? □自分の希望する業界・職種への就職実績があるか? |
| サポート体制 | □スタッフの専門性(精神保健福祉士、キャリアコンサルタント等の資格保有者はいるか) □面談の頻度や、相談のしやすさはどうか □企業インターン(実習)の機会は豊富か |
| 事業所の雰囲気 | □見学・体験時に、スタッフや利用者の表情は明るいか □清潔感があり、集中できる環境か □自分と年齢や障害特性が近い利用者はいるか |
見学や体験の際には、「前の事業所では〇〇が合わなかったのですが、こちらではどのようなサポートをしてもらえますか?」と具体的に質問することで、より的確な回答を得られます。
ステップ3: ハローワークや障害者就業・生活支援センターを活用する
就労移行支援だけに頼らず、他の支援機関を併用することで、より多角的なサポートが受けられます。
- ハローワーク(障害者専門窓口)
豊富な求人情報と、専門職員による職業相談が受けられます。 - 障害者就業・生活支援センター
就職だけでなく、金銭管理や住居など、生活面も含めた一体的な相談が可能です。就職後の定着支援も手厚いのが特徴です。
ステップ4: 就職以外の選択肢も視野に入れる
すぐに一般就労を目指すことだけがゴールではありません。少し遠回りに見えても、自分に合ったステップを踏むことが大切です。
- 就労継続支援A型・B型
まずは支援のある環境で「働くこと」に慣れ、自信をつける。 - 自立訓練
生活リズムや体調管理に課題がある場合、まずは生活の土台作りに専念する。 - 学び直し
障害者向けの職業訓練校(正式名称: 障害者職業能力開発校、通称: アビリティセンター)や、大学・専門学校で専門知識を身につけるという選択肢もあります。

Q&A|就労移行支援の「無駄」「就職できない」に関するよくある質問

最後に、多くの方が抱える疑問についてお答えします。
- Q就労移行支援の就職率はどのくらいですか?
- A
厚生労働省の最新の調査(令和4年度)によると、就労移行支援事業所からの一般就労への移行率は約52.9%です。 つまり、半数以上の方が就職に至っている一方で、半数近くの方は他の進路を選んでいる、あるいは利用を継続しているということになります。この数字は事業所によって大きく異なるため、あくまで参考値として捉えてください。
- Q利用期間(2年間)を使い切ってしまいました。もう利用できませんか?
- A
原則として利用期間は24ヶ月(2年)ですが、自治体の審査により、必要性が認められれば期間の延長や再利用が可能な場合があります。 ただし、延長や再利用が認められるには、初回利用時とは異なる目標設定や、就労への具体的な見込みなど、客観的な必要性を市区町村に説明する必要があり、必ずしも希望通りになるとは限りません。まずはお住まいの市区町村の障害福祉課の窓口に相談してみてください。
- Q「就職できなかった」という経歴は、面接で不利になりますか?
- A
いいえ、不利にはなりません。 むしろ、その経験をどう捉え、次にどう活かそうとしているかを前向きに語ることができれば、プラスの評価に繋がる可能性すらあります。
面接官は「就労移行支援で何を学びましたか?」という質問を通して、あなたの自己理解度や課題解決能力を見ています。「〇〇という課題が見つかったので、次は△△を意識して働きたいです」というように、経験を学びに変えて話すことが重要です。

まとめ
就労移行支援を利用して就職できなかったという経験は、決してあなたの価値を下げるものではありません。それは、ゴールに辿り着くための一つのプロセスであり、「自分に本当に合った道」を探すための貴重な試行錯誤の時間だったのです。
悔しさや焦りを感じるのは当然です。しかし、その感情に蓋をせず、経験を客観的に分析し、得られたものを一つひとつ数え上げてみてください。そうすれば、次の一歩は、以前よりもずっと確かな、あなただけの道になるはずです。
一人で抱え込まず、信頼できる家族や、新しい支援機関のスタッフにぜひ相談してみてください。あなたの未来は、これからです。

【免責事項】
この記事に掲載されている情報は、2025年8月時点のものです。制度や法律は変更される可能性がありますので、最新かつ正確な情報については、厚生労働省やお住まいの自治体の公式サイトをご確認ください。









