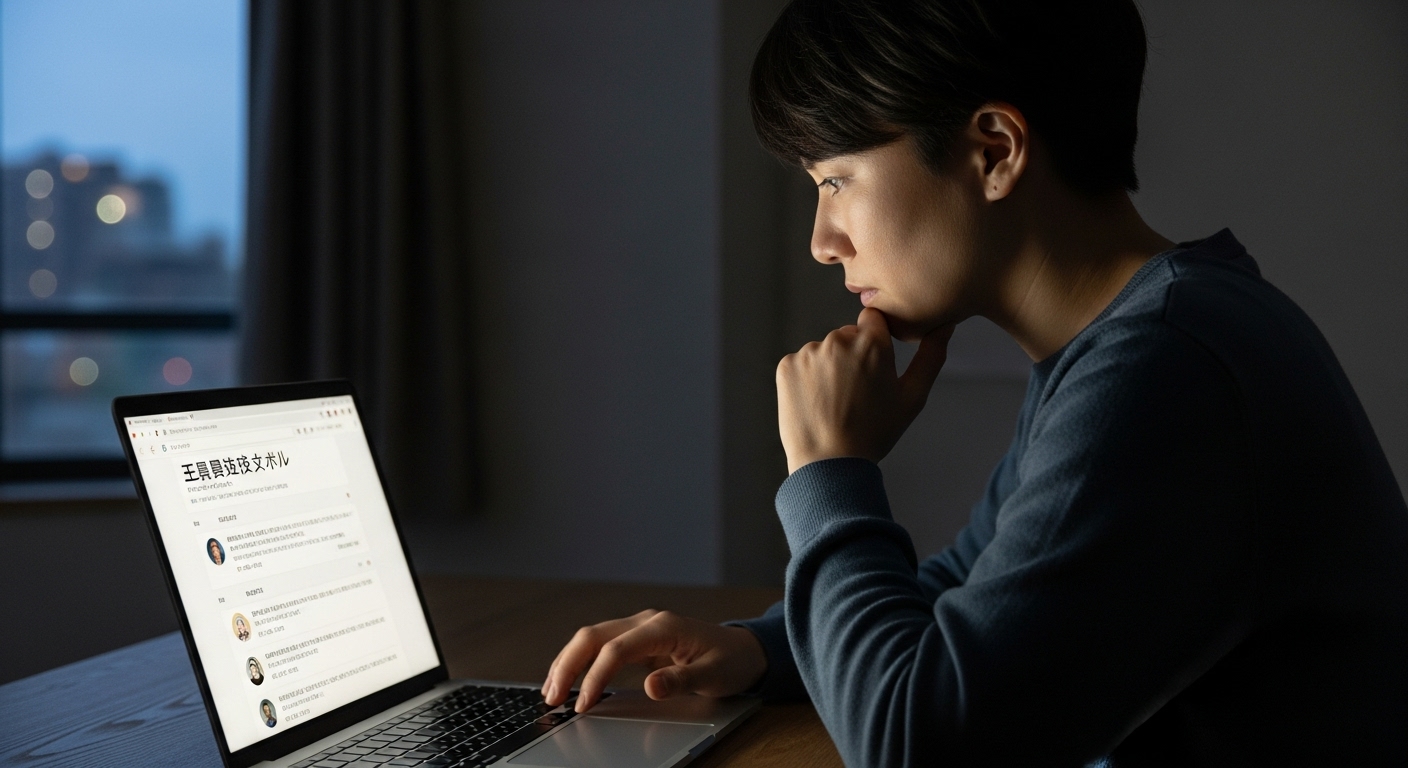「就労移行支援って、ネットで見ると『ひどい』とか『意味ない』って書かれてて不安…」
「知人から『やめとけ』って言われたけど、本当にそうなのかな?」
障害や病気と向き合いながら、就職を目指して情報収集する中で、そんなネガティブな評判を目にして、一歩踏み出すことをためらってはいませんか?
大切な時間とお金を投資するかもしれないサービスだからこそ、絶対に失敗したくない、後悔したくないと思うのは当然のことです。
ご安心ください。この記事では、なぜ就労移行支援に「ひどい」「意味ない」といった声が上がるのか、その根本的な理由を5つのポイントから徹底的に分析します。
そして、その上で「あなたにとって最高の支援」を提供してくれる優良な事業所を、ご自身の目で見抜くための具体的な7つのチェックポイントを詳しく解説します。
この記事を最後まで読めば、ネットの評判に惑わされることなく、あなたの不安は「自信」に変わります。そして、あなたの未来を切り拓くための、力強い一歩を踏み出せるようになるはずです。
記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。
読み間違いがありますが、ご容赦ください。
▼就労移行支援「ひどい・意味ない」は本当?後悔しない事業所の選び方と活用術
▼あわせて読みたい記事
なぜ就労移行支援は「ひどい」「意味ない」と言われるのか?5つの理由

まず、なぜ一部で「やめとけ」とまで言われてしまうのか。その背景には、残念ながら利用者と事業所の間に生まれる「ミスマッチ」や、一部の事業所が抱える構造的な問題が存在します。
理由1:事業所の質に大きな差がある
最も大きな原因は、事業所の数が増え続ける一方で、その「質」が玉石混交であるという点です。厚生労働省の令和5年度(2023年度)の調査によると、全国に約3,150ヶ所の事業所があります。その中には、利益だけを追求するような質の低い事業所も紛れています。
- 儲け主義の事業所の存在
就労移行支援は国の給付金で運営されています。そのため、利用者の就職や定着よりも、とにかく利用者数を確保して給付金を得ることを優先する事業所が残念ながら存在します。このような事業所では、支援が手薄だったり、形式的なトレーニングばかりだったりする傾向があります。 - スタッフの専門性や経験が不足している
利用者をサポートするスタッフの質も、事業所によって大きく異なります。障害に関する知識や、キャリアカウンセリングの経験が浅いスタッフが担当になると、的確なアドバイスがもらえず、「相談しても意味がない」と感じてしまうことがあります。
理由2:プログラムの内容が合わない・レベルが低い
事業所が提供する訓練プログラムが、自分自身のスキルや目指すキャリアと合っていない場合、「通う意味がない」と感じてしまいます。
- カリキュラムが画一的で、個別のニーズに対応していない
例えば、事務職を目指しているのに、軽作業やビジネスマナー研修ばかり…といったケースです。利用者一人ひとりの希望や特性に合わせた個別支援計画がきちんと作られていないと、貴重な時間を無駄にしてしまう可能性があります。 - 簡単な作業ばかりでスキルアップに繋がらない
「パソコンの入力練習だけ」「毎日同じ書類の封入作業だけ」など、誰にでもできるような簡単な作業しか提供されず、専門的なスキルが全く身につかないという声も聞かれます。
理由3:「就職」だけがゴールになっている
就労移行支援の目的は「就職し、長く働き続けること」のはずです。しかし、事業所によっては目先の「就職率」を追い求めるあまり、本質を見失っている場合があります。
- 就職実績を重視するあまり、無理な就職を勧めてくる
事業所の実績を上げるために、本人の希望や特性を無視して、とにかく就職できそうな企業を半ば強引に勧めてくるケースです。これでは、たとえ就職できても長続きしません。 - 就職後の定着支援が手薄い
就職が決まった途端にサポートが終了し、入社後に壁にぶつかっても相談に乗ってもらえない。これも「意味ない」と感じる大きな原因です。本来、就職後の定着支援こそが、就労移行支援の価値ある部分なのです。
理由4:人間関係のトラブル
閉鎖的な環境で毎日顔を合わせるため、人間関係の悩みはつきものです。
- スタッフとの相性が悪い(高圧的、親身でないなど)
支援を受けるはずのスタッフから心ない言葉をかけられたり、悩みを真剣に聞いてもらえなかったりすると、通所自体が大きなストレスになります。 - 他の利用者とのコミュニケーションがストレスになる
様々な特性を持つ利用者が集まるため、どうしても他の利用者との間でトラブルが起きたり、グループワークが苦痛に感じたりすることもあります。
理由5:期待していたサポートが受けられない
見学時や説明会で受けた印象と、実際に利用を開始してからの現実にギャップがあるケースです。
- 「聞いていた話と違う」というミスマッチ
「PCスキルが学べると聞いたのに、実際は自習ばかり」「いつでも相談できると言われたのに、スタッフはいつも忙しそう」など、事前の期待値が高いほど、裏切られたと感じてしまいます。 - 事務的な対応で、親身な相談ができない
何か相談してもマニュアル通りの対応しかされず、一人ひとりの状況に寄り添ったサポートが受けられないと、「ここいても意味がない」という無力感につながります。
「やめとけ」は早計?就労移行支援のメリット・デメリットを再確認

「ひどい」と言われる理由を見て不安になったかもしれませんが、それはあくまで一部の側面です。多くの人が就労移行支援を活用して、希望のキャリアを実現しているのもまた事実です。ここで一度、冷静にメリットとデメリットを整理してみましょう。
就労移行支援のメリット
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 生活リズムの安定 | 決まった時間に通所することで、昼夜逆転などを改善し、働くための体力をつけられる。 |
| 専門スキルの習得 | PCスキル(Word, Excel)、デザイン、プログラミングなど、就職に直結する専門知識を無料で学べる。 |
| 自己理解の深化 | スタッフとの面談やプログラムを通して、自分の得意・不得意や、働く上での配慮事項を客観的に把握できる。 |
| 手厚い就職活動サポート | 履歴書添削、面接練習、求人紹介、企業見学の同行など、一人では難しい就活を全面的に支援してもらえる。 |
| 就職後の定着支援 | 就職後も定期的な面談などで、職場での悩みや課題を相談でき、長く働き続けるためのサポートが受けられる。 |
| 同じ悩みを持つ仲間との出会い | 同じ目標を持つ仲間と交流することで、孤独感が和らぎ、情報交換や励まし合いができる。 |
就労移行支援のデメリット
| デメリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 必ず就職できる保証はない | あくまで「支援」サービスであり、本人の努力や状況によっては就職に至らないケースもある。 |
| 質の低い事業所に当たるリスク | 前述の通り、事業所の質にばらつきがあり、合わない場所を選んでしまうと時間と労力を無駄にする可能性がある。 |
| 利用期間の制限 | 原則2年間という利用期間の上限があるため、焦りを感じることがある。 |
| 費用がかかる場合がある | 前年度の世帯所得によっては、自己負担額が発生する場合がある。(多くの場合は無料) |
| 人間関係のストレス | スタッフや他の利用者との相性が合わない場合、通所が精神的な負担になることがある。 |
【最重要】後悔しない!「ひどい事業所」を絶対に見抜く7つのチェックポイント

ここからが本題です。数多くの事業所の中から、あなたにとって本当に価値のある「優良事業所」を見つけ出すための、具体的なチェックポイントを7つご紹介します。見学や体験利用の際には、このリストを片手に、鋭い目でチェックしてみてください。
1. 実績は「就職率」より「定着率」を重視する
多くの事業所が「就職率90%以上!」といった高い数値をアピールしていますが、本当に見るべきは「定着率」です。定着率とは、就職した人がその後も長く(半年や1年後)働き続けられているかを示す割合です。
- なぜ定着率が重要か?
高い就職率は、無理な就職をさせた結果かもしれません。しかし、高い定着率は、その事業所の支援が利用者の特性とマッチしており、就職後のサポートもしっかりしていることの何よりの証拠です。 - 確認方法
「就職された方の、半年後や1年後の定着率はどのくらいですか?」とストレートに質問しましょう。明確な数字をすぐに答えられたり、公表データを見せてくれたりする事業所は信頼できます。逆に言葉を濁すようなら要注意です。半年後で85%以上が、質の高い事業所の一つの目安ですが、これは公的な平均値ではありません。厚生労働省のデータでは就職1年後の定着率は約80%台で推移しており、これを大きく上回るかどうかがポイントになります。
2. プログラムの内容と個別支援計画を確認する
あなたの「こうなりたい」という目標を実現できるプログラムがあるか、具体的に確認しましょう。
- スキルアップできる具体的なカリキュラムか?
「PC講座」といった漠然とした説明だけでなく、「ExcelのVBA講座」「Illustratorを使ったデザイン講座」など、具体的な内容を確認します。時間割や月間スケジュールを見せてもらいましょう。 - 自分の希望や特性に合わせた個別支援計画を作成してくれるか?
「入所したら、どのような流れで個別支援計画を立てていくのですか?」と質問し、アセスメント(評価)の方法や面談の頻度などを確認します。あなたの話をじっくり聞き、一緒に計画を考えてくれる姿勢があるかが重要です。
3. スタッフの専門性と人柄をチェックする
支援の質は、スタッフの質で決まります。資格だけでなく、その人柄も見極めましょう。
- 資格の有無
社会福祉士、精神保健福祉士、キャリアコンサルタントなどの専門資格を持つスタッフが在籍しているかは、一つの安心材料になります。 - スタッフの表情、言葉遣い、利用者への接し方
見学中に、スタッフが他の利用者とどう接しているかを観察しましょう。笑顔で対等な目線で話しているか、言葉遣いは丁寧か。あなたへの説明が丁寧なのは当然です。他の利用者への態度にこそ、その事業所の本質が現れます。
4. 事業所の雰囲気と他の利用者の様子を観察する
データや説明だけでは分からない「空気感」は非常に重要です。
- 明るく、清潔感があるか
整理整頓されていて、明るい雰囲気の場所は、通うモチベーションにも繋がります。逆に、薄暗かったり、物が散乱していたりする場所は避けましょう。 - 利用者が主体的に活動しているか、表情はどうか
利用者の皆さんの表情を見てみましょう。活き活きとプログラムに取り組んでいますか?それとも、ただ時間を潰しているように見えますか?利用者同士でコミュニケーションを取る様子があるかも、良い雰囲気の指標になります。
5. 提携している企業や就職先の実例を聞く
どのような企業への就職実績があるかは、その事業所の「出口」の質を示します。
- どのような業種・職種の企業と繋がりがあるか?
障害者雇用に理解のある優良企業とのパイプがあるかを確認します。企業からの実習を積極的に受け入れているかもポイントです。 - 自分の希望する働き方に近い就職実績があるか?
「私のような〇〇の障害特性がある方で、△△職に就職された方の事例はありますか?」と具体的に聞いてみましょう。プライバシーに配慮しつつ、過去の事例を具体的に話してくれる事業所は、支援のノウハウが豊富である可能性が高いです。
6. 費用と交通費について明確に説明を求める
お金の話は聞きにくいかもしれませんが、後々のトラブルを避けるために不可欠です。
- 利用料金の計算方法
就労移行支援の自己負担額は、前年度の世帯所得によって決まります。ほとんどの方が無料で利用できますが、該当する可能性がある場合は、計算方法を明確に説明してもらいましょう。 - 交通費や昼食代の補助の有無
事業所によっては、交通費や昼食代を補助してくれる場合があります。毎日通うとなると大きな差になるので、必ず確認しておきましょう。
7. 口コミや評判を鵜呑みにせず、必ず自分の目で確かめる
ネットの口コミは参考にはなりますが、それが全てではありません。
- ネットの口コミの信憑性
良い口コミも悪い口コミも、一個人の主観的な感想です。あなたに合うかどうかは、あなた自身でしか判断できません。 - 複数の事業所を見学・体験することの重要性
面倒でも、最低3ヶ所以上の事業所を見学・体験利用することを強くお勧めします。比較することで、それぞれの事業所の長所・短所が明確になり、「自分に合うのはここだ」という確信を持って選ぶことができます。
▼ネット上の噂に惑わされず、まずは制度の本来の目的や仕組みを正しく理解することが大切です。就労移行支援の正しい活用法については、以下の記事で徹底解説しています。
もし「ひどい事業所」に入ってしまったら?3つの対処法

万全の準備をしても、実際に利用してみたら「合わない」と感じる可能性はゼロではありません。もしそうなってしまっても、一人で抱え込まず、すぐに行動しましょう。
1. 事業所内の相談員や責任者に相談する
まずは、事業所内部での解決を試みましょう。担当スタッフとの相性が悪い場合、事業所の管理者やサービス管理責任者(サビ管)に相談することで、担当を変更してもらえたり、環境が改善されたりする可能性があります。
2. 市区町村の障害福祉課に相談する
事業所内での解決が難しい場合は、お住まいの市区町村の障害福祉担当課や、基幹相談支援センターに相談しましょう。ここは、サービスの利用計画を立てる際にやり取りをした公的な窓口です。事業所に対して指導・助言を行ってくれる場合があります。
3. 他の事業所への変更を検討する
どうしても改善が見られない場合は、事業所を変更することも可能です。支給決定期間内であれば、手続きを行うことで他の事業所に移ることができます。合わない場所で我慢し続ける必要は全くありません。
まとめ:正しい知識で、就労移行支援を「最高の味方」にしよう
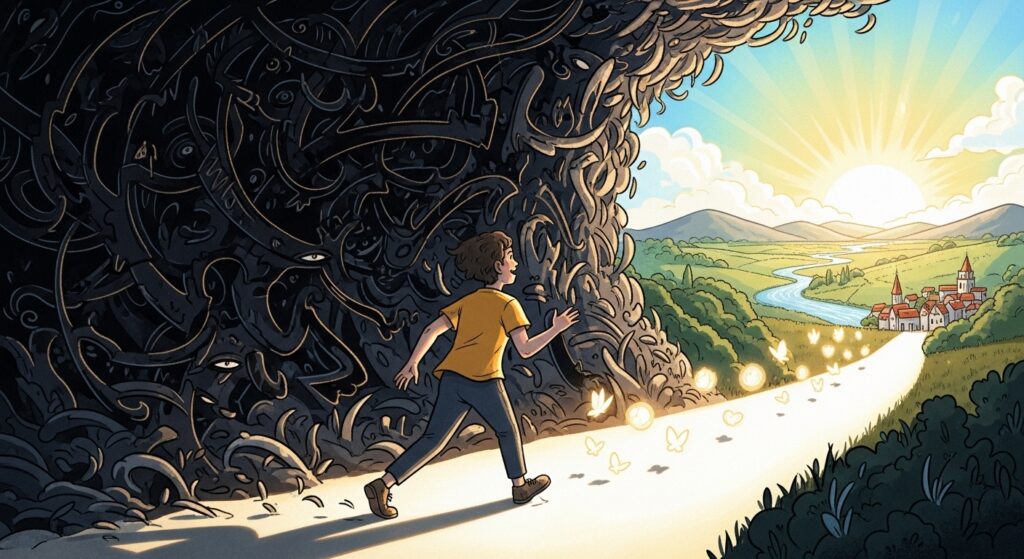
「就労移行支援はひどい」「意味ないからやめとけ」
こうした厳しい評判は、残念ながら一部に存在する質の低い事業所や、利用者とのミスマッチによって生まれてしまっている側面があります。
しかし、この記事でご紹介した7つのチェックポイントを活用すれば、ネットの不確かな情報に振り回されることなく、あなたの目標達成を全力でサポートしてくれる「最高のパートナー」となる事業所をご自身の力で見つけ出すことが可能です。
不安な気持ちは、情報を集め、自分の目で確かめることでしか解消できません。
この記事が、あなたの胸の中にある不安を少しでも和らげ、未来へ向かうための、前向きで、力強い一歩を踏み出すきっかけとなれたなら、これほど嬉しいことはありません。
最終更新日: 2025年8月17日
注意: 制度や事業所の情報は変更される場合があります。最新の情報は各事業所の公式サイトや、お住まいの市区町村の窓口で必ずご確認ください。