「いつかは親元を離れて自立したい」
「でも、一人で暮らしていくのは正直、不安…」
「親亡き後の生活はどうなるんだろう…」
障害のある方やそのご家族にとって、「自立」と「暮らし」は、希望であると同時に大きな不安が伴うテーマではないでしょうか。
そんな「一人暮らしは不安、でも自分らしく生きたい」という想いに応える選択肢の一つが、共同生活援助(グループホーム)です。
共同生活援助は、プライバシーが守られた個室で生活しながら、食事や金銭管理、健康面でのサポートなど、必要な支援を受けられる「暮らしの場」です。決して施設に”入る”のではなく、地域のアパートや一軒家で、数人の仲間とともに、支援を受けながら”暮らす”というイメージです。
この記事では、共同生活援助(グループホーム)について、
「どんなサービス?」
「費用はどのくらい?」
「実際の生活はどんな感じ?」
といった基本的な疑問から、メリット・デメリット、入居までの具体的なステップまで、あらゆる情報を網羅して、どこよりも分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、共同生活援助が「自分らしい暮らし」を実現するための力強い選択肢であることが分かり、未来への第一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えているはずです。
▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。
共同生活援助(グループホーム)の基本を5分で理解!

まずは「共同生活援助って、そもそも何?」という基本から見ていきましょう。難しい言葉は使わず、ポイントを絞って解説します。
どんなサービス?を一言で解説
共同生活援助(グループホーム)とは、一言でいうと「障害のある方が、支援を受けながら少人数で共同生活を送る『住まいの場』」のことです。
多くは地域の中にある普通の一軒家やアパートなどを活用しており、世話人(せわにん)や生活支援員(せいかつしえんいん)といったスタッフが、入居者の自立した生活をサポートします。
重要なのは、これが「障害者総合支援法」という法律に基づいた、国の正式な福祉サービスであるという点です。そのため、利用料の補助など、安心して利用できる仕組みが整っています。
誰が利用できるの?【対象者】
基本的に、知的障害、精神障害、身体障害、難病などがあり、支援を受けながら地域での自立した生活を目指したい方が対象となります。
- 障害種別:
知的障害、精神障害(発達障害も含む)、身体障害、難病等の方が利用できます。障害者手帳がなくても、医師の診断書などで障害があると認められれば対象となる場合があります。 - 障害支援区分:
必ずしも障害支援区分(障害の程度を示すもの)の認定は必要ありません。「共同生活を営むのに支障がない」と判断されれば利用可能です。 - 年齢:
原則として18歳以上の方が対象です。ただし、身体障害のある方については、65歳以降の新規利用は制限される場合があります(65歳前からの継続利用は可能)。また、15歳以上の児童でも、児童相談所長の意見により利用が適当と認められた場合は利用可能です。
「自分は対象になるのかな?」と迷ったら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に問い合わせてみましょう。
グループホームにはどんな種類がある?
グループホームは、提供される支援の内容によって、主に3つのタイプに分かれます。どのタイプが合うかは、ご本人が必要とする支援の量によって異なります。
| タイプ名 | 特徴 | こんな方におすすめ |
|---|---|---|
| 介護サービス包括型 | 事業所のスタッフが、食事や相談支援に加えて、入浴や排せつなどの介護も一体的に提供します。 | 主に夜間や休日に、見守りだけでなく身体的な介護も必要な方 |
| 外部サービス利用型 | 食事や相談支援は事業所のスタッフが行い、入浴などの介護が必要な場合は、外部のヘルパー事業所などと契約して利用します。 | 身体的な介護はあまり必要なく、自分のペースで生活したい方 |
| 日中サービス支援型 | スタッフが24時間体制で常駐し、日中も含めて手厚い支援や介護を提供します。 | 短期入所を併設している場合が多く、緊急時の対応や家族の休息(レスパイト)にも活用できます。 |
| 移行支援住居 | 2024年度の新設サービスとして、移行支援住居も追加されました。これは、一人暮らし等を希望し可能と見込まれる利用者が、共同生活援助から退所に向けて移行支援を受けるための新しい仕組みです。 |
このほか、グループホームの近くにあるアパートなどで一人暮らしをしながら支援を受ける「サテライト型住居」という形もあります。将来の完全な一人暮らしに向けたステップアップとして利用されることが多いです。
グループホームでの暮らしを徹底解剖!サービス内容と1日の流れ

では、実際にグループホームではどのような生活が待っているのでしょうか。具体的なサポート内容と、利用者の1日のスケジュール例から、暮らしのイメージを膨らませてみましょう。
具体的にどんな支援を受けられるの?【サービス内容】
グループホームで受けられる支援は、身の回りのことだけでなく、健康面や社会と繋がるためのサポートまで多岐にわたります。スタッフは「何でもやってあげる」のではなく、本人ができることは見守り、苦手な部分を一緒に練習しながら、自立を後押ししてくれます。
| サポートの種類 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 食事 | 栄養バランスを考えた朝食・夕食の提供、休日の昼食作り、一緒に買い物や調理の練習 |
| 家事 | 部屋の掃除や洗濯のサポート、ゴミ出しのルールの確認 |
| 健康管理 | 毎日の服薬の確認、体調が悪い時の相談、病院への通院同行 |
| 金銭管理 | お小遣いの管理方法の助言、公共料金の支払いのサポート |
| 相談・助言 | 仕事や人間関係の悩み相談、将来の目標(一人暮らしなど)に向けた計画作り |
| 余暇活動 | 休日の外出(買い物、映画など)の計画、季節ごとのイベント(クリスマス会など)の企画・参加 |
| 連携 | 日中活動の場(作業所や会社)との連絡調整、関係機関との連携 |
| 移行支援(2024年度新設) | 一人暮らし等を希望する利用者への支援、退去時の定着支援 |
利用者のリアルな1日を覗いてみよう【スケジュール例】
暮らし方は人それぞれですが、ここでは一般的なスケジュール例を2パターンご紹介します。
【平日:日中に作業所へ通うAさんの例】
| 時間 | スケジュール |
|---|---|
| 6:30 | 起床、身支度 |
| 7:00 | 朝食(世話人さんが用意した温かいごはん) |
| 8:00 | 出発「いってきます!」と作業所の送迎バスへ |
| 9:00~16:00 | 日中活動(就労継続支援B型事業所で軽作業) |
| 17:00 | 帰宅「ただいま!」、お茶を飲んで一息 |
| 18:30 | 夕食(他の利用者さんと談笑しながら) |
| 19:30 | 入浴、洗濯 |
| 20:30 | 自由時間(自分の部屋でテレビを見たり、リビングでおしゃべりしたり) |
| 22:00 | 就寝 |
【休日:グループホームで過ごすBさんの例】
| 時間 | スケジュール |
|---|---|
| 8:00 | 起床(ゆっくりめの朝) |
| 8:30 | 朝食 |
| 10:00 | 掃除・洗濯(自分の部屋や共有スペースを掃除) |
| 12:00 | 昼食(世話人さんと一緒に簡単な昼食を作る) |
| 14:00 | 外出(近くのスーパーへ買い物、図書館へ行くなど) |
| 17:00 | 帰宅 |
| 18:30 | 夕食 |
| 20:00 | 自由時間(趣味のイラストを描く、共有スペースでDVD鑑賞) |
| 22:30 | 就寝 |
気になる費用は?月々いくらかかるの?【料金徹底ガイド】
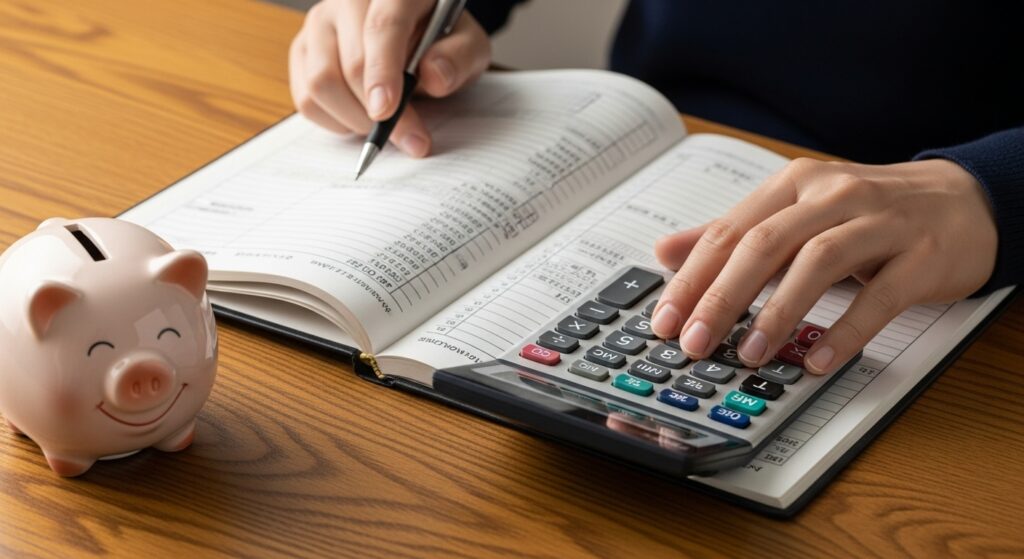
自立した生活を考える上で、お金のことは最も重要なポイントの一つです。グループホームの費用は、意外と複雑ではありません。大きく分けて3つの費用から成り立っています。
費用の内訳は大きく3つ
①サービス利用料(国が定める費用)
障害福祉サービスの利用にかかる費用で、原則として1割が自己負担となります。しかし、所得に応じた月ごとの負担上限額が決められており、それを超える分は支払う必要がありません。
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
②家賃
お部屋代です。グループホームの家賃は、その地域の家賃相場によって大きく異なり、地域差が顕著です。都市部では月額5万円~8万円程度、地方では月額2万円~4万円程度が一般的です。
ここで知っておきたいのが、国の補助制度です。「特定障害者特別給付費(補足給付)」という制度があり、収入などの条件を満たせば、月額最大1万円の家賃補助が受けられます。
さらに、自治体によっては独自の家賃補助制度を設けている場合もあるので、市区町村の窓口で確認してみましょう。
③その他の実費
日常生活で必要になるお金です。具体的には以下のようなものが含まれます。
- 食費: 朝食・夕食の材料費として、月額25,000円~35,000円程度が目安です。
- 水道光熱費: 月額1万円~1.5万円程度を、入居者全員で分担したり、共益費として支払ったりします。
- 日用品費: トイレットペーパーや洗剤など、共同で使う消耗品代です。
これらの実費は事業所によって設定が異なるため、契約前に必ず確認することが大切です。
【モデルケース】障害年金で生活できる?月額費用のシミュレーション
「障害年金だけでも生活できるの?」という疑問に、具体的なシミュレーションでお答えします。
【収入(2025年8月時点の最新金額)】
- 障害基礎年金2級: 約69,308円(月額)
- 就労継続支援B型事業所の工賃: 約17,000円(全国平均、地域差あり)
- 収入合計: 約86,308円
【支出】
| 項目 | 金額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃 | 25,000円 | 家賃3.5万円から国の補助1万円を引いた額 |
| 食費 | 30,000円 | 朝夕提供の場合 |
| 水道光熱費 | 10,000円 | 共益費として |
| 日用品費など | 5,000円 | |
| サービス利用料 | 0円 | 住民税非課税世帯のため |
| 支出合計 | 70,000円 |
【手元に残るお金】
収入 86,308円 – 支出 70,000円 = 16,308円
このシミュレーションでは、毎月16,308円が手元に残る計算になります。このお金を、携帯電話代や趣味、お小遣い、貯金などに充てることができます。このように、多くの場合、障害年金と工賃の範囲内で十分に生活することが可能です。
グループホームを利用するメリットと注意点

グループホームでの生活は、多くのメリットがある一方で、共同生活ならではの注意点も存在します。両方を正しく理解し、自分に合った選択をすることが大切です。
自立への大きな一歩!5つのメリット
- 安心感:
体調が悪い時や困ったことがあった時、すぐに相談できるスタッフがいる安心感は何物にも代えがたいです。夜間もスタッフがいるため、緊急時も安心です。 - 生活リズムの安定:
食事や就寝の時間が決まっているため、自然と規則正しい生活リズムが身につき、心身の健康を保ちやすくなります。 - 社会的交流:
他の利用者と日常的に関わる中で、コミュニケーションの練習ができ、社会性が育まれます。孤独を感じにくくなるのも大きなメリットです。 - 家族の負担軽減:
ご本人が自立した生活を送ることで、これまで介護や支援を担ってきたご家族は、心身の負担が軽くなり、自分の時間を持つことができます。これを「レスパイト(休息)」と呼びます。 - 自立へのステップアップ:
スタッフの支援を受けながら家事や金銭管理を練習することで、将来的な一人暮らしに向けたスキルと自信を身につけることができます。2024年度からは移行支援住居という新しい仕組みも始まり、一人暮らしへの移行支援がさらに充実しています。
知っておきたい3つの注意点(デメリット)と対策
- プライバシーと人間関係
- 課題: 共同生活のため、ある程度の音や気配が気になることも。また、他の利用者やスタッフと性格が合わない可能性もゼロではありません。
- 対策: 見学時に、個室の広さや壁の厚さ、リビングでの過ごし方などをしっかり確認しましょう。人間関係のミスマッチを防ぐためにも、契約前の「体験利用」は非常に重要です。
- ルールや制約
- 課題: 門限、外泊のルール、食事の時間など、集団生活を円滑に送るための一定のルールが存在します。
- 対策: 自分にとって「これだけは譲れない」という条件は何かを整理しておきましょう。見学や体験利用の際にルールについて詳しく質問し、自分のライフスタイルに合うかを見極めることが大切です。
- すぐに入居できない可能性
- 課題: 特に都市部ではグループホームの需要が高く、希望してもすぐに空きがない場合があります。全国で約15万人が利用している人気のサービスです。
- 対策: 「そろそろ考えたいな」と思った段階で、早めに地域の相談支援事業所などに相談を始めることをお勧めします。複数の候補をリストアップしておくことも有効です。
入居までの完全ロードマップ【探し方から契約まで】

「グループホーム、良さそうだな」と思ったら、次は何をすればいいのでしょうか。相談から契約までの流れを、4つのステップで分かりやすく解説します。
STEP1: 相談する
最初の第一歩は、専門家への相談です。一人で悩まず、まずは以下の窓口に連絡してみましょう。
- 市区町村の障害福祉課:
地域のグループホームの情報や、利用できる制度について教えてくれます。 - 相談支援事業所:
「相談支援専門員」という、障害福祉サービスの利用計画を立ててくれるプロがいます。あなたに合ったグループホーム探しを、中立的な立場でサポートしてくれます。
STEP2: 探す・見学する
相談支援専門員などと連携しながら、候補となるグループホームを探し、実際に見学に行きます。
- 探し方:
相談支援事業所からの紹介のほか、福祉医療機構が運営する「WAM NET(ワムネット)」というサイトで全国の事業所を検索できます。2024年度からは情報公表システムとしても活用されており、より詳しい情報が確認できるようになりました。 - 見学時のチェックリスト:
見学は、暮らしのミスマッチを防ぐ最大のチャンスです。以下のリストを参考に、気になる点はすべて質問しましょう。
| チェック項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| 居室・共用部 | 部屋の広さ、日当たり、収納は十分か。清潔に保たれているか。お風呂やトイレは使いやすいか。 |
| 人・雰囲気 | スタッフはどんな表情で働いているか。他の利用者はどんな雰囲気で過ごしているか。支援の方針は自分に合っているか。 |
| ルール・生活 | 門限や外泊、食事の時間はどうなっているか。来客は可能か。金銭管理はどのようにサポートしてくれるか。 |
| 周辺環境・立地 | 最寄り駅からの距離、スーパーやコンビニ、病院は近くにあるか。日中活動の場所へのアクセスは良いか。 |
| 費用 | 家賃や食費、光熱費など、月々の総額はいくらになるか。支払い方法はどうか。 |
| 新しい取り組み | 一人暮らしへの移行支援や地域との連携など、最新のサービスに取り組んでいるか。 |
STEP3: 体験利用する
気になるグループホームが見つかったら、契約の前に「体験利用」をさせてもらいましょう。数日から1週間程度、実際に宿泊して生活を体験することで、雰囲気や支援内容が本当に自分に合っているかを最終確認できます。食事の味や夜間の様子など、見学だけでは分からない部分を知る絶好の機会です。
STEP4: 申請・契約
体験利用を経て「ここに決めたい」となれば、いよいよ手続きです。
- 障害福祉サービス受給者証の申請:
共同生活援助を利用するために必要な「受給者証」を市区町村に申請します。(多くの場合、相談支援専門員がサポートしてくれます) - 事業所との利用契約:
グループホームの運営事業者と正式に利用契約を結びます。契約書の内容はしっかり確認し、分からない点は遠慮なく質問しましょう。
【まとめ】共同生活援助は「自分らしい暮らし」への扉

共同生活援助(グループホーム)について、その基本から具体的な暮らし、費用、入居までの流れを詳しく解説してきました。
改めてお伝えしたいのは、共同生活援助は、単に「住む場所」を提供するサービスではないということです。
それは、安心できる環境と、信頼できるスタッフのサポートを受けながら、自立した生活に挑戦し、自分らしい人生を築いていくための、大切なステップです。
2024年度の制度改正により、一人暮らしへの移行支援がさらに充実し、より多様な暮らし方の選択肢が増えています。また、全国で約15万人が利用している実績があり、多くの方が安心して地域での生活を送っています。
親元を離れて生活することには、大きな希望と同じくらいの不安があるかもしれません。しかし、あなたが一歩踏み出すことを応援し、支えてくれる人や場所が必ずあります。
この記事を読んで、少しでも「話を聞いてみようかな」と思えたなら、ぜひお住まいの地域の相談窓口に足を運んでみてください。一人で抱え込まず、専門家と一緒に考えることで、未来への道はきっと拓けていきます。
あなたが、あなたらしく輝ける最高の暮らしを見つけられることを、心から願っています。
【記事の正確性について】
本記事は2025年10月時点の制度に基づいて作成されています。制度は定期的に改正されるため、最新情報については厚生労働省や各自治体の公式情報をご確認ください。金額等については地域差があるため、詳細は地元の相談窓口にお問い合わせください。









