「何度言っても伝わらない」
「良かれと思ってしたことが、いつも裏目に出てしまう」
「家の中で、私だけが我慢している気がする…」
パートナーや親、成人した子どもに対して、そんな風に感じていませんか?
出口の見えないトンネルの中にいるような孤独感と、「自分の努力が足りないのかもしれない」という罪悪感。その尽きない悩みとストレスは、決してあなたのせいでも、愛情不足が原因でもありません。
それは、本人に悪気はないと頭では分かっていても、どうしても生じてしまう「発達障害の特性」との関わりの中で生まれる、特有のストレスなのかもしれません。
この記事では、脳科学・心理学の知見に基づき、大人の発達障害を持つご家族が抱えるストレスの正体を丁寧に解き明かします。そして、あなたがこれ以上自分を責めることなく、あなた自身を守りながら、家族とより良い関係を築いていくための具体的な方法を、一つひとつ分かりやすく解説します。
もう一人で抱え込まないでください。この記事が、あなたの心を少しでも軽くする一助となることを願っています。
▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。
【セルフチェック】もしかして「カサンドラ症候群」?

家族との関係で強いストレスを感じているなら、まず「カサンドラ症候群(カサンドラ状態)」について知っておくことが大切です。これは正式な病名ではありませんが、多くの家族が苦しんでいる状態を指す言葉です。
カサンドラ症候群とは?
カサンドラ症候群とは、ASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害の特性を持つパートナーや家族と、情緒的な相互関係を築くことが難しい状況の中で、もう一方が深刻な心身の不調をきたしてしまう状態を指します。
この状態の辛い点は、悩みを周囲に相談しても「考えすぎだよ」「誰にでもあること」などと理解されにくく、共感を得られないために孤立が深まってしまうことにあります。
こんな症状はありませんか?心身のサインをチェック
もし、あなたに以下のサインが複数当てはまるなら、一人で抱え込まずに専門家の助けを求めることを検討してください。
| 分類 | 具体的な症状 |
|---|---|
| 身体的症状 | □ 原因不明の頭痛やめまいが続く □ 眠れない、または寝ても疲れが取れない □ 動悸や息苦しさを感じることがある □ 慢性的な疲労感、倦怠感がある □ 食欲不振または過食 |
| 精神的症状 | □ 気分が落ち込み、何もやる気が起きない □ 自分を責め、自己肯定感が著しく低下している □ 些細なことでイライラしたり、涙が出たりする □ 常に不安感や焦燥感がある |
| 社会的症状 | □ 人と会うのが億劫になり、孤立している □ 「自分が我慢すれば丸く収まる」と諦めている □ 家族以外のことに興味や関心がなくなった |
これらのサインは、あなたの心が「もう限界だ」と悲鳴を上げている証拠です。決して見過ごさないでください。
なぜ?大人の発達障害の家族がストレスを抱える4つの原因
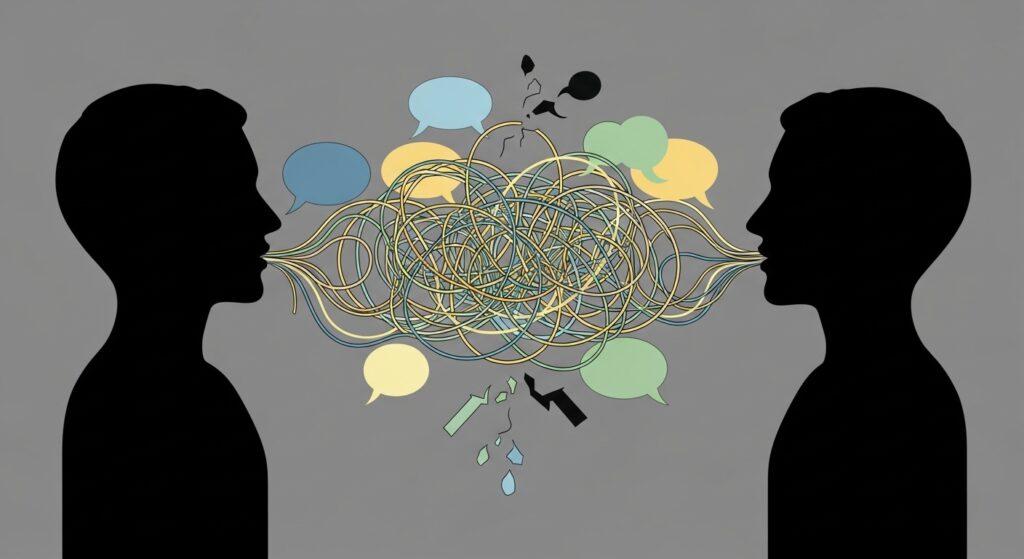
家族が抱えるストレスは、発達障害の「特性」への無理解や、それによって引き起こされるすれ違いが根本的な原因です。具体的に見ていきましょう。
1. コミュニケーションのすれ違い
発達障害、特にASD(自閉スペクトラム症)の特性を持つ人は、言葉の裏にある意図や感情を読み取ることが苦手な場合があります。
- 言葉を文字通りに受け取る
「(疲れたから)少し休みたい」という言葉の裏にある「手伝ってほしい」という気持ちを察することが難しい。 - 曖昧な表現が理解できない
「あれ、適当にやっておいて」といった指示では、何をどうすれば良いのか分からず混乱してしまう。 - 相手の表情や声色から感情を読めない
家族が怒っていたり悲しんでいたりしても、その変化に気づきにくい。
こうしたすれ違いが毎日続くと、「どうして分かってくれないの?」という不満や、「話すだけ無駄だ」という諦めの気持ちにつながり、大きなストレスとなります。
2. 共感性の欠如と一方的な関係性
相手の立場に立って気持ちを想像する「共感性」に課題があることも、家族を苦しめる一因です。本人に悪気はなくても、結果として家族は「気持ちを分かち合えない」という深い孤独を感じることになります。
- 喜びや悲しみを共有できない
嬉しい出来事を話しても反応が薄かったり、落ち込んでいる時に的外れなアドバイスをされたりする。 - 常に自分だけが相手に合わせている感覚
相手の興味や関心には付き合うが、自分の話は聞いてもらえない。 - 感謝や謝罪の言葉がない
「やってもらって当たり前」という態度に見え、家族の努力や苦労が報われないと感じる。
3. こだわりの強さと変化への抵抗
発達障害の特性として、物事の順序や配置、日々のルーティンなどに対する強いこだわりが見られることがあります。このこだわりが、家族の生活に大きな影響を与えることがあります。
- 独自のルールを強要する
タオルの畳み方から食事のメニューまで、細かいルールがあり、それを破るとひどく不機嫌になる。 - 急な予定変更に対応できない
楽しみにしていた家族旅行も、少しでも予定が変わるとパニックになったり、行くこと自体を拒否したりする。 - 柔軟な対応が難しい
「いつもと違う」状況への不安が強く、家族が常に気を遣い、振り回されてしまう。
4. 社会的役割のプレッシャーと孤立
家庭内での役割分担が著しく偏ることも、ストレスの大きな原因です。
- 家事・育児・金銭管理の負担
ADHD(注意欠如・多動症)の特性で、片付けやスケジュール管理、金銭管理が苦手な場合、その負担がすべてパートナーにのしかかる。 - 対外的な窓口役
親戚付き合いや学校行事など、コミュニケーションが必要な場面はすべて自分が担当しなければならない。 - 周囲に理解されない苦しみ
この大変さを親や友人に相談しても、「うちも同じよ」「あなたのわがままでは?」と軽くあしらわれ、誰にも分かってもらえないという孤立感を深めてしまう。
【ステップ別】今日からできる!家族のストレスを軽減する具体的な対処法

ストレスの原因が分かったら、次に行うのは具体的な対処です。重要なのは、「相手を変えようとする」のではなく、「自分を守り、関わり方を変える」ことです。
ステップ1:まず自分を守る「セルフケア」を最優先に
疲弊しきった状態では、どんな良い方法も実践できません。家族のためにも、まずはあなた自身の心と体を守ることを最優先してください。
物理的に距離と時間を確保する
常に一緒にいると、お互いの存在がストレス源になってしまいます。意識的に一人になれる時間と空間を作りましょう。
- 週末に数時間、一人で外出する
- 寝室を別にする
- 自治体のショートステイやレスパイトサービスを利用する
- 趣味のサークルなど、家庭以外の居場所を持つ
感情を吐き出す場所を見つける
溜め込んだ感情は、いつか必ず爆発してしまいます。安全な場所で、自分の気持ちを言葉にして吐き出しましょう。
- 信頼できる友人や親族に話を聞いてもらう
- 専門のカウンセラーに相談する
- 同じ悩みを持つ人が集まる家族会(自助グループ)に参加する
- 匿名で利用できるSNSやブログで気持ちを綴る
「べき思考」を手放す
「妻だからこうすべき」「親だから我慢すべき」といった役割意識は、あなたを追い詰める鎖になります。
- 完璧を目指さない: 家事が少し手抜きになっても大丈夫。
- 「助けて」と言う: 一人で全部やろうとせず、周りに助けを求めることを自分に許可する。
- 自分を褒める: 「今日も一日よくやった」と、頑張っている自分を認め、労ってあげましょう。
ステップ2:相手ではなく「特性」を理解する
相手の言動に腹が立った時、「なぜこの人はこうなんだ!」と人格を責めるのではなく、「これは〇〇という特性のせいなんだ」と捉え直すことが、ストレス軽減の鍵です。
発達障害の正しい知識を得る
厚生労働省のウェブサイトや専門書、信頼できる医療機関の情報を参考に、客観的な知識を身につけましょう。「悪気があってやっているわけではない」と理解できるだけで、気持ちが楽になります。
得意なこと・苦手なことのリストアップ
本人と可能であれば一緒に、生活の中での「得意なこと」「苦手なこと」を書き出してみましょう。これは、感情的な対立を避け、問題解決に焦点を当てるための「取扱説明書」になります。
| 得意なこと | 苦手なこと | |
|---|---|---|
| 例 | ・一度決めたルールはきっちり守る ・興味のある分野の知識が豊富 | ・急な予定変更 ・複数のことを同時に頼まれる ・曖昧な指示を理解する |
ステップ3:コミュニケーションの「ルール」を作る
気持ちが伝わらない相手には、伝え方を変える工夫が必要です。家庭内に明確な「コミュニケーションルール」を作りましょう。
曖昧な表現を避け、具体的に伝える
「なぜ?」と問い詰めるのではなく、「どうしてほしいか」を具体的に伝えましょう。
- NG例: 「なんでいつも脱ぎっぱなしなの!」
- OK例: 「帰ってきたら、シャツとズボンは洗濯カゴに入れてください」
感情ではなく「情報」として伝える
感情的に訴えるより、事実や自分の気持ちを客観的に伝える方が響きます。「あなた」を主語にするのではなく、「私」を主語にする「アイメッセージ」が有効です。
- NG例(YOUメッセージ): 「あなたはいつも約束を忘れる!」
- OK例(Iメッセージ): 「私は、約束を忘れられると悲しい気持ちになる」
視覚情報を活用する
口頭での指示は忘れられやすい特性があります。言葉だけでなく、「見て分かる」情報で補いましょう。
- ホワイトボード: 家族の予定や「やることリスト」を共有する。
- スマートフォンのリマインダー/カレンダー: ゴミ出しの日や大切な約束をアラームで通知する。
- 写真やイラスト: やってほしい家事の手順を写真に撮って貼っておく。
ステップ4:一人で抱え込まない!外部の専門家やサービスを頼る
家庭内の問題は、家庭内だけで解決しようとすると行き詰まります。専門家や公的サービスという「第三者」の視点を入れることが極めて重要です。
| 相談先の種類 | 特徴 | 主な相談内容 |
|---|---|---|
| 発達障害者支援センター | 各都道府県・指定都市に設置。専門職員が相談に応じ、適切な支援機関につないでくれる総合窓口。 | 本人のこと、家族の悩み、利用できるサービス全般 |
| 精神保健福祉センター | 各都道府県・指定都市に設置。心の健康に関する相談窓口。家族からの相談も可能。 | 本人の精神状態、家族のメンタルヘルス |
| 医療機関(精神科・心療内科) | 発達障害の診断や治療、カウンセリングを行う。 | 確定診断、薬物療法、心理療法、家族への助言 |
| カウンセリングルーム | 臨床心理士などの専門家が対応。じっくり話を聞いてもらい、心理的なサポートを受けられる。 | 家族自身のストレス、夫婦関係、コミュニケーションの悩み |
| 家族会・自助グループ | 同じ立場の人たちが集まり、体験や情報を共有する場。ピアサポート。 | 日常の悩み、孤独感の解消、情報交換 |
これらの機関は、あなたとあなたの家族をサポートするために存在します。相談することは、決して恥ずかしいことではありません。
家族が診断を拒否…そんな時どうすればいい?

家族が自身の特性に気づいていなかったり、診断を受けることを頑なに拒否したりするケースは少なくありません。そんな時は、焦らず慎重に対応することが大切です。
無理に病院へ連れて行こうとしない
本人が受け入れていない段階で「あなたは病気だから病院へ行こう」と無理強いするのは逆効果です。本人のプライドを傷つけ、心を閉ざしてしまいます。まずは、家族が先に相談機関へ行き、専門家のアドバイスを受けることから始めましょう。
本人が感じている「困りごと」に焦点を当てる
「発達障害」という言葉を出さずに、本人が現実に感じているであろう「生きづらさ」や「困りごと」に焦点を当てて話してみましょう。
- 例: 「最近、仕事でミスが増えて辛そうだね。専門家に相談すれば、うまく集中できる方法が見つかるかもしれないよ」
- 例: 「人間関係で悩んでいるみたいだけど、コミュニケーションのコツを教えてくれる場所があるらしいよ」
本人の悩み解決に繋がる提案としてアプローチすることで、聞く耳を持ってもらいやすくなります。
第三者からのアプローチを検討する
家族からの言葉は素直に受け入れられなくても、本人が信頼している第三者(親友、尊敬する上司、かかりつけ医など)からの助言であれば、耳を傾けることがあります。事前にその方に状況を相談し、協力を仰ぐのも一つの方法です。
まとめ:希望を捨てずに、まず自分を大切にすることから始めよう

大人の発達障害を持つ家族との生活は、決して平坦な道のりではないかもしれません。コミュニケーションのすれ違いや、理解されない孤独感に、心が折れそうになる日もあるでしょう。
しかし、どうか忘れないでください。あなたが抱えているそのストレスは、決してあなたのせいではありません。
この記事で紹介したように、まずはあなた自身を守ることを最優先し、心と体にエネルギーを充電してください。そして、相手の「特性」を正しく理解し、コミュニケーションの「ルール」を作ることで、無用な衝突は確実に減らせます。
何より大切なのは、一人で抱え込まないことです。日本には、あなたと家族を支えるための専門機関やサービス、そして同じ悩みを持つ仲間たちがたくさんいます。勇気を出して、外部の力を借りてください。
状況は、必ず良い方向へ向かいます。この記事が、暗闇の中にいるあなたの足元を照らす、小さな光となることを心から願っています。
【情報の取り扱いに関するご注意】
この記事で紹介した相談窓口や公的制度に関する情報は、2025年10月時点のものです。ご利用の際は、お住まいの自治体や各機関の公式サイトにて最新の情報をご確認ください。また、この記事は情報提供を目的としており、医学的な診断や治療に代わるものではありません。心身の不調を感じる場合は、速やかに専門の医療機関にご相談ください。
記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医









