「また仕事が続かなかった…」
「自分はなんてダメなんだろう…」
何度も転職を繰り返すたびに、自信を失い、社会から取り残されたような孤独感に苛まれていませんか?
もしあなたが発達障害の特性によって働きづらさを感じているのなら、仕事が続かないのは、決してあなたの努力や能力が足りないからではありません。それは、あなたの「特性」と「働く環境」の間にミスマッチが起きているサインなのです。
この記事では、発達障害を持つ方が仕事でつまずきやすい根本的な原因を解き明かし、明日から実践できる具体的な対策、そしてあなたの強みを最大限に活かせる仕事や働き方まで、網羅的に解説します。
この記事を読み終える頃には、「自分に合う働き方が見つかるかもしれない」という希望の光が見え、次の一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。
記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。
読み間違いがありますが、ご容赦ください。
▼発達障害と仕事のミスマッチを乗り越える!特性を強みに変える実践的ヒントと多様な働き方
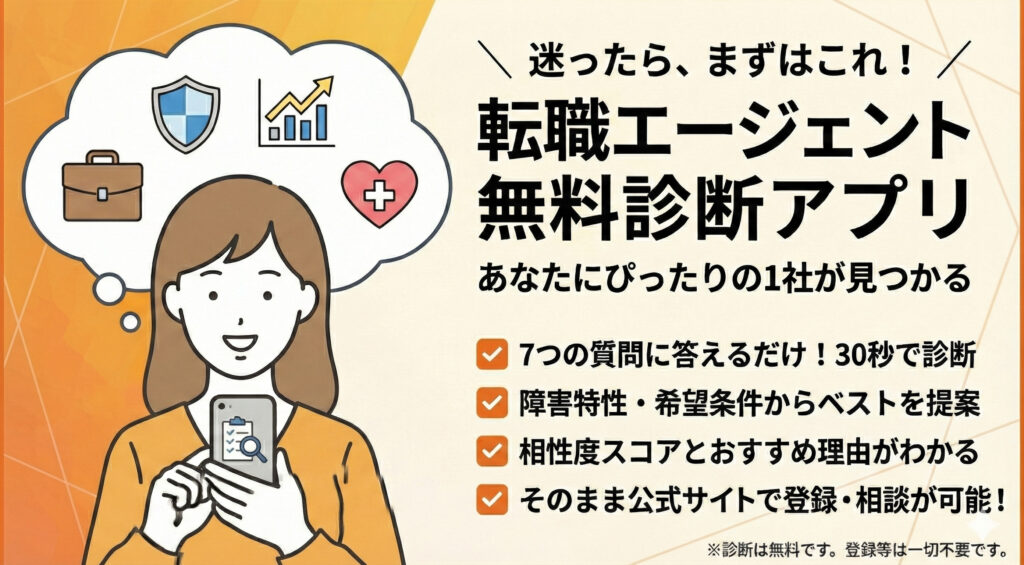
なぜ?発達障害で仕事が続かない5つの根本原因

原因1:ASD(自閉スペクトラム症)の特性による困難
ASDの特性を持つ方は、その真面目さや探究心の強さが仕事で高く評価される一方、以下のような困難を抱えることがあります。
- コミュニケーションの壁
「空気を読む」「暗黙の了解」といった曖昧なコミュニケーションが苦手で、言葉を文字通りに受け取ってしまい、人間関係で孤立してしまうことがあります。 - 感覚過敏
オフィスの蛍光灯の光、パソコンのファンの音、同僚の話し声などが大きなストレスとなり、仕事に集中できなくなることがあります。 - こだわりと変化への抵抗
決まった手順やルールへのこだわりが強く、急な仕様変更や予期せぬトラブルへの対応にパニックを起こしてしまうことがあります。
原因2:ADHD(注意欠如多動症)の特性による困難
ADHDの特性を持つ方は、その行動力や発想力が魅力ですが、衝動性や不注意といった特性が仕事の妨げになることがあります。
- 注意の持続が困難
重要な会議中に別の考えが浮かんで集中できなかったり、単純な事務作業でケアレスミスを連発してしまったりします。 - タスク管理の苦手さ
複数の業務を同時に進めることや、優先順位をつけて計画的に物事を進めるのが苦手で、納期遅れや仕事の抜け漏れが発生しがちです。 - 衝動性
思いついたことをすぐ口に出してしまったり、熟考せずに行動してしまったりすることで、周囲との摩擦を生むことがあります。
原因3:SLD(限局性学習障害)の特性による困難
特定のスキルの習得に著しい困難があるSLD。例えば、以下のようなケースがあります。
- 読字障害(ディスレクシア)
メールやマニュアルを読むのに時間がかかり、業務効率が上がらない。 - 書字表出障害(ディスグラフィア)
報告書などの文章作成が極端に苦手。 - 算数障害(ディスカリキュリア)
計算や数字の管理が苦手で、経理などの業務でミスが多くなる。
原因4:二次障害による心身の不調
職場で困難な状況が続くことで、過剰なストレスがかかり、うつ病や適応障害、不安障害といった「二次障害」を引き起こすことがあります。心身が疲弊し、出社すること自体が困難になってしまうケースも少なくありません。
原因5:職場環境とのミスマッチ
個人の特性だけでなく、職場環境との相性も非常に重要です。
| ミスマッチの例 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 業務内容 | 自分の興味や得意なことと、実際の業務内容がかけ離れている。 |
| 人間関係 | 障害への理解がなく、適切な配慮が得られない。高圧的な上司や同僚がいる。 |
| 物理的環境 | 騒がしいオープンオフィス、頻繁な電話対応など、感覚過敏には辛い環境。 |
| 企業文化 | 臨機応変な対応やマルチタスクを過度に求める文化になじめない。 |
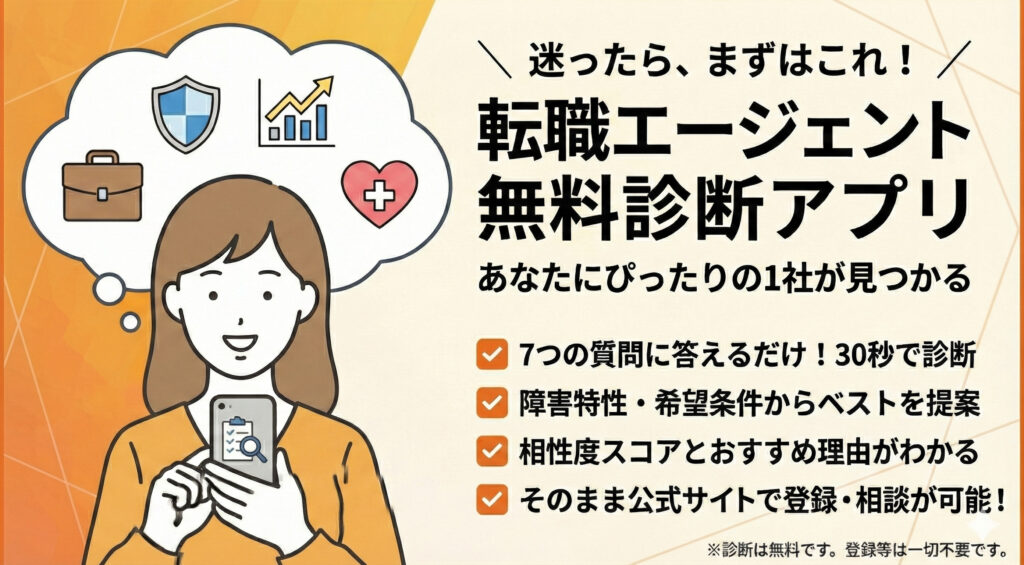
今すぐできる!仕事を続けるための具体的な7つの対策

STEP1:自分の「取扱説明書」を作る(自己理解)
まず、客観的に自分を理解することが重要です。ノートやアプリに書き出してみましょう。
- 得意なこと: (例)集中してデータ分析をすること、アイデアを出すこと
- 苦手なこと: (例)電話対応、マルチタスク、曖昧な指示の理解
- ストレスを感じる状況: (例)騒がしい場所、急な予定変更
- 必要な配慮: (例)指示はチャットで具体的にしてほしい、静かな席で作業したい
これは、後の「合理的配慮」を求める際にも役立つ重要な資料になります。
STEP2:環境を調整してもらう(合理的配慮)
自分の努力だけでは限界があります。勇気を出して、職場に配慮を求めてみましょう。伝え方のポイントは、「感情」ではなく「事実」と「代替案」をセットで伝えることです。
悪い例: 「うるさくて集中できないので、なんとかしてください!」
良い例: 「周りの音が気になってしまい、作業効率が落ちてミスが増えてしまいます。可能であれば、パーテーションのある席に移動させていただくか、ノイズキャンセリングイヤホンの使用を許可いただけないでしょうか?」
STEP3:タスク管理術を身につける
ADHDの特性がある方に特に有効です。便利なツールを積極的に活用しましょう。
- ToDoリストアプリ:
TodoistやMicrosoft To Doなどでタスクを可視化し、抜け漏れを防ぐ。 - タイマー: 「ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)」で集中力を持続させる。
- リマインダー: スマートフォンのリマインダー機能で、会議や提出期限を忘れないようにする。
STEP4:コミュニケーションの工夫
ASDの特性がある方は、コミュニケーションのルールを決めておくとスムーズです。
- 指示はメモ: 必ずメモを取り、復唱して認識のズレがないか確認する。
- 結論から話す: 「PREP法(結論→理由→具体例→結論)」を意識して、要点を簡潔に伝える練習をする。
- 報連相のテンプレート化: 報告の型を決めておくと、何を伝えれば良いか迷わなくなります。
STEP5:ストレスコーピングを見つける
意識的に心と体を休ませることが、長く働き続ける秘訣です。自分に合ったストレス解消法(コーピング)を複数持っておきましょう。
(例:散歩、音楽を聴く、好きな香りを嗅ぐ、瞑想アプリを使う)
STEP6:完璧主義を手放す
真面目な方ほど100%を目指してしまいがちですが、仕事は60?80%の完成度で十分な場合がほとんどです。「完璧じゃなくていい」「まずは完成させよう」と自分に言い聞かせましょう。
STEP7:小さな成功体験を積み重ねる
「今日はToDoリストを3つ完了できた」「報連相がスムーズにできた」など、どんなに小さなことでも自分を褒めましょう。自己肯定感を育むことが、働く意欲に繋がります。
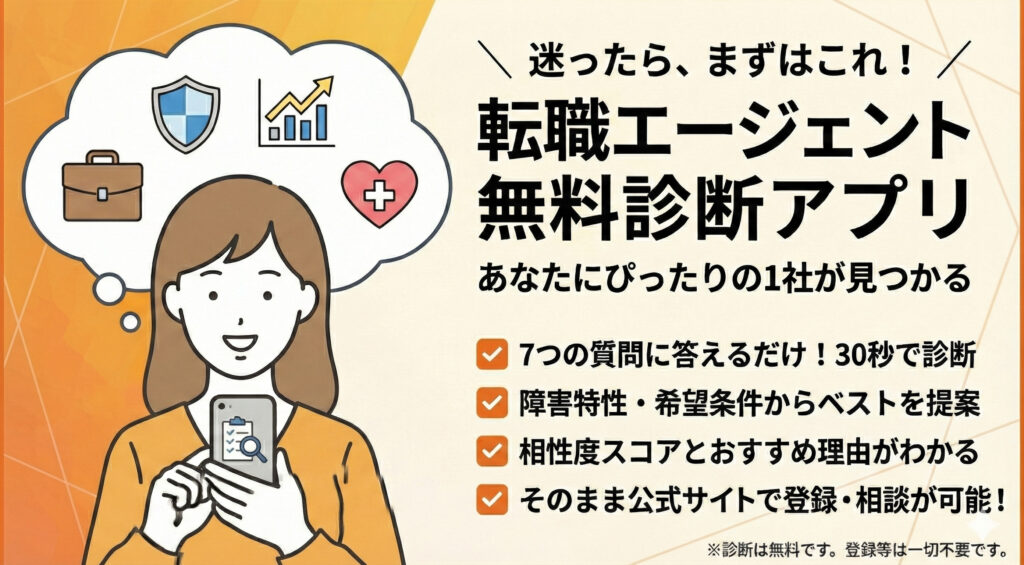
【特性別】あなたの強みを活かせる仕事15選

ASD(自閉スペクトラム症)の強みを活かせる仕事
| 強み | おすすめの仕事 | 理由 |
|---|---|---|
| 探究心・集中力 | プログラマー、Webデザイナー、研究職、テスター | 特定の分野を深く掘り下げ、一人で集中して取り組む作業に向いている。 |
| 几帳面さ・正確性 | 経理、校正・校閲、データ入力、品質管理 | ルールや手順に沿って、正確さが求められる作業で力を発揮する。 |
| 論理的思考 | Webマーケター、財務アナリスト、法務 | 客観的なデータや事実に基づいて、論理的に物事を分析・判断する能力が活かせる。 |
ADHD(注意欠如多動症)の強みを活かせる仕事
| 強み | おすすめの仕事 | 理由 |
|---|---|---|
| 行動力・発想力 | 企画・マーケティング、営業、ジャーナリスト、起業家 | アイデアを形にし、フットワーク軽く動くことが求められる仕事で活躍できる。 |
| 好奇心旺盛 | Webライター、動画編集者、イベントプランナー | 様々な情報に触れ、変化や刺激のある環境でモチベーションを維持しやすい。 |
| 対人への関心 | 販売員、カウンセラー、福祉職 | 独創的な視点や共感性を活かし、人と接する仕事でやりがいを感じられる場合がある。 |
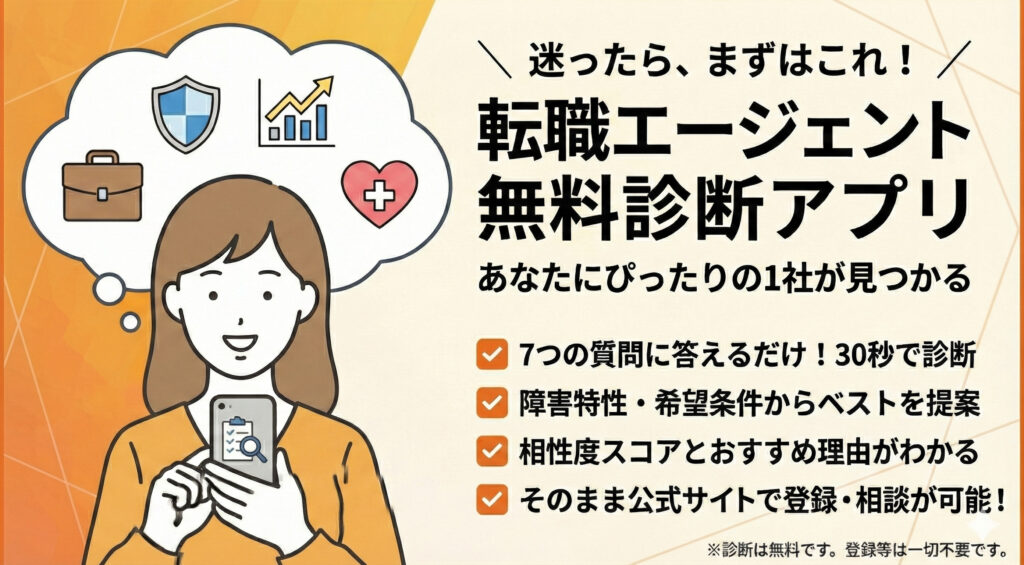
会社員だけが道じゃない!多様な働き方の選択肢

障害者雇用という選択肢
障害者手帳を取得している方が対象となる雇用形態です。合理的配慮を得やすく、障害への理解がある環境で働けるという大きなメリットがあります。給与水準や求人数の面で一般雇用と比較検討が必要です。
一般雇用(クローズ/オープン)
障害を会社に伝えず(クローズ)に働くか、伝えた上(オープン)で働くかを選択できます。
- クローズ: 職種の選択肢が広いが、配慮は得にくい。
- オープン: 配慮は得やすいが、求人が限られる場合がある。
特例子会社
企業が障害者雇用のために設立した子会社です。障害のある社員が多数在籍しており、設備や制度面でのサポートが手厚いのが特徴です。
就労継続支援(A型/B型)
すぐに一般企業で働くのが難しい方向けの福祉サービスです。
- 就労継続支援A型
事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら働きます。原則として最低賃金が保証されます。 - 就労継続支援B型
事業所と雇用契約を結ばず、比較的自分のペースで軽作業などの訓練を行います。作業量に応じた「工賃」が支払われます。
フリーランス・起業
組織のルールや人間関係に縛られず、自分の裁量で仕事を進められる働き方です。Webライター、デザイナー、プログラマーなど、スキルがあれば在宅で始められる仕事も多くあります。収入が不安定になるリスクもありますが、働き方の自由度は最も高い選択肢と言えるでしょう。
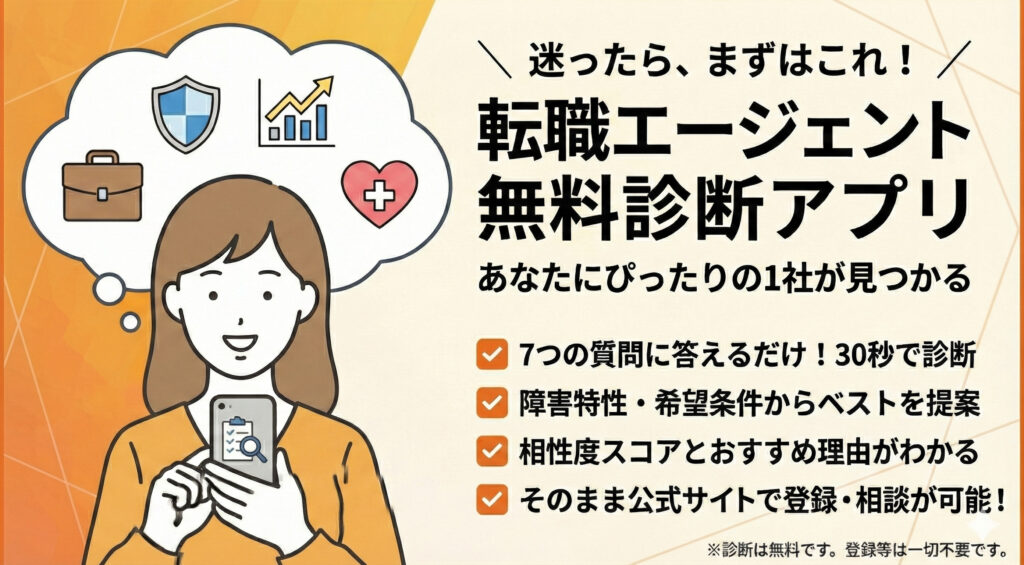
一人で抱え込まないで。相談できる専門機関・支援サービス

| 機関名 | 役割・特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 就労移行支援事業所 | 職業訓練、求職活動、就職後の定着支援まで、一貫してサポートしてくれる民間の事業所。 | スキルアップから就職までトータルで支援してほしい人。 |
| 地域障害者職業センター | 専門的な職業評価やリハビリテーションプログラムを提供する公的機関。 | 自分の適性や必要な配慮を客観的に評価してほしい人。 |
| 障害者就業・生活支援センター | 就業面と生活面の両方から一体的な相談・支援を行う。愛称は「なかぽつ」。 | 仕事だけでなく、生活全般の悩みも合わせて相談したい人。 |
| ハローワーク(専門援助部門) | 障害のある方向けの専門窓口があり、求人紹介や就職相談に乗ってくれる。 | 具体的に障害者雇用の求人を探したい人。 |
これらの機関は、相談だけであれば無料で利用できる場合がほとんどです。まずは話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなるはずです。
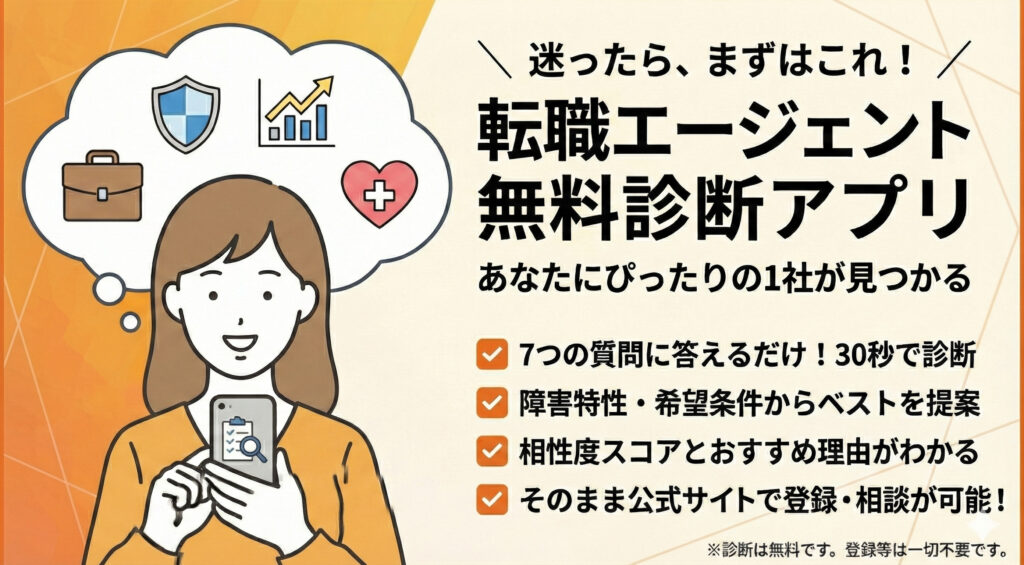
まとめ:自分に合った場所で、あなたらしく輝こう

「発達障害で仕事が続かない」という悩みは、決してあなた一人のものではありません。そして、それはあなたの能力や価値を決めるものでもありません。
大切なのは、自分の特性という「個性」を正しく理解し、その個性が輝ける場所を見つけることです。そのためには、時には環境を変える、つまり「転職」や「働き方を変える」という選択も、前向きで戦略的な一歩なのです。
この記事で紹介した対策や選択肢を参考に、ぜひあなたに合った働き方を探してみてください。一人で悩まず、家族や支援機関を頼りながら、焦らず、あなたのペースで進んでいきましょう。あなたの未来は、あなたが思っているよりもずっと明るく、可能性に満ちています。
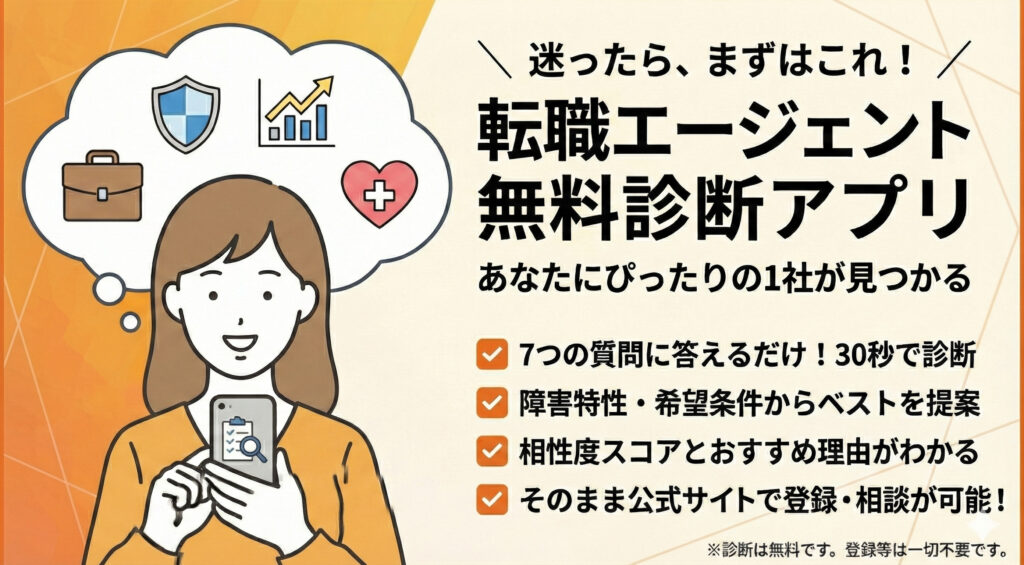
【免責事項】
本記事は、発達障害の特性により仕事の継続に困難を感じている方への情報提供を目的としています。医学的な診断や治療に代わるものではありません。心身の不調を感じる場合は、必ず医療機関にご相談ください。また、本記事に掲載されている制度やサービスに関する情報は、記事公開時点のものです。ご利用の際は、必ず各機関の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。










