「今の仕事、なんだか働きづらい…」
「自分の特性に合う職場がどこかにあるはずなのに…」
発達障害のある方にとって、転職はキャリアを切り拓く大きなチャンスであると同時に、多くの不安が伴うものでしょう。過去に転職を繰り返してしまい、自信を失いかけている方もいるかもしれません。
ご安心ください。現在の障害者雇用市場は、法律の後押しもあり、あなたを求める企業が増えている「売り手市場」です。しかし、ただ闇雲に転職活動をしても、再び同じ壁にぶつかってしまう可能性があります。
本当の転職成功とは、「内定を取ること」ではなく、「新しい職場で自分らしく、長く働き続けること」です。
この記事では、転職のノウハウだけでなく、内定の先にある「職場定着」までを見据えた、戦略的な転職活動の全てを、客観的なデータに基づいて徹底解説します。この記事を読めば、あなたの転職に関する不安が解消され、自信を持って次の一歩を踏み出せるようになるはずです。
記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。
読み間違いがありますが、ご容赦ください。
▼発達障害と転職:ミスマッチをなくし、自分らしく長く働くための戦略と支援策
発達障害を取り巻く転職市場のリアル【2025年最新】
まず、現在の転職市場があなたにとって追い風であることを知りましょう。客観的なデータから、市場の現状と、知っておくべき現実を解説します。

法定雇用率の上昇と「売り手市場」の背景
現在、障害者の採用市場は「売り手市場」と言われています。その最大の理由は、国が定める「法定雇用率」が段階的に引き上げられているからです。
企業は、全従業員のうち一定の割合で障害のある方を雇用することが法律で義務付けられています。この割合が、2024年4月には2.5%、2026年7月には2.7%へと引き上げられることが決まっています。
| 年 | 民間企業の法定雇用率 |
|---|---|
| ~2024年3月 | 2.3% |
| 2024年4月~ | 2.5% |
| 2026年7月~ | 2.7% |
このため、多くの企業が障害者雇用を重要な経営課題と捉え、採用に積極的になっています。実際に、厚生労働省のデータによると、民間企業で働く障害者の数は20年連続で過去最高を更新しており、市場は拡大し続けているのです。
理想と現実のギャップ:賃金・雇用形態の実態
市場が活況な一方で、知っておくべき課題もあります。平成30年度障害者雇用実態調査によると、発達障害のある方の雇用形態で最も多いのは「有期契約・非正規」で、平均賃金は月額約12.7万円です。これは、身体障害のある方の平均賃金21.5万円と比較すると、低い水準にあります。
この背景には、企業側の「会社内に適当な仕事があるか」という課題があります。企業が障害者雇用を進める際、既存の業務ではなく、新たに切り出した単純作業を任せることが多く、結果として賃金が低くなる傾向があるのです。
だからこそ、転職活動では給与額だけでなく、任される業務内容やキャリアアップの可能性をしっかりと見極めることが重要になります。
どんな仕事が多い?職種・業種・企業規模の傾向
発達障害のある方が最も多く従事している職種は「事務的職業」で、業種では「サービス業」「製造業」が続きます。
また、少し意外かもしれませんが、働く場所の約4人中3人が従業員数100人未満の事業所、つまり中小企業です。大手企業が障害者雇用の目的を「社会的責任」とする一方、中小企業は「既存社員の成長」や「イノベーションの創出」といった、より積極的な目的を掲げる傾向があります。
企業規模の大小だけで判断せず、その企業が障害者雇用にどのような価値を見出しているかに注目することが、良い職場と出会うためのヒントになります。
なぜ?発達障害のある人が転職を繰り返す根本原因
「次こそは長く働きたい」と誰もが願うはず。しかし、障害者雇用全体の離職データを見ると、短期離職の課題が浮き彫りになってきます。失敗の連鎖を断ち切るために、まずはその根本原因を理解しましょう。
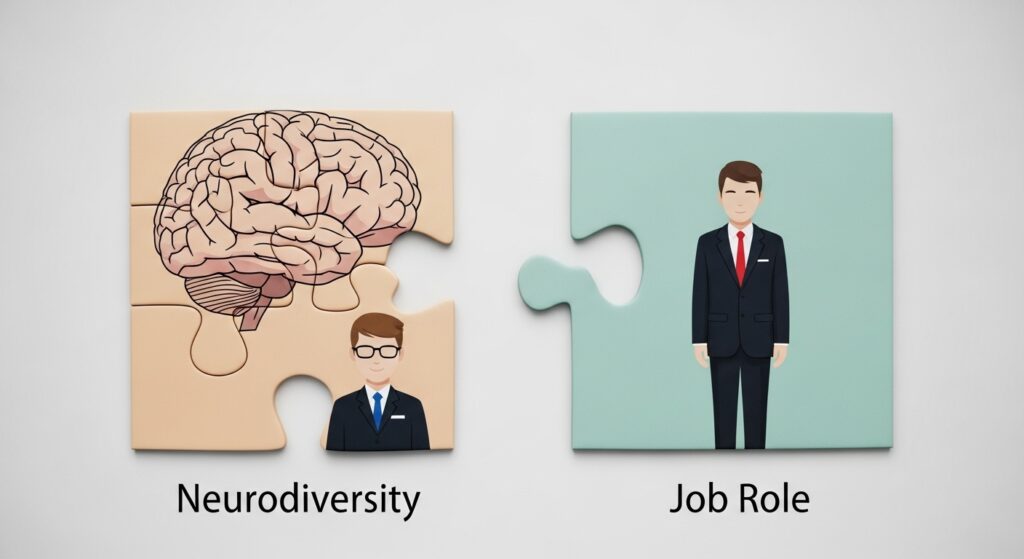
離職理由の多くは「特性と環境のミスマッチ」
離職の主な理由は「個人的な理由」とされていますが、その中身は「特性と職場環境のミスマッチ」「コミュニケーションの課題」「キャリア計画の困難さ」などです。
これは、企業側が採用時に「応募者の適性や能力を十分に把握できるか」を不安に思っていることの裏返しでもあります。つまり、あなたと企業、双方の間に「情報のギャップ」が存在することが、ミスマッチの根本原因なのです。
この悪循環を断ち切る鍵は、次の2つのステップにあります。
- 徹底的な自己理解
- オープンかクローズかの戦略的選択
成功の鍵は「オープン就労」か「クローズ就労」かの戦略的選択
転職活動において、最初に決断すべき最も重要な選択がこれです。
| 項目 | オープン就労(障害を開示) | クローズ就労(障害を非開示) |
|---|---|---|
| 概要 | 障害者雇用枠で応募。障害特性への配慮を求める。 | 一般雇用枠で応募。障害を伝えない。 |
| メリット | 合理的配慮が受けられる、定着率が高い、安心して働ける | 求人数や職種の選択肢が広い、給与水準が高い傾向 |
| デメリット | 求人数や職種が限られる、給与水準が低い傾向 | 必要な配慮を得られない、障害を隠す精神的負担、通院等も自己責任 |
| 1年後職場定着率 | 障害者求人:約87% 一般求人開示:約50% | 約31% |
注目すべきは、1年後の職場定着率の圧倒的な差です。障害者求人でのオープン就労の定着率は約87%と非常に高いのに対し、クローズ就労では約31%に留まります。
この差は、「合理的配慮」の有無が、キャリアの持続可能性を左右することを明確に示しています。クローズ就労のメリットは魅力的ですが、「長期的に安定して働き続けられるか?」という視点を持つことが極めて重要です。特別な理由がない限り、オープン就労を第一の選択肢として検討することを強く推奨します。
まずは「自分のトリセツ」作りから|自己理解を深める重要性
ミスマッチを防ぐには、まず自分自身が「自分の専門家」になる必要があります。以下の点を言語化し、「自分のトリセツ(取扱説明書)」を作成してみましょう。
- 得意なこと: (例:ルールが明確な作業、集中してデータ入力すること、情報収集)
- 苦手なこと: (例:曖昧な指示の理解、マルチタスク、電話対応、雑談)
- ストレスを感じる状況: (例:急な予定変更、騒がしい環境、一度に多くの指示をされる)
- 強みとして活かせる特性: (例:過集中を活かした高い精度、こだわりを活かした品質管理)
- 必要な配慮と自分でできる工夫: (例:指示はチャットでお願いしたい(配慮)、言われたことはメモに書き出す(工夫))
この「トリセツ」が、後の応募書類作成や面接で、あなたを助ける強力な武器になります。
【実践編】発達障害の特性を強みに変える転職活動の進め方
自己理解が深まったら、いよいよ実践です。あなたの特性を「弱み」ではなく「強み」として伝え、企業に安心感を与える方法を解説します。

書類選考で安心感を与える「応募書類」の書き方
企業が最も知りたいのは、「あなたの自己管理能力」と「長く働いてくれるか」です。応募書類では、単に苦手なことを書くのではなく、「課題+自己対処+希望する配慮」を3点セットで伝えることが極めて重要です。
悪い例
コミュニケーションが苦手です。
これでは、採用担当者は「どう対応すればいいのだろう…」と不安になってしまいます。
良い例
口頭での曖昧な指示を一度で理解することが苦手です。しかし、指示された内容は必ずメモを取り、図に描いて言語化することで正確に業務を遂行する工夫をしています。そのため、可能であればチャットやメールなど、テキストで指示をいただけますと大変助かります。
このように伝えることで、「自分の特性を客観的に理解し、すでに対策を打てている人材だ」というポジティブな印象を与え、企業側の不安を安心感に変えることができます。
苦手意識を克服する「面接」の準備と伝え方のコツ
面接では、曖昧な質問や非言語的なコミュニケーションが課題になりやすいかもしれません。しかし、適切な準備をすれば乗り越えられます。
最も効果的な対策は、支援機関を活用した「模擬面接」です。
模擬面接では、以下の点を重点的に練習しましょう。
- 結論から話す(PREP法)
Point(結論) → Reason(理由) → Example(具体例) → Point(結論)を意識する。 - 具体的なエピソードの準備
「あなたの強みは?」といった質問に対し、実体験に基づいたエピソードを話せるように準備しておく。 - 逆質問の用意
企業への関心を示すだけでなく、自身の働きやすさに関わる質問(例:「指示系統はどのようになっていますか?」「チームでのコミュニケーションはどのようなツールを使っていますか?」など)を準備する。
模擬面接を繰り返すことで、本番での認知的な負担を減らし、自信を持って受け答えができるようになります。
【完全比較】発達障害に強い転職支援サービスの種類と賢い選び方
一人で転職活動を進める必要は全くありません。あなたの状況に合わせて、専門家のサポートを最大限に活用しましょう。支援サービスは大きく3種類に分けられます。

支援サービスは主に3種類!それぞれの役割と対象者
あなたの「今」の状況に合わせて、最適なサービスを選ぶことが成功への近道です。
- ハローワーク(公的機関)
- 特徴
全国のどこにでもあり、障害者専門の窓口が設置されている。障害者手帳がなくても相談可能。求人紹介だけでなく、企業での実習を試せる「トライアル雇用」制度もある。 - 向いている人
どこに相談すればいいか分からない人、まず公的な機関で話を聞きたい人。
- 特徴
- 転職エージェント(民間)
- 特徴
障害者雇用に特化したプロが、キャリア相談から求人紹介、書類添削、面接対策まで一貫してサポート。非公開求人など、豊富な求人情報が魅力。 - 向いている人
ある程度のスキルや職歴があり、「今すぐ転職したい」と考えている人。
- 特徴
- 就労移行支援事業所(福祉サービス)
- 特徴
転職活動だけでなく、働くために必要なスキル(PC、コミュニケーション等)の習得、体調管理、自己理解などを体系的に学べる場所。就職後の「定着支援」までサポートしてくれるのが最大の強み。 - 向いている人
働くことにブランクがある、短期離職を繰り返している、スキルや体調面に不安がある人。
- 特徴
「転職エージェント」が転職という”点”を支援するのに対し、「就労移行支援」は安定して働き続けるという”線”で支援してくれる、とイメージすると分かりやすいでしょう。
【目的別】おすすめ転職エージェント・就労移行支援サービス比較表
数あるサービスの中から、特に実績のある主要なサービスを比較しました。
| サービス名 | 種類 | 特徴・強み | 注意点 |
|---|---|---|---|
| LITALICO仕事ナビ | エージェント | 業界最大級の求人数。幅広い職種や働き方(在宅など)に対応。 | 首都圏の求人が中心。希望条件によっては紹介が少ない場合も。 |
| dodaチャレンジ | エージェント | 大手企業の求人に強い。業界No.1の就職実績。手厚いサポートに定評。 | 質の高い求人が多いため、社内選考が厳しい傾向がある。 |
| atGP | エージェント | 91.4%という高い職場定着率が強み。IT・事務系の求人が豊富。 | 対応地域が限られる場合がある。 |
| 就労移行支援事業所 | 就労移行支援 | 基礎スキルの習得から定着支援まで包括的にサポート。自己理解プログラムが充実。 | 利用期間中は原則工賃が発生しない。すぐに就職したい人には不向き。 |
成功率を高めるサービスの併用戦略
一つのサービスに絞る必要はありません。複数のサービスを併用することで、それぞれの「良いとこ取り」をするのが賢い戦略です。
併用戦略の例
戦略①:大手と中小、両方の可能性を探りたい
- dodaチャレンジ(大手・非公開求人担当) + LITALICO仕事ナビ(多様な中小企業・在宅求人担当)
戦略②:まず生活リズムとスキルを整えてから、転職活動をしたい
- 就労移行支援事業所(基礎固め・自己理解担当) → 転職エージェント(求人紹介・選考対策担当)
戦略③:全てのサービスの基盤として
- ハローワーク(トライアル雇用・公的制度の相談担当)を常に併用する。
このように、各サービスの強みを理解し、自分の目的や段階に合わせて戦略的に組み合わせることで、転職成功の可能性を飛躍的に高めることができます。
内定はゴールじゃない!長く働き続けるための「職場定着」の秘訣
本当の成功は、入社後にあります。新しい環境で安心して力を発揮し、長く働き続けるための知識と準備について解説します。

「合理的配慮」とは?企業に求めるべきサポートと伝え方
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の従業員と平等に働けるように、企業側が提供する調整や変更のことです。これは法律で定められた企業の義務であり、遠慮なく求めるべき当然の権利です。
しかし、ただ「配慮してください」では、企業側も何をすれば良いか分かりません。ここでも、自己理解に基づいた具体的な要望を伝えることが重要です。面接の段階で、「私はこういう特性があり、このような工夫をしていますが、もし可能であれば、〇〇のような配慮をいただけると、よりパフォーマンスを発揮できます」と伝えることで、企業側も安心して受け入れ準備を進めることができます。
【具体例】特性別に伝える合理的配慮メニュー表
自身の特性に合わせて、どのような配慮を求めることができるか、具体的な「メニュー表」として参考にしてください。
| 課題・特性 | 合理的配慮の具体例 |
|---|---|
| コミュニケーション | ・口頭指示に加え、チャットなどテキストで記録を残してもらう。 ・「なるべく早く」などの曖昧な表現を避け、具体的な期限を提示してもらう。 |
| タスク・時間管理 | ・タスクの優先順位を明確にしてもらう。 ・一つの作業が終わってから、次の指示を出してもらう(シングルタスク化)。 |
| 作業環境・感覚過敏 | ・集中しやすいように、パーテーションで区切られた席を用意してもらう。 ・ノイズキャンセリングイヤホンの使用を許可してもらう。 |
| 体調管理・勤怠 | ・時差出勤やフレックスタイム制度の利用を認めてもらう。 ・定期的な通院のための休暇取得に理解を得る。 |
| 報告・連絡・相談 | ・報連相のタイミングや方法(例:毎朝10時にチャットで報告)を事前に決めておく。 ・困った時に誰に相談すれば良いか、相談窓口を明確にしてもらう。 |
このメニュー表を参考に、自分の「トリセツ」と合わせて、必要な配慮を整理しておきましょう。
入社後も使える!職場定着支援サービスと助成金制度の知識
入社後、もし困ったことがあっても一人で抱え込む必要はありません。
- ジョブコーチ支援
専門の支援員が職場を訪問し、あなたと企業の間に入って、業務の進め方やコミュニケーションの調整を行ってくれます。 - 障害者就業・生活支援センター
仕事だけでなく、生活面も含めた相談に乗ってくれる身近な支援機関です。
さらに、あなたを雇用することで、企業側は国から助成金を受け取れることを知っておくのも強力なカードになります。例えば、「特定求職者雇用開発助成金」などがあり、これは企業の採用コストや受け入れ体制整備の負担を軽減するものです。
面接時に、「私が長く働くことで、御社は助成金を活用して、より良い職場環境を整備することも可能です」といった視点を伝えられれば、あなたは単なる「支援される側」から、「企業と共により良い環境を創るパートナー」へと変わることができるのです。
まとめ:不安を自信に変え、あなたらしいキャリアを築こう
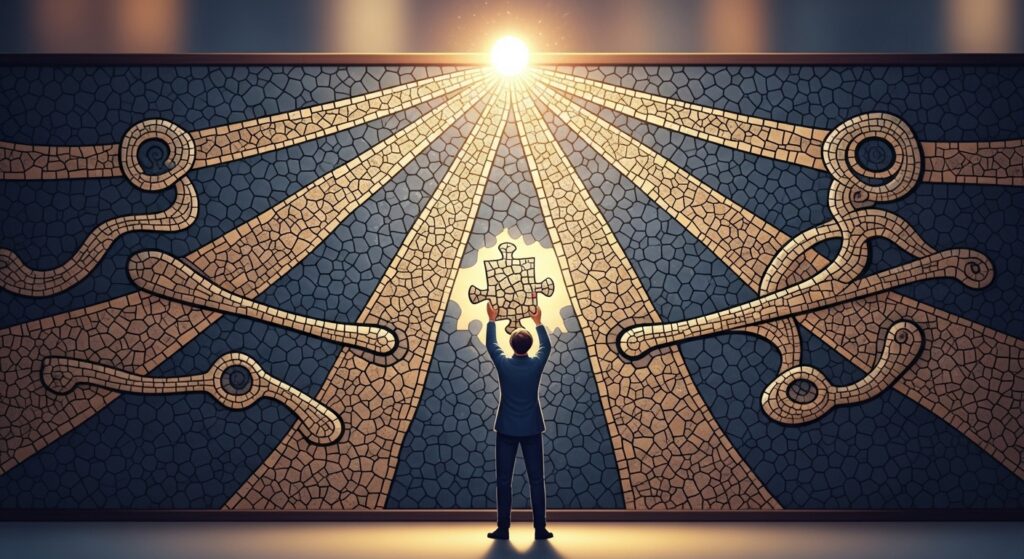
発達障害のある方の転職活動は、決して孤独な戦いではありません。
市場はあなたを求めており、あなたを支える多くの専門家や制度が存在します。
重要なのは、転職を「点」で捉えるのではなく、「職場定着」という未来まで続く「線」で捉えることです。
転職成功へのステップ
- まずは自己理解
自分の「トリセツ」を作り、強みと必要な配慮を言語化する。 - 戦略を選択する
長期的な安定を目指し、「オープン就労」を軸に考える。 - 専門家を頼る
自分の状況に合わせ、転職エージェントや就労移行支援を戦略的に併用する。 - 対等なパートナーとして
「合理的配慮」を具体的に伝え、企業側のメリットも提示する。
転職は、単に仕事を変えることではありません。あなたらしく輝ける場所を見つけ、より良い人生を築くための、積極的な一歩です。
このガイドが、あなたのその一歩を力強く後押しできることを心から願っています。
※本記事の情報は2025年8月時点のものです。法律や各サービス内容は変更される可能性があるため、最新情報は公式サイト等で必ずご確認ください。










