「なぜか職場に馴染めない」
「相手の気持ちが分からず、人間関係がうまくいかない」
「特定の音や光が耐えられないほど辛い」。
そんな生きづらさを感じていませんか?
もしかしたら、その悩みはあなたの性格や努力不足のせいではなく、ASD(自閉スペクトラム症)の特性に起因するものかもしれません。
この記事では、大人のASDの方が日常で経験しがちな「あるある」を、「仕事」「人間関係」「日常生活」の場面別に合計50選、当事者のリアルな声も交えながら徹底解説します。
単なる「あるある」の紹介で終わらせず、
- なぜそうなるのか?(特性との関連)
- 明日からできる具体的な対処法
- 周りの人ができるサポート
まで詳しく解説します。この記事を読めば、自分や周りの人への理解が深まり、生きづらさを解消するヒントがきっと見つかるはずです。
記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。
読み間違いがありますが、ご容赦ください。
▼大人のASDあるある50選!生きづらさの正体と自分らしい活かし方
▼時間がない方のために「解説動画」も作りました。
もしかして私も?大人のASD(自閉スペクトラム症)とは
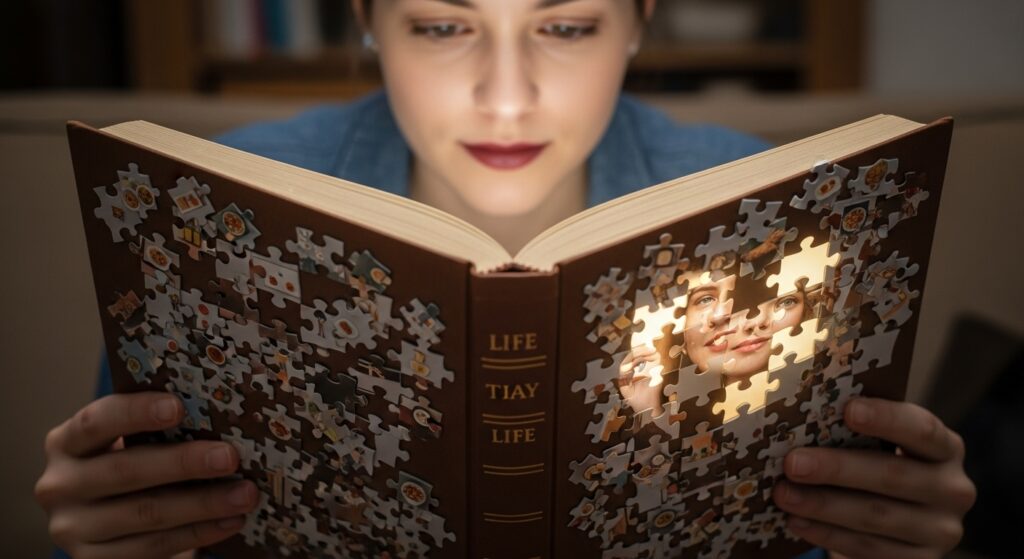
「ASD(自閉スペクトラム症)」は、生まれつきの脳機能の発達のかたよりによる発達障害の一つです。「自閉症」や「アスペルガー症候群」なども、現在ではこのASDに統合されています。「スペクトラム」という言葉が示す通り、特性の現れ方には個人差が非常に大きいのが特徴です。
ASDの3つの主な特性
ASDの特性は、大きく以下の3つに分けられます。これらの特性が様々な場面で「あるある」な困りごととして現れます。
| 特性 | 具体的な特徴 |
|---|---|
| 社会的コミュニケーションの困難 | ・相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取るのが苦手 ・言葉の裏にある意図(皮肉、冗談など)を理解するのが難しい ・抽象的な表現や曖昧な指示の理解が困難 |
| 対人関係の困難 | ・他人への興味が薄い、または関わり方が一方的になりがち ・その場の空気を読む、暗黙のルールを察することが苦手 ・友達付き合いなど、集団行動が苦痛に感じることがある |
| 限定された興味とこだわり行動 | ・興味の対象が非常に限定的で、一度興味を持つと深く没頭する ・特定の手順やルール、物の配置などに強いこだわりを持つ ・予期せぬ変更や予定外の出来事への対応が極端に苦手 |
なぜ大人になってから気づくのか?
子どもの頃は「少し変わった子」「マイペースな子」で済まされていた特性が、大人になり、就職や結婚などで複雑な対人関係やタスク管理が求められるようになると、困難として表面化しやすくなります。特に知的な遅れがない場合、本人の努力や工夫でなんとか乗り越えてきた結果、大人になるまで本人も周囲も気づかないケースが少なくありません。
「あるある」を知ることが自己理解の第一歩
これから紹介する「あるある」に心当たりがあるからといって、すぐにASDと断定できるわけではありません。しかし、多くの人が共感する「あるある」を知ることは、これまで漠然と感じてきた「生きづらさ」の正体を突き止め、自分を客観的に理解するための大きな一歩となります。
【仕事編】大人のASDあるある15選
職場は、ASDの特性が原因で困難を感じやすい場面の代表例です。コミュニケーションや業務の進め方で、多くの「あるある」が存在します。
コミュニケーション・対人関係のあるある

- 雑談が苦手で浮いてしまう
「天気の話」や「昨日のテレビの話」など、目的のない会話にどう参加していいか分からず、黙り込んでしまいがち。結果的に「付き合いが悪い」「何を考えているか分からない」と思われてしまうことがあります。 - 指示が曖昧だと動けない
「あれ、適当によろしく」「なるべく早めに」といった曖昧な指示では、何をどこまで、いつまでにやればいいのか分からずフリーズしてしまいます。「〇〇の資料を、△△の形式で、今日の15時までに」のように具体的な指示が必要です。 - 冗談や皮肉が通じない
言葉を文字通りに受け取るため、上司の「こんなこともできないのか(笑)」という冗談を真に受けて深く傷ついたり、本気で落ち込んだりします。 - 会議で発言するタイミングが分からない
議論の流れや場の空気を読んで、適切なタイミングで発言することが苦手です。考えがまとまった頃には話題が変わっていたり、逆に突然、文脈とずれた発言をしてしまったりします。 - 電話対応が極度にストレス
相手の表情が見えず、声の情報だけでやり取りしなければならない電話は非常に高い集中力を要します。いつかかってくるか分からない緊張感や、会話をしながらメモを取るマルチタスクも大きな負担です。
業務遂行・タスク管理のあるある

- マルチタスクができない
複数の業務を同時に、または並行して進めるのが極端に苦手です。一つの作業に集中している時に別の仕事を頼まれると、頭が真っ白になってパニックになることがあります。 - 過集中で休憩を忘れる
興味のある仕事や得意な作業に没頭すると、時間を忘れて驚異的な集中力を発揮します(過集中)。しかし、その分休憩や食事を忘れてしまい、気づいた時には疲れ果てて動けなくなることも。 - こだわりが強く、マイルールを曲げられない
「この手順でないとダメ」「資料のフォントはこれ」など、自分なりのやり方やルールに強いこだわりがあります。非効率だと分かっていても、なかなか変更できません。 - 優先順位をつけるのが苦手
すべてのタスクが同じ重要度に見えてしまい、何から手をつければ良いか分からなくなります。緊急性と重要度のマトリクスで判断することが難しい傾向があります。 - 報連相のタイミングや内容が分からない
「どこまで進んだら報告すべきか」「どの情報を共有すべきか」の判断が苦手です。良かれと思って細かく報告しすぎて「しつこい」と言われたり、逆に完璧になるまで報告せず「なぜ早く言わない」と叱られたりします。
職場環境のあるある

- オフィスの騒音や光が辛い
感覚過敏の特性により、他の人が気にならないようなキーボードの音、話し声、蛍光灯のちらつき、コピー機の作動音などが耐え難い苦痛に感じることがあります。 - 飲み会など非公式な集まりが苦痛
大勢の人がガヤガヤ話す居酒屋の環境や、目的の分からない雑談が中心の飲み会は、情報量が多すぎてエネルギーを大量に消耗します。 - 急な変更や予定外の業務にパニックになる
見通しを立てて行動することを好むため、突然のスケジュール変更や差し込みの業務に非常に弱い傾向があります。どう対応していいか分からず、思考が停止してしまいます。 - 評価と自己評価にズレがある
仕事の成果は出していても、コミュニケーション面でのマイナス評価を受け、正当に評価されていないと感じることがあります。逆に、自分では完璧にできたと思っていても、周りからは「融通が利かない」と見られていることも。 - 完璧主義で燃え尽きやすい
0か100かで考えてしまう傾向があり、常に100%を目指そうとします。適度に力を抜くことができず、エネルギー切れを起こして燃え尽きてしまう(バーンアウト)ことがあります。
【対策】職場で実践できる7つの工夫

| 悩み | 自分でできる対策 | 周囲ができるサポート |
|---|---|---|
| 曖昧な指示が苦手 | 指示は5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)で確認する癖をつける。チャットなどテキストで指示をもらう。 | 指示は具体的・明確に伝える。「〇〇を、△△の目的で、□□の手順で、××時までに」のように伝える。 |
| マルチタスクが苦手 | 1つのタスクが終わってから次に進む「シングルタスク」を意識する。タスクリストを作成し、上司に優先順位を確認する。 | 一度に複数の指示を出さない。急な差し込み業務は、今やっている作業との優先順位を明確に示す。 |
| 報連相が苦手 | 報告するタイミング(例:1日の終わり、タスクの完了時)や内容を上司と事前に決めておく。「報連相のテンプレート」を作る。 | 報告のタイミングを具体的に指示する。「この作業が終わったら声をかけてください」など。 |
| 感覚過敏 | ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓、ブルーライトカット眼鏡などを使う。パーテーションで区切られた席を希望する。 | 座席の位置を配慮する(出入り口から遠い、窓際など)。香りの強い柔軟剤などを控える。 |
| 雑談・飲み会が苦手 | 昼休みは一人で過ごす、飲み会は一次会だけで失礼するなど、自分のルールを決めておく。「耳が敏感で、騒がしい場所が苦手です」と正直に伝えるのも手。 | 無理に参加を強制しない。ランチミーティングなど、別の形の交流を提案する。 |
| 急な変更が苦手 | 変更の可能性がある場合は、事前に伝えてもらうようお願いする。「もしAがダメならBのパターンで」と複数案を想定しておく。 | 変更は可能な限り早く、理由と共にていねいに伝える。 |
| 完璧主義 | 「まずは60%の完成度で相談する」など、ハードルを下げるルールを作る。タイマーで作業時間を区切る。 | 「完璧でなくて大丈夫」「まずはドラフトで共有して」と声かけをする。 |
【人間関係・コミュニケーション編】大人のASDあるある10選
親しい友人や家族、パートナーとの間でも、ASDの特性からくるすれ違いや誤解が生じることがあります。
友人・知人とのこと

- 相手の気持ちを察するのが難しい
「顔には『大丈夫』と書いてあるけど、本当は怒っている」といった、表情や態度から相手の感情を推測するのが苦手です。「言わなくても分かるでしょ」が通用せず、関係がこじれる原因になります。 - 興味のない話だと相槌が打てない
自分の関心がない話題になると、どう反応していいか分からず、無表情になったり、話を聞いていないような態度を取ってしまったりします。悪気はないのですが、「失礼な人」だと思われがちです。 - 複数人での会話についていけない
あちこちに飛ぶ話題、同時多発的な会話、暗黙の了解など、情報処理が追いつかず、ただ黙ってその場にいるだけになってしまいます。 - 相手との距離感が分からず、馴れ馴れしいかよそよそしくなる
親しくなりたいと思うあまり、初対面でプライベートな質問をしすぎたり、逆に関わり方が分からず、何年も会っているのに敬語が抜けなかったりします。 - 約束を忘れたり、時間を守れなかったりする
興味のあること以外への注意が散漫になりがちで、口約束などを忘れてしまうことがあります。また、準備に時間がかかりすぎる、移動時間を見誤るなどで遅刻してしまうことも。
恋愛・パートナーとのこと

- 愛情表現が独特、または苦手
「好き」「愛してる」といった言葉での表現や、ハグなどの身体的接触が苦手な場合があります。愛情がないわけではなく、表現方法が分からない、または感覚的に受け付けないのです。 - パートナーにも「正しさ」を求めてしまう
物事を白黒はっきりさせたい、正しくありたいという気持ちが強く、パートナーの意見が「正しくない」と感じると、論理的に相手を言い負かそうとしてしまうことがあります。 - 一人の時間がないと無理
どれだけ好きな相手でも、四六時中一緒にいると感覚的な刺激や情報量が多すぎて疲弊してしまいます。一人になって思考を整理し、エネルギーを充電する時間が不可欠です。 - 記念日やイベント事に興味が薄い
誕生日やクリスマスなど、世間一般で大切にされるイベントの重要性が理解できず、関心が薄いことがあります。パートナーからは「思いやりがない」と受け取られてしまうことも。 - 感覚の違い(触覚など)でスキンシップが苦痛なことがある
触覚が過敏な場合、特定の触られ方を不快に感じたり、手をつなぐこと自体がストレスになったりすることがあります。
【対策】良好な人間関係を築くための5つのヒント

- 「言葉」で伝える・確認する
「察してほしい」をなくし、「〇〇してほしい」「今はこう感じている」と具体的に言葉で伝え合いましょう。「今、怒ってる?」と正直に聞くことも大切です。 - お互いの「トリセツ」を作る
「こういう時はそっとしておいてほしい」「騒がしい場所は苦手」など、自分の特性や苦手なことを事前に相手に伝えておきましょう。相手の「トリセツ」も聞くことで、無用な衝突を避けられます。 - スケジュールは共有・リマインドする
共有カレンダーアプリなどを使って、お互いの予定を可視化しましょう。大事な約束は前日にリマインドし合うルールにするのも有効です。 - 一人の時間を尊重する
「週に一度は別々に過ごす日を作る」など、お互いが意識的に一人の時間を確保できるようなルールを作りましょう。 - 「違い」を責めずに「工夫」を話し合う
特性からくるすれ違いは、どちらが悪いわけでもありません。「なぜ分かってくれないんだ」と責めるのではなく、「どうすればうまくいくか」という視点で、二人で解決策を探す姿勢が大切です。
【日常生活・プライベート編】大人のASDあるある15選
一人で過ごす時間や家庭内でも、ASDの特性は様々な形で現れます。感覚の偏りや、強いこだわりがその代表です。
感覚の偏りに関するあるある

- 特定の音・光・匂い・味・感触が耐えられない(感覚過敏)
救急車のサイレン、時計の秒針の音、スーパーの照明、他人の香水、特定の食材の食感など、多くの人が気にしない刺激が耐え難い苦痛となり、パニックや体調不良を引き起こします。 - 痛みや空腹に気づきにくい(感覚鈍麻)
ケガをしても痛みを感じにくかったり、空腹や喉の渇きに気づかず、倒れる寸前まで活動してしまったりします。 - 洋服のタグや素材が気になって仕方ない
首筋のタグがチクチクして集中できない、特定の化学繊維の肌触りがダメなど、衣類の素材や縫い目に強い不快感を覚えます。 - 偏食が激しい
食感や匂い、見た目に強いこだわりがあり、食べられるものが極端に少ないことがあります。「わがまま」と誤解されがちですが、本人にとっては安全なものを食べているという感覚です。 - 人混みが極端に苦手
繁華街や満員電車など、不特定多数の人が発する音、匂い、視線、動きといった情報が一気に入ってきて処理しきれず、ひどく疲弊します。
こだわり・習慣に関するあるある

- 決まった手順(ルーティン)でないと落ち着かない
朝起きてから家を出るまでの順番、通勤経路、仕事の進め方など、あらゆる行動がルーティン化しています。この手順が崩れると、強い不安を感じます。 - 物の配置に強いこだわりがある
本の並び順、机の上の物の配置などが1mmでもズレていると気になってしまい、直さずにはいられません。 - 好きなことにはとことん没頭し、寝食を忘れる
自分の興味がある分野(特定の学問、アニメ、ゲーム、収集など)に関しては、驚異的な知識と集中力を発揮し、何時間でも没頭できます。 - 収集癖がある
同じ種類のものを色違いで全部集めたり、特定のシリーズのグッズをコンプリートしたりするなど、コレクションに熱中します。 - 予期せぬ出来事への対応が苦手
「行きつけの店が閉まっていた」「電車が遅延した」といった予期せぬトラブルに、どう対応していいか分からず頭が真っ白になります。
生活全般のあるある

- 体調管理が苦手
感覚鈍麻から自分の体調の変化に気づきにくく、疲れを溜め込んで突然ダウンしてしまうことがあります。睡眠のリズムが崩れやすい人も多いです。 - 部屋が極端に散らかっているか、モデルルームのように片付いているかの両極端
どこから手をつけていいか分からずゴミ屋敷のようになるか、こだわりが強く完璧に片付いているかの両極端になりがちです。 - 金銭管理が苦手
衝動的に高額なものを買ってしまう、支出の管理ができずいつの間にかお金がなくなっている、などのお金のトラブルを抱えやすい傾向があります。 - 興味の幅が狭く、休日の過ごし方がワンパターン
新しいことに挑戦するのが苦手で、休日はいつも同じ場所に出かけたり、家で好きなことに没頭したりと、行動範囲が限定的になりがちです。 - 事実をストレートに言いすぎて相手を傷つけてしまう
思ったことをオブラートに包まず、事実をそのまま伝えてしまいます。嘘がつけない誠実さの裏返しでもありますが、相手を傷つける意図はなくても、結果的に人間関係を損なうことがあります。
【対策】ストレスを減らし、穏やかに暮らすための8つの工夫

- 感覚過敏対策グッズを活用する
ノイズキャンセリングイヤホン、サングラス、肌触りの良い素材の服など、自分に合ったアイテムで刺激を減らす。 - ルーティンを味方につける
決まった時間に食事や睡眠をとるなど、体調を整えるための「良いルーティン」を意識的に作る。 - アラームやリマインダーを活用する
「休憩する」「薬を飲む」「食事をとる」など、忘れがちな行動をスマートフォンのリマインダー機能で管理する。 - 「もしも」の時の代替案を用意しておく
「A店が閉まっていたらB店に行く」など、トラブルを想定して代替案をいくつか用意しておくとパニックを防げる。 - 片付けはエリアと時間を区切る
「今日は机の上だけ」「15分だけやる」など、小さなゴールを設定して取り組む。 - お金は目的別に封筒で分ける
家賃、食費、趣味など、目的別に予算を分けて管理すると使いすぎを防げる。家計簿アプリの活用も有効。 - 一人の時間を確保する
意識的に刺激の少ない環境で心と体を休ませる時間をスケジュールに組み込む。 - 「枕詞」を意識する
事実を伝える前に「個人的な意見なんだけど」「確認したいんだけど」といったクッション言葉(枕詞)を挟む練習をする。
女性のASDに特有の「あるある」とは?

ASDは男性に多いとされてきましたが、近年、女性のASDも注目されています。女性の場合、特性が異なった形で現れるため、見過ごされやすい傾向があります。
- 「擬態(カモフラージュ)」で特性が隠れやすい
周囲に合わせようと、必死に「普通」を演じる(擬態する)のが得意な人が多いです。その場の会話に合わせて笑ったり、流行のファッションを取り入れたりして障害がないように振る舞うため、周りから気づかれにくい一方、本人は常に無理をしていて、家では疲れ果ててぐったりしています。 - 共感疲れ・感情の波に悩まされやすい
相手の感情を読み取るのは苦手でも、感受性が強く、相手のネガティブな感情(怒り、悲しみなど)に強く影響を受けてしまうことがあります(共感疲労)。また、ホルモンバランスの影響もあり、感情の起伏が激しくなることがあります。 - ライフステージの変化(妊娠・出産・育児)で困難が表面化しやすい
育児は、子どもの予測不能な行動や、感覚的な要求(泣き声、抱っこなど)、ママ友付き合いなど、ASDの人が苦手とする要素の連続です。これまで擬態で乗り切ってきた人も、育児をきっかけに限界を感じ、特性が表面化することがあります。
「あるある」に疲れたあなたへ。専門機関への相談という選択肢

多くの「あるある」に心当たりがあり、日常生活に支障が出ているなら、一人で抱え込まずに専門機関に相談することも考えてみましょう。
- どこに相談すれば良いか分からない
相談先には、「発達障害者支援センター」「精神科・心療内科」「カウンセリングルーム」などがあります。発達障害者支援センターは、診断の有無にかかわらず相談でき、地域の専門機関を紹介してくれます。まずはここから相談してみるのが良いでしょう。 - 診断を受けるのが怖い
診断を受けることにはメリットとデメリットがあります。- メリット
生きづらさの原因が分かり安心する、自分に合った対処法が分かる、障害者手帳の取得により福祉サービスや就労支援を受けられる場合があります、など。 - デメリット
「障害者」というレッテルを貼られることへの抵抗感、診断名によっては、一部の生命保険や医療保険への加入に影響が出ることがあります、など。
診断を受けるかどうかは、専門家と相談しながら慎重に決めることが大切です。
- メリット
- 周りの人にどう説明すればいいか分からない
家族や職場に伝える際は、単に「ASDです」と告げるだけでなく、「こういう特性があって、〇〇が苦手です。だから△△のように配慮してもらえると助かります」と、具体的な特性と必要な配慮をセットで伝えることが重要です。 - 支援制度があることを知らない
障害者手帳を取得すると、就労移行支援、自立訓練、障害者雇用枠での就職、税金の優遇措置など、様々な支援を受けることができます。※最新の情報やお住まいの自治体の制度については、各窓口にご確認ください。 - 二次障害を発症してしまう
周囲の無理解や失敗体験が続くことで、自己肯定感が低下し、うつ病や不安障害、適応障害などの二次障害を引き起こすことがあります。そうなる前に、専門機関に繋がることが非常に重要です。 - グレーゾーンでどこにも相談できないと感じる
診断基準は満たさないものの、ASDの傾向があって生きづらさを感じている「グレーゾーン」の人も多くいます。グレーゾーンであっても、カウンセリングや、発達障害者支援センター、当事者会などで相談に乗ってもらうことは可能です。 - 自分の「強み」に気づいていない
苦手なことが多い一方で、ASDの人は「特定の分野への集中力と探究心」「論理的思考力」「誠実で嘘がつけない」「独自の視点や発想力」といった素晴らしい強みを持っていることが多くあります。その強みを活かせる環境を見つけることが、自分らしく生きる鍵となります。
まとめ:特性を理解し、自分らしい生き方を見つけよう

大人のASD「あるある」、あなたにはいくつ当てはまったでしょうか。
多くの「あるある」は、社会に適応しようと頑張っているからこそ生じる悩みです。決してあなたの努力が足りないわけではありません。もちろん、ここで紹介した「あるある」が全ての人に当てはまるわけではありません。ASDの特性はまさに「スペクトラム(連続体)」であり、一人ひとり現れ方は異なります。
大切なのは、自分の特性を正しく理解し、「苦手なこと」には工夫や配慮で対処し、「得意なこと」を最大限に活かすことです。
この記事で紹介した対処法を参考に、まずは一つ、自分にできそうなことから試してみてください。そして、もし一人で抱えるのが辛いと感じたら、勇気を出して専門機関のドアを叩いてみてください。
あなたの「生きづらさ」が少しでも軽くなり、あなたらしい人生を歩むための一助となれば幸いです。
記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医
参考文献:
- 厚生労働省 「発達障害の理解 ~ メンタルヘルスに配慮すべき人への支援 ~」
- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5).









