「もしかして、あの同僚は発達障害…?でも本人に自覚がない…」そんな悩みを抱えていませんか?
コミュニケーションがうまくいかない、ミスが多くて仕事が進まない。あなたが一人で抱え込み、疲弊してしまう前に、できることがあります。
この記事では、大人の発達障害の特性から、明日から実践できる具体的な接し方、そして何より大切な「あなた自身を守る方法」まで、専門的な知見を交えながら網羅的に解説します。
もう一人で悩まないでください。この記事を読めば、きっと心が軽くなり、状況を改善する一歩を踏み出せるはずです。
▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。
もしかして…?職場で見られる大人の発達障害の特性(本人に自覚がないケース)
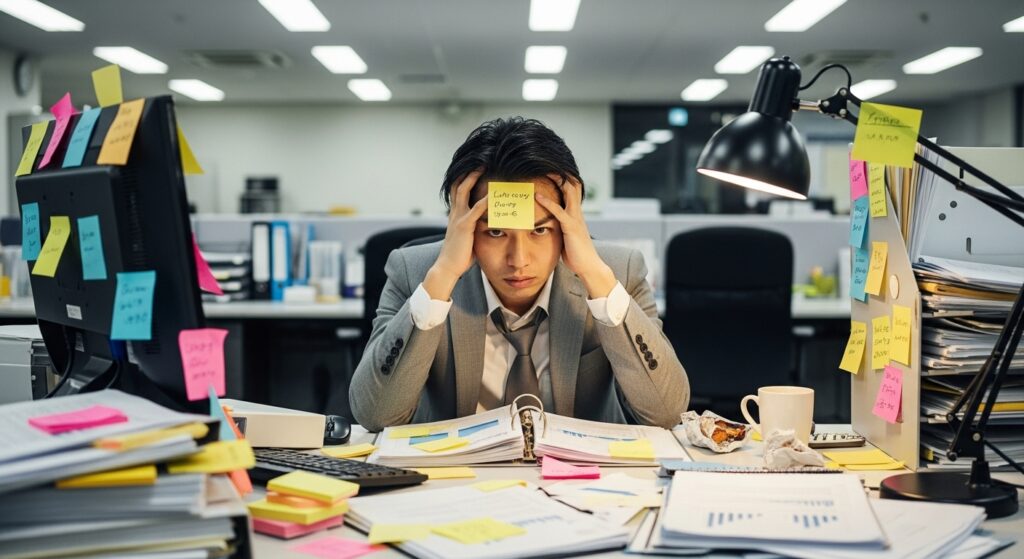
同僚の言動に悩んだとき、背景にあるかもしれない「特性」について知ることは、適切な対応を考える第一歩です。近年、大人の発達障害への理解が広まりつつありますが、これは決して他人事ではありません。潜在的なケースを含めると、私たちの職場にそうした特性を持つ人がいるのはごく自然なことです。
ただし、以下の内容はあくまで傾向であり、医学的な診断ではないことを心に留めておいてください。
ASD(自閉スペクトラム症)の傾向が強い同僚の特徴
対人関係やコミュニケーションに特有の困難さを抱えやすい傾向があります。
1. 場の空気が読めない・暗黙のルールが苦手
「会議が長引いているから、そろそろまとめよう」といった暗黙の了解や、その場の雰囲気を察することが苦手な場合があります。そのため、悪気なく不適切なタイミングで発言してしまうことがあります。
2. こだわりが強く、急な変更やマルチタスクに対応できない
一度決めた手順やルール通りに進めることを得意としますが、予期せぬスケジュールの変更や、複数の業務を同時に進めるマルチタスクには強いストレスを感じ、混乱してしまうことがあります。
3. 曖昧な指示の理解が難しく、言葉を文字通りに受け取る
「これ、いい感じにまとめておいて」といった抽象的な指示を理解するのが困難です。「いい感じ」が何を指すのか分からず、作業が止まってしまうことがあります。また、皮肉や冗談が通じにくい場合もあります。
ADHD(注意欠如多動症)の傾向が強い同僚の特徴
「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性が見られることがあります。
1. ケアレスミスや忘れ物が多い(不注意)
書類の誤字脱字が多い、重要な会議の日時を忘れる、物の置き忘れが多いなど、注意を持続させることが苦手なために起こるミスが目立ちます。
2. じっとしていられず、仕事中に離席しがち(多動性)
デスクワーク中に貧乏ゆすりをしたり、ペンを回し続けたり、目的もなく歩き回ったりすることがあります。本人は無意識であることが多いです。
3. 思いつきで発言・行動してしまう(衝動性)
相手が話している最中に、自分の考えを遮って話し始めたり、深く考えずに重要な契約を進めようとしたりするなど、結果を予測する前に行動してしまう傾向があります。
※注意点:素人判断は禁物です
これらの特性は誰にでも多少なりとも当てはまる可能性があります。また、複数の特性を併せ持っている場合も少なくありません。「発達障害だ」と決めつけることは絶対に避けてください。あくまで、「そうした特性があるのかもしれない」という視点を持ち、関わり方を工夫するためのヒントとして捉えましょう。
【明日から実践】自覚のない発達障害の同僚への具体的な接し方7選

相手を変えることはできませんが、こちらの関わり方を少し工夫するだけで、状況が大きく改善する可能性があります。ここでは、明日からすぐに使える7つの具体的な方法をご紹介します。
1. 「具体的・肯定的」な指示を徹底する【言い換えフレーズ集】
曖昧な表現は混乱の元です。誰が聞いても同じように解釈できる「5W1H」を意識した、具体的で肯定的な言葉で伝えましょう。
| やってしまいがちなNG指示 | おすすめのOK指示(言い換え例) |
|---|---|
| 「なるべく早くお願い」 | 「明日の15時までにお願いします」 |
| 「臨機応変に対応して」 | 「もしAパターンがダメなら、Bパターンで進めてください」 |
| 「もっと頑張って」 | 「まずは資料のP.5にあるグラフ作成から始めましょう」 |
| 「なんでミスしたの?」 | 「次はミスを防ぐために、ダブルチェックのリストを一緒に作ろうか」 |
| 「普通はこうするでしょ」 | 「この業務は、この手順書通りに進めるのがルールなんだ」 |
2. 複数の指示を一度に出さない(シングルタスクの原則)
「AとBをやって、終わったらCもお願い」と一度に伝えると、相手は混乱してしまいます。一つの作業が終わってから、次の指示を出すように心がけましょう。タスクリストを共有するのも有効です。
3. 口頭だけでなく、テキストや図で補足する
口頭での指示は、記憶から抜け落ちてしまう可能性があります。ビジネスチャットやメールで内容をテキストとして残したり、複雑な手順は図やフローチャートで示したりすると、認識のズレを防げます。
4. 感情的ではなく、I(アイ)メッセージで事実を伝える
問題が起きた際に「どうして(You)いつもこうなの?」と相手を主語にして責めるのではなく、「私は(I)こうしてくれると助かる」と自分を主語にして伝えましょう。客観的な事実と、自分の気持ちや要望をセットで伝えることで、相手も受け入れやすくなります。
5. 良い点を見つけて具体的に褒める(ポジティブなフィードバック)
誰でも得意なこと、苦手なことがあります。できたことや、その人の強みに目を向けて、「〇〇さんの作る資料は、データが正確でいつも助かります」のように具体的に褒めることで、本人の自己肯定感が高まり、強みを伸ばすきっかけになります。
6. 休憩や業務量の調整をそれとなく促す
集中しすぎて過集中になっていたり、逆に疲れが見えたりするときは、「少し休憩したらどう?」「このタスク、量が多いから手伝おうか?」と声をかけることで、本人が自分の状態に気づくきっかけを作れます。
7. 特性を「強み」と捉え、得意な業務を任せる
例えば、こだわりが強い特性は、緻密なデータチェックや品質管理といった業務で「強み」になります。興味のある分野への集中力が高いなら、専門的なリサーチを任せるのも良いでしょう。適材適所で業務を割り振ることで、チーム全体の生産性が向上します。
関係悪化を招く!絶対にやってはいけないNG対応とは?

良かれと思って取った行動が、かえって相手を傷つけ、関係を悪化させてしまうこともあります。以下の対応は避けましょう。
1. 人前で叱責したり、欠点を指摘したりする
プライドを深く傷つけ、強い拒絶反応を示す原因になります。何かを伝える際は、必ず1対1になれる会議室など、人目につかない場所を選びましょう。
2. 「普通は」「常識的に」といった曖昧な言葉で責める
「普通」や「常識」の尺度は人それぞれです。相手にとってはなぜ責められているのか理解できず、ただただ混乱し、自信を失うだけです。
3. 嫌味や皮肉を言ったり、無視したりする
言葉の裏の意味を理解するのが苦手な場合、嫌味や皮肉は全く通じないか、文字通りに受け取って深く傷つく可能性があります。無視は関係を断絶させる最悪の対応です。
4. 本人に「発達障害じゃない?」と直接指摘する
医師でもない限り、他人の障害を診断・断定することはできません。このような指摘は職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があり、相手に深い心の傷を負わせるだけでなく、あなた自身の立場を危うくします。絶対にやめましょう。
もう限界…一人で抱え込まないで。あなた自身を守るためのメンタルケア

同僚への対応に悩み、ストレスが溜まると、あなた自身が心身の不調をきたしてしまうかもしれません。そうなる前に、自分を守るための行動を取りましょう。
1. 自分のせいだと責めない(カサンドラ症候群について)
「自分の伝え方が悪いのかも」「私が我慢すれば…」と自分を責めないでください。コミュニケーションがうまくいかないのは、特性のすれ違いが原因かもしれません。身近な人に悩みを理解してもらえず、孤立感や抑うつ状態に陥ることを指す「カサンドラ症候群」という状態もあります。
2. 物理的・心理的な距離を取る
可能であれば、一時的に席を離れたり、関わる業務を減らしたりして物理的な距離を取りましょう。また、「これは私の問題ではなく、会社・チームの課題だ」と捉え、心理的に境界線を引くことも大切です。
3. 客観的な事実を記録する(行動記録シートのすすめ)
感情的にならず、冷静に状況を把握するために「いつ、どこで、何があったか」「それによって業務にどんな影響が出たか」を客観的に記録しましょう。これは、後に上司へ相談する際の重要な資料にもなります。
| 日時 | 場所 | 出来事(客観的な事実) | 業務への影響 |
|---|---|---|---|
| 8/27 14:00 | 執務室 | Aさんに口頭で依頼した資料作成の締切(本日17時)を忘れられていた。 | チーム定例会での報告に間に合わず、会議が30分延長した。 |
| 8/28 11:00 | 会議室 | B社との打ち合わせ中、先方の話を遮って自分の意見を話し始めた。 | B社の担当者が不快感を示し、場の空気が悪くなった。 |
4. 信頼できる人に話を聞いてもらう
一人で抱え込まず、信頼できる同僚や上司、社外の友人や家族に話を聞いてもらいましょう。誰かに話すだけで、気持ちが整理され、心が軽くなることがあります。
状況が改善しない…会社(上司・人事)に相談する際の注意点と伝え方

個人の努力だけでは改善が難しい場合は、会社組織として対応してもらう必要があります。感情的に訴えるのではなく、準備を整えて冷静に相談することが成功の鍵です。
相談する前に準備すべきこと
1. 感情論を排し、客観的な事実(記録)を整理する
「〇〇さんのせいで、いつも大変なんです!」ではなく、先ほど紹介した行動記録シートなどを用いて、「いつ、何があり、業務にどのような支障が出たか」という客観的な事実を時系列でまとめます。
2. 業務への具体的な支障をリストアップする
「コミュニケーションが取りづらい」といった主観的な問題ではなく、「〇〇という言動により、プロジェクトが〇日遅延した」「月平均〇時間の残業が発生している」など、具体的な損失や影響を数値で示せるとより説得力が増します。
3. 改善のための「提案」を用意する
ただ不満を伝えるだけでなく、「業務の指示は必ずチャットで行うルールにしてほしい」「〇〇さんの業務内容を、強みが活かせる〇〇に変更してはどうか」といった、前向きな改善案を用意していくと、問題解決能力の高さも示すことができます。
誰に、どのように相談すべきか?
まずは直属の上司に相談するのが基本
チームのマネジメントは上司の責任です。まずは直属の上司に「チームの業務効率化について、ご相談したいことがあります」と時間を取ってもらい、準備した資料をもとに冷静に伝えましょう。
上司が機能しない場合は人事部や相談窓口へ
上司が取り合ってくれない、あるいは上司自身が問題の原因である場合は、人事部や社内に設置されているハラスメント相談窓口、コンプライアンス窓口などに相談しましょう。
会社への伝え方の例文
「〇〇さん(上司)お時間いただきありがとうございます。本日は、チームの生産性向上についてご相談があり、お時間をいただきました。
実は、同僚の△△さんの件で、業務上いくつかの支障が出ております。これは決して△△さん個人を非難したいわけではなく、チームとしてより円滑に業務を進めるためのご相談です。
こちらが、ここ1ヶ月の具体的な事象と業務への影響をまとめたものです。(記録を見せる)
この状況を改善するため、例えば、チーム内の指示系統をチャットに一本化する、△△さんの得意なデータ分析業務の割合を増やす、といった対策が考えられるのではないかと思っております。
〇〇さん(上司)のお考えもお聞かせいただけますでしょうか。」
専門機関にも相談できます|社内外の相談窓口一覧

社内での解決が難しい場合や、より専門的なアドバイスが欲しい場合は、外部の機関を頼ることもできます。
社内の相談窓口
- 産業医・保健師(常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務)
従業員の心身の健康をサポートする専門家です。守秘義務があるため、安心して相談できます。 - コンプライアンス・ハラスメント相談窓口
多くの企業に設置されている相談窓口です。匿名での相談を受け付けている場合もあります。
社外の相談窓口
- 発達障害者支援センター
各都道府県・指定都市に設置されています。本人だけでなく、家族や企業からの相談にも応じています。 - 総合労働相談コーナー
各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内に設置されており、職場のトラブルに関するあらゆる相談を専門の相談員が無料で受け付けています。 - 地域の就労支援機関
就労移行支援事業所など、障害のある方の就労をサポートする機関です。企業へのアドバイス(コンサルティング)を行っている場合もあります。
まとめ:一人で抱え込まず、適切なステップで働きやすい環境を

最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。
- 発達障害の特性を理解する
ASDやADHDの特性を知ることで、同僚の言動の背景を推測し、冷静に対応するヒントになる。ただし、素人判断は禁物。 - 具体的な接し方を試す
「指示は具体的に」「テキストも活用」「感情的にならない」など、明日からできる工夫で関係が改善することがある。 - 自分自身のメンタルケアを最優先に
一人で抱え込まず、自分を責めないこと。客観的な記録をつけ、物理的・心理的な距離を取ることも大切。 - 冷静に、戦略的に会社に相談する
改善が見られない場合は、客観的な事実と改善案を用意して、上司や人事に相談する。 - 外部の専門機関も活用する
社内での解決が難しい場合は、発達障害者支援センターなどの専門機関を頼る。
発達障害の同僚への対応は、あなた一人で解決できる問題ではありません。
まずはこの記事で紹介した適切な接し方を試し、あなた自身の心を守ることを最優先にしてください。そして、必要であれば勇気を出して周囲や専門家の力を借りましょう。
この記事が、あなたの悩みを少しでも軽くし、あなたとチームにとってより良い職場環境を築くための一助となれば幸いです。
※注意事項:
本記事は情報提供を目的としており、自己診断を促すものではありません。気になる症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医










