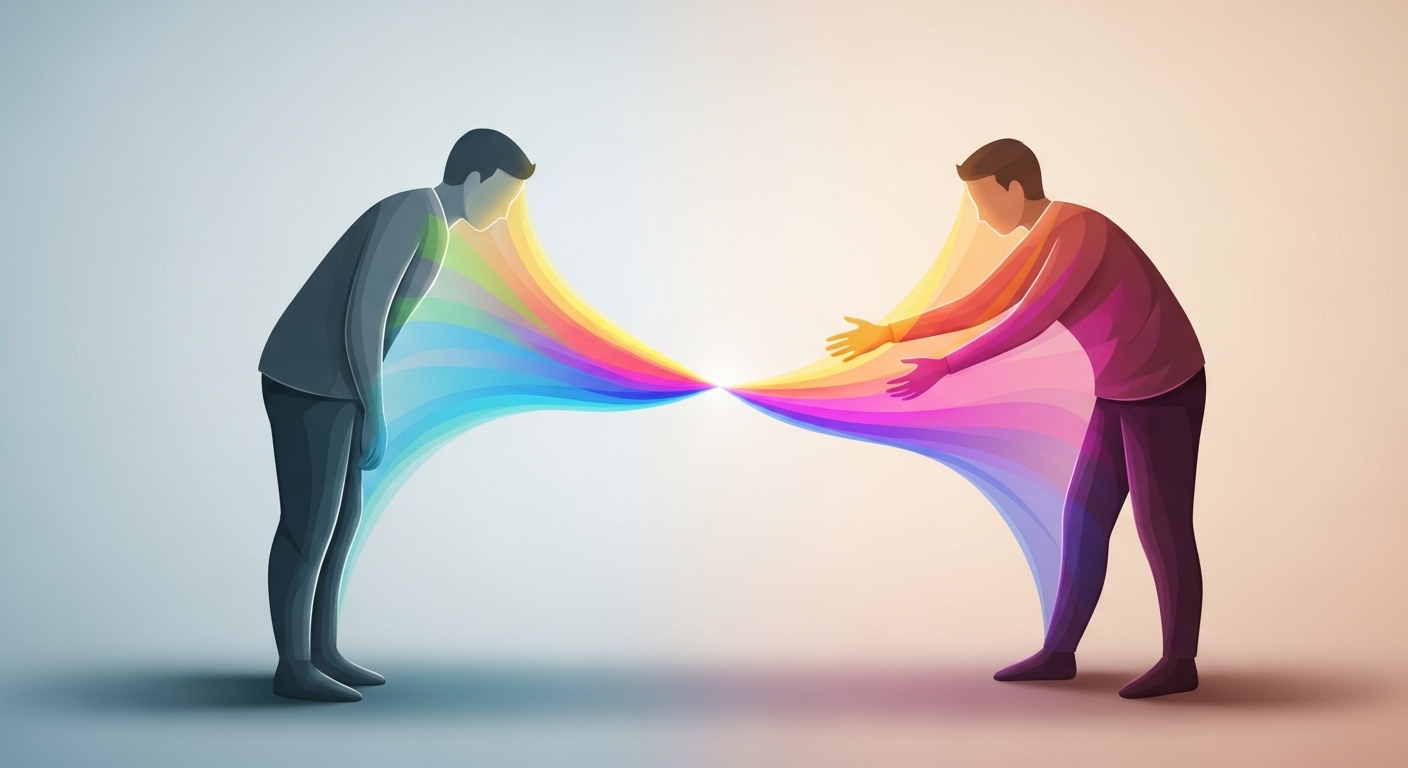「なぜか人との会話が弾まない」「いつも一方的に話してしまう」「相手の言っていることの意図が掴めず、固まってしまう」。
そんな悩みを抱え、人間関係や仕事でつまずきを感じていませんか? もしかしたら、そのコミュニケーションの難しさは、あなたの性格や努力不足の問題ではなく、大人の発達障害の特性が関係しているのかもしれません。
この記事では、発達障害の専門的な知見に基づきながら、会話のキャッチボールが苦手になる原因を分かりやすく解説します。特に、対人関係やコミュニケーションの困難さが特徴的な自閉スペクトラム症(ASD)を中心に、当事者の方が明日からすぐに試せる具体的なトレーニング方法から、家族や同僚など周りの人ができるサポートまで、網羅的にご紹介します。
この記事を読めば、悩みの正体が分かり、自分らしいコミュニケーションを築くための第一歩を踏み出せるはずです。
▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。
もしかして…?会話の苦手さは大人の発達障害が関係しているかも

まずは、ご自身の状況を客観的に把握するために、会話で感じがちな「あるある」をチェックしてみましょう。
こんな「あるある」、ありませんか?会話の悩みチェックリスト
一つでも深く頷くものがあれば、この記事がお役に立てるかもしれません。
| チェック項目 | 具体的な状況例 |
|---|---|
| □ 一方的に話してしまう | 相手が話す隙を与えず、自分の興味のあることを延々と話してしまう。 |
| □ 会話の始め方が分からない | 雑談の輪にどう入ればいいか分からず、タイミングを逃してしまう。 |
| □ 話が急に飛ぶ・脱線する | 会話の途中で思いついた別の話題を、脈絡なく話し始めてしまう。 |
| □ 相槌が不自然になる | 「へぇ」「そうなんだ」しか言えず、会話がそこで終わってしまう。 |
| □ 冗談や皮肉が通じない | 相手の言った言葉をそのままの意味で受け取ってしまい、真に受けてしまう。 |
| □ 表情や空気を読むのが苦手 | 相手が退屈そうなのに気づかず、話を続けてしまう。 |
| □ 質問の意図が分からない | 「最近どう?」のような曖昧な質問に、何をどこまで答えるべきか悩んでしまう。 |
| □ 沈黙が怖くて焦ってしまう | 少しでも間が空くと不安になり、何か話さなきゃと焦って空回りする。 |
これらの悩みは、大人の発達障害、特に自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)の特性と深く関わっている場合があります。
なぜ?発達障害(特にASD)で会話のキャッチボールが苦手になる3つの理由
自閉スペクトラム症(ASD)には、対人関係やコミュニケーションにおける特有のパターンがあります。それが会話のキャッチボールを難しくさせる主な原因と考えられています。
1. 言葉の裏が読めない・文字通りに受け取ってしまう
ASDの特性の一つに、言葉を額面通りに受け取る傾向があります。「(会議室が暑い状況で)ちょっと考えます」と言われたら、「本当に検討してくれるんだ」と解釈し、「窓を開けましょうか?」といった提案が思い浮かばない、といったケースです。皮肉やお世辞、比喩表現の理解も苦手なため、会話が噛み合わない原因になります。
2. 興味の範囲が限定的で、自分の話が多くなる
自分の好きなことや関心のあることに対しては、非常に深く探求し、豊富な知識を持っています。これは素晴らしい長所ですが、コミュニケーションにおいては、相手の興味関心をよそに自分の話に夢中になってしまうことがあります。相手にとっては「自分の話ばかりする人」と映ってしまうかもしれません。
3. 複数の情報を同時に処理するのが苦手(聴覚情報処理障害など)
相手の「言葉」だけでなく、「表情」「声のトーン」「身振り」など、会話中は様々な情報が飛び交っています。ASDのある人の中には、これらの情報を同時に処理するのが苦手な方がいます。また、周りの雑音の中から必要な音声情報だけを聞き分けるのが難しい「聴覚情報処理障害(APD)」を併せ持つ場合もあり、「話を聞いていない」と誤解される原因にもなります。
ADHD(不注意・多動性)の特性と会話の「ずれ」
ADHDの「不注意」や「衝動性」といった特性も、会話に影響を与えます。
- 不注意: 相手の話の途中で集中力が切れ、別のことを考えてしまう。
- 衝動性: 相手の話を最後まで聞かずに、思いついたことを遮って話してしまう。
これらの特性が、話の脱線や、会話の流れを止めてしまう原因となることがあります。
【当事者向け】明日から試せる!会話の苦手さを克服する7つの実践トレーニング

特性は変えられなくても、工夫次第でコミュニケーションを円滑にすることは可能です。ここでは、スポーツの練習のように、段階的に取り組める具体的なトレーニング方法をご紹介します。
Step 1《準備編》:不安を減らすための事前準備
試合の前に作戦を立てるように、会話にも準備が大切です。行き当たりばったりで臨むのではなく、事前の準備で不安を大きく減らせます。
① 目的を一つに絞る「今日のゴール設定」
「楽しく雑談する」といった曖昧な目標は、かえってプレッシャーになります。「〇〇さんに、週末の予定を聞いてみる」「会議で一回は質問する」など、達成可能で具体的なゴールを一つだけ設定しましょう。クリアできれば成功体験となり、自信につながります。
② 話題を予測する「会話の地図」作り
相手や場面に合わせて、事前に話す内容をいくつか用意しておきます。天気、ニュース、相手の趣味など、当たり障りのない「安全な話題」をいくつかストックしておくと、沈黙が怖くなくなります。
| 場面 | 準備する話題の例 |
|---|---|
| 職場の同僚と | ・進行中のプロジェクトの進捗 ・最近導入されたツールの使用感 ・会社の近くの新しいランチのお店 |
| 友人との食事 | ・最近見た映画やドラマの感想 ・次の休みの日の予定 ・共通の趣味に関する新しい情報 |
| あまり知らない人 | ・今日の天気や気候について ・出身地や住んでいる場所について ・好きな食べ物や季節について |
Step 2《実践編》:会話をスムーズに進める具体的な型(テンプレート)
会話は、ある程度の「型」を覚えることで、格段にスムーズになります。まずはテンプレートを真似ることから始めてみましょう。
③ 相槌は「さしすせそ」+表情で
単調な相槌は、相手に「話を聞いていない」という印象を与えがちです。まずはバリエーションを増やすことを意識しましょう。
- さ: さすがですね!
- し: 知りませんでした!
- す: すごいですね!
- せ: センスいいですね!
- そ: そうなんですね!/それは大変でしたね。
言葉だけでなく、少しだけ頷いたり、眉を上げたりと、表情をセットで使うのがポイントです。
④ 質問は「5W1H」で具体的に返す
相手の話を聞いたら、その中から「いつ(When)」「どこで(Where)」「だれが(Who)」「なにを(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」を使って質問を返してみましょう。これにより、相手は「自分の話に興味を持ってくれている」と感じ、会話が自然に続きます。
例:
相手:「週末、キャンプに行ってきたんだ」
自分:「どこに行ってきたんですか?」「誰と行ったんですか?」
⑤ 話を広げる「拡張オープンクエスチョン」
「はい/いいえ」で終わらない質問(オープンクエスチョン)に、感情や考えを尋ねる言葉をプラスすると、より深い話につながります。
例:
「〇〇について、どう思いましたか?」
「その時、どんな気持ちでしたか?」
「もう少し詳しく教えてもらえますか?」
Step 3《応用編》:心地よい関係を築くために
⑥ 自分のトリセツを伝える「自己開示」
信頼できる相手には、自分の特性を伝えておくのも有効な方法です。「人の話を遮ってしまうことがあるかもしれないけど、悪気はないんだ」「難しい言葉は一度で理解できないことがあるから、簡単な言葉で言ってもらえると助かる」など、事前に伝えておくことで、無用な誤解を防げます。
⑦ 会話に詰まった時の「お助けフレーズ」集
頭が真っ白になってしまった時のために、その場を乗り切るための「お助けフレーズ」を準備しておきましょう。
- 「すみません、少し考えを整理させてください」
- 「面白い視点ですね。もう少し考えてから意見を言ってもいいですか?」
- 「〇〇という理解で合っていますか?」
【周りの人向け】家族・同僚ができるサポートと心地よい関わり方

発達障害のある方のコミュニケーションの困難は、本人の努力だけで解決するものではありません。周りの人の少しの配慮や工夫によって、驚くほど円滑になることがあります。
まずは特性を「知る」ことから始めよう
「空気が読めない」「わがまま」と見えてしまう行動の裏には、悪意ではなく、脳機能の特性が隠れています。まずは、これまで紹介したようなASDやADHDの特性について理解を深めることが、サポートの第一歩です。
すぐに実践できる4つのコミュニケーションのコツ
① 曖昧な表現を避け、具体的に伝える
「あれ、適当にやっておいて」「なるべく早くお願い」といった曖昧な指示は、混乱の原因になります。
- NG例:「この資料、いい感じにまとめといて」
- OK例:「この資料のAとBのデータを引用して、グラフを2つ作り、金曜日の15時までに提出してください」
② 一度に伝える情報は一つだけ
一度に多くの情報を伝えると、処理しきれずにフリーズしてしまうことがあります。指示や依頼は、一つずつ簡潔に伝えることを心がけましょう。
③ 図やテキストなど視覚情報を活用する
口頭での説明に加えて、チャットやメールで要点をテキストで送ったり、簡単な図を描いて説明したりすると、格段に理解しやすくなります。
④ 沈黙を恐れず、考える時間を与える
質問に対してすぐに返事がなくても、それは無視しているわけではなく、頭の中で一生懸命に言葉を探している時間かもしれません。少し待つ姿勢が、本人に安心感を与えます。
「よかれと思って」が逆効果になるNGな関わり方
- 無理に雑談の輪に入れようとする
本人にとっては大きな苦痛である場合があります。 - 「普通はこうだよ」と一般論を押し付ける
特性によって「普通」が難しいことを理解し、具体的な方法を一緒に考える姿勢が大切です。 - 感情的に叱責する
なぜ怒られているのか理解できず、パニックになったり心を閉ざしてしまったりする原因になります。
会話に失敗して落ち込んだ時の心の処方箋

どんなに準備や練習をしても、会話がうまくいかない日はあります。大切なのは、その失敗をどう受け止め、次に活かすかです。
自分を責めないで。失敗は「データ収集」と捉えよう
「またやってしまった…」と自分を責めるのはやめましょう。一つ一つの会話は、あなたにとっての「実験」であり「データ収集」です。「この言い方は伝わりにくかったな」「次は別の聞き方を試してみよう」と、客観的に分析することで、自己肯定感を下げずに次に進めます。
気持ちを切り替える3つのセルフケア
① 事実と感情を書き出して分ける
「会議でうまく発言できず、みんなに呆れられたに違いない」と感じたとします。
これを、「事実(会議で発言できなかった)」と「感情・推測(みんなに呆れられたに違いない)」に分けて紙に書き出してみましょう。事実と感情を切り離すだけで、冷静さを取り戻せます。
② 信頼できる人に話して客観的意見をもらう
一人で抱え込まず、パートナーや友人、カウンセラーなど、信頼できる人に話してみましょう。「自分では大失敗だと思っていたけど、周りはそれほど気にしていなかった」といった客観的なフィードバックが得られるかもしれません。
③ 自分の「好き」に没頭する時間を作る
会話で消耗したエネルギーは、自分の好きなことや得意なことに没頭して回復させましょう。趣味の時間、好きな音楽を聴く、美味しいものを食べるなど、自分が心からリラックスできる活動が、次への活力となります。
仕事の悩みから解放されるために

特に仕事の場面では、コミュニケーションの困難が業務の支障や人間関係のストレスに直結しやすくなります。
職場での具体的な困りごとと対策
| 困りごと | 対策例 |
|---|---|
| 報告・連絡・相談 | ・報告する内容を箇条書きでメモしてから話す。 ・口頭だけでなく、チャットやメールも活用する。 ・「5分だけよろしいですか」と時間を区切って相談する。 |
| 会議 | ・事前にアジェンダを確認し、自分の意見や質問をまとめておく。 ・発言のタイミングが掴めなければ、ファシリテーターに事前に伝えておく。 |
| 雑談 | ・無理に参加せず、会釈や笑顔でやり過ごすのも一つの手。 ・自分の好きなことに関する話題なら、少しだけ話してみる。 |
発達障害の特性を強みに変える働き方とは
コミュニケーションは苦手でも、特定の分野への集中力や、正確な作業を黙々とこなす力、独自の視点などは、大きな強みになります。ITエンジニア、研究職、デザイナー、データ入力など、特性を活かせる職業は数多く存在します。
合理的配慮と活用できる社内・社外の制度
2024年4月に改正された障害者差別解消法により、民間事業者にも「合理的配慮」の提供が義務付けられました(それまでは努力義務でした)。例えば、「指示は口頭ではなく文書で伝えてもらう」「静かな環境で作業させてもらう」といった配慮を求めることが可能です。人事部や産業医、あるいは社外の就労移行支援事業所などに相談してみましょう。
一人で抱え込まないで。専門家や支援機関に相談しよう

もし、日常生活や仕事に大きな支障が出ているなら、専門家や支援機関の力を借りることを検討してください。
相談できる窓口一覧(医療機関・支援センターなど)
- 精神科・心療内科: 発達障害の診断や、二次障害(うつ病など)の治療を行います。
- 発達障害者支援センター: 都道府県・指定都市が設置する専門機関。相談や助言、支援機関の紹介などを行います。
- 就労移行支援事業所: 一般企業への就職を目指す障害のある方向けに、職業トレーニングや就職活動のサポートを提供します。
- 相談支援事業所: 障害のある方の様々な相談に応じ、福祉サービスの利用計画を作成します。
- 相談支援事業所: 障害のある方の様々な相談に応じ、福祉サービスの利用計画を作成します。
また、近くに専門の医療機関がない場合や、通院する時間が取れない場合は、オンラインでの診療や相談も選択肢の一つです。
▶ 仕事や学校の悩み、もしかしてASDが原因かも? 治療法やオンライン診療のメリットについて解説|エニキュア
診断を受けるメリット・デメリット
診断を受けることで、自分の特性を客観的に理解し、必要な支援や配慮を受けやすくなる(障害者手帳の取得、障害者雇用の利用など)というメリットがあります。一方で、診断名がつくことへの心理的な抵抗を感じる方もいるかもしれません。メリット・デメリットをよく考え、専門家と相談しながら決めることが大切です。
自分に合った支援の見つけ方
まずは、お住まいの地域の発達障害者支援センターに連絡してみるのがおすすめです。現状の困りごとを伝えることで、あなたに合った医療機関や支援機関の情報を提供してくれます。
まとめ:自分らしいコミュニケーションを見つける旅へ

会話のキャッチボールができない悩みは、決してあなたのせいではありません。脳の特性によるものです。
重要なのは、一般的な「コミュニケーション上手」を無理に目指すのではなく、自分の特性を理解し、自分に合ったやり方で、相手と心地よい関係を築くことです。
この記事で紹介したトレーニングや工夫は、そのための「杖」や「地図」のようなものです。ぜひ、できそうなものから一つずつ試してみてください。
失敗を恐れず、自分らしいコミュニケーションの形を見つける旅を、今日から始めてみませんか。
【免責事項】
本記事は情報提供を目的としており、医学的な診断や治療、専門的な支援に代わるものではありません。発達障害に関する具体的な困りごとや診断については、必ず専門の医療機関や発達障害者支援センターなどにご相談ください。また、記事内で紹介している対策方法は、すべての方に効果があることを保証するものではありません。ご自身の状況に応じて、無理のない範囲でお試しください。
記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医