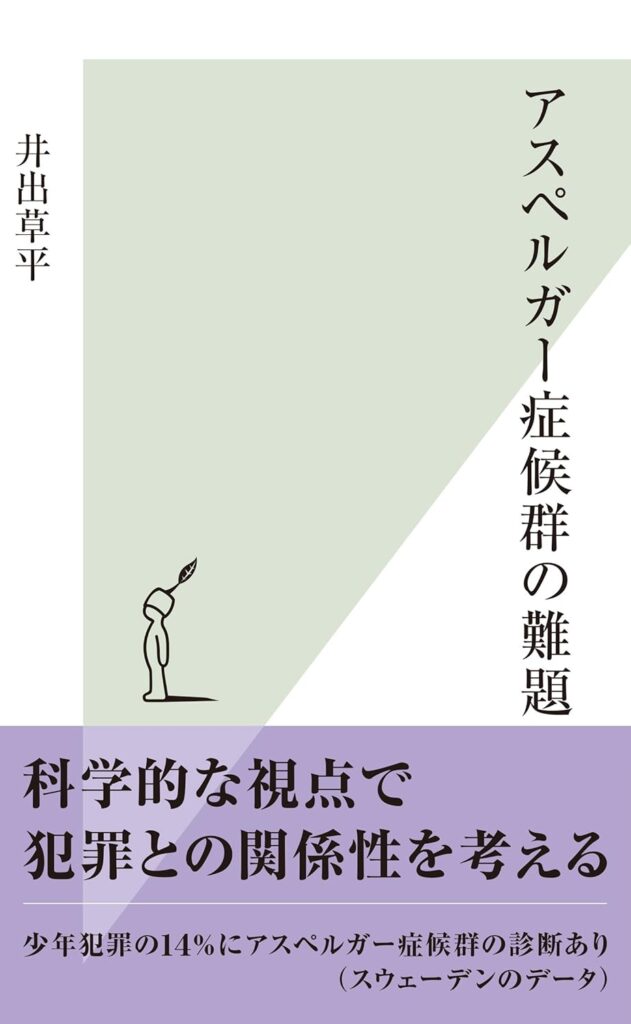「うちの子は大丈夫?」その不安に、データで向き合う勇気をくれる一冊をご紹介します。
発達障害のある子を育てる中で、ふと胸をよぎる不安はありませんか?
テレビで流れる不可解な少年事件のニュース。思春期に入り、少しずつ理解が難しくなっていく我が子の言動。「この子の将来は、本当に大丈夫だろうか…」。誰にも言えないけれど、そんな漠然とした不安が、心の隅にいつも横たわっている。
そんな保護者の方にこそ、今日は少し勇気を出して、一冊の本をご紹介したいと思います。
井出草平さんの『アスペルガー症候群の難題』(光文社新書)。
タイトルを見て、ドキッとしたかもしれません。「アスペルガー」と「犯罪」を結びつけるような本なんて、読みたくない。そう思うのが当然です。私自身、この本を手に取るとき、同じように感じました。
でも、読み終えた今、この本は決して私たちを不安に陥れるものではなく、むしろ冷静な知識という「お守り」を授けてくれる、誠実な一冊だと感じています。
なぜ、今この本を読む意味があるのか

本書は、これまでタブー視されがちだった「アスペルガー症候群の特性と、一部のケースで見られる反社会的行動との関連性」という非常にデリケートなテーマを扱っています。
しかし、そのアプローチは驚くほど冷静です。著者は、個人的な体験談や印象論を一切挟まず、国内外の研究論文や統計データといった「科学的根拠(エビデンス)」だけを頼りに、静かに筆を進めていきます。
だからこそ、私たちは感情的に揺さぶられることなく、この難しい問題を「社会の構造」として客観的に理解することができるのです。
ポイント1:「うちの子」の話ではない。でも、社会を知るために必要。
まず、何よりも強くお伝えしたいのは、本書が「発達障害=犯罪」と短絡的に結びつけるものでは断じてない、ということです。著者が示すデータを見ても、アスペルガー症候群を持つ人のごくごく一部にしか、そうした傾向は見られません。
ではなぜ読む必要があるのか。それは、私たちの愛する子どもたちが生きていく「社会」が、この問題をどう見て、なぜ誤解してしまうのかを知るためです。社会の偏見や無理解から子どもを守るために、私たちはまず、その「偏見の正体」を冷静に知る必要があるのです。
ポイント2:「心の闇」ではなく「支援の不足」が問題だとわかる

これまで不可解な事件は「心の闇」という曖昧な言葉で片付けられてきました。しかし本書は、問題の根本は個人の心ではなく、社会全体の「支援の不足」にあると教えてくれます。
特に胸に迫るのは、暴力行為の「防波堤」が家族、とりわけ母親に押し付けられているという現実です。家庭内で起こる他害行為や、それに疲弊していく家族の姿。これは、決してひとつの家庭だけで抱え込む問題ではありません。社会が、行政が、もっと早く手を差し伸べるべき構造的な課題なのだと、本書は気づかせてくれます。
ポイント3:未来への具体的な「備え」のヒントが見つかる

本書は、問題を指摘するだけで終わりません。
- 早期発見と早期介入の重要性
- 親が子育ての方法を学ぶ「ペアレント・トレーニング」の有効性
- 学校現場における特別支援教育の課題
など、具体的な予防策や支援のあり方についても言及されています。
漠然と将来を憂うのではなく、「今、親として何ができるのか」「社会や学校に何を求めていくべきか」という、次の一歩を踏み出すための具体的な羅針盤となってくれるはずです。
こんな保護者の方に読んでほしい

- 思春期のお子さんの言動に戸惑い、将来に不安を感じている方
- ニュースで発達障害と事件が結びつけて語られるたびに、胸を痛めている方
- お子さんのために、社会や学校、行政にどんな支援を求めていけばいいか、具体的な視点が欲しい方
- 感情的にではなく、冷静な知識として我が子のこと、そして社会との関わりを学びたい方
この本を読むことは、決して楽な体験ではないかもしれません。ページをめくるたびに、胸が苦しくなる瞬間もあるでしょう。
でも、どうか恐れないでください。
読み終えたとき、あなたの心の中にある漠然とした黒い霧のような不安は、きっと「解決すべき具体的な課題」へと姿を変えているはずです。そしてそれは、闇雲に怯えるのではなく、前に進むための確かな一歩となります。
一人で抱え込まず、まずは正しい知識を手にすることから始めてみませんか。この本は、そのための、最も信頼できるパートナーの一人になってくれると信じています。